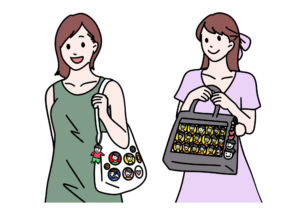なぜ、あくびはうつるのか? 最新科学が解き明かす「共感」と「脳冷却」の不思議な関係

午後3時の会議室。少しだけ重たい空気の中、隣の席の同僚が小さくあくびをしました。すると、なぜか自分もあくびがしたくなる——。数秒後、向かいの席の人も、その隣の人も。あくびが部屋中に広がっていきます。
あなたも、こんな経験ありませんか?
「退屈な会議のせいでしょ」と片付けてしまいがちですが、ちょっと待ってください。もしこの何気ない「あくびの伝染」が、私たち人間が互いにつながり合う仕組みによるとしたら?
なぜあくびはうつるのか——。この問いを入り口に、脳科学と心理学が解き明かしつつある、私たちの心と脳をつなぐ不思議なメカニズムを探る旅に出かけましょう。
この記事を読み終わる頃には、ありふれた「あくび」という行為が、少しだけ面白く、そして愛おしく見えてくるかもしれません。
- 1. 心のシンクロ?「ものまね細胞」が生む共感
- 1.1. 相手の「だるさ」を、無意識に感じている?
- 1.2. 親しい人ほどよくうつる? 感情のつながりが鍵
- 1.3. 種を超えた絆〜動物たちが教えてくれること〜
- 2. あくびにまつわる意外な話
- 2.1. 「酸素不足説」は間違いだった
- 2.2. 人生で最初のあくび、それはお腹の中で
- 2.3. あくびを「武器」にした人たち
- 3. 脳のクーリングシステム?体の知恵としてのあくび
- 3.1. あくびは、脳に内蔵されたラジエーター
- 3.2. 「ちょうどいい温度」が証明する脳冷却
- 3.3. 2つの仮説比較
- 4. 2つの仮説は対立していない?
- 4.1. 進化が重ね着した機能
- 4.2. つられ笑いとカメレオン効果
- 4.3. 意志では止められない? 脳の自動プログラム
- 5. おわりに
- 5.1. 参考
心のシンクロ?「ものまね細胞」が生む共感

相手の「だるさ」を、無意識に感じている?
あくびの伝染について、最も直感的で分かりやすいのが「共感仮説」です。これは、他人があくびをするのを見ると、その人の「眠い」「疲れた」「退屈だ」といった内面の状態を、私たちが無意識のうちに理解し、共有してしまうために起こる、という考え方です。
この心の動きを支えているのが、脳の中にある「ミラーニューロン」と呼ばれる神経細胞だと考えられています。「ものまね細胞」と想像してみてください。誰かが微笑むのを見ると、この細胞がまるで「自分自身が」微笑んでいるかのように活動し、相手の喜びのかけらを私たちに感じさせてくれるのです。
あくびも同じです。他人のあくびという行動を観察したミラーニューロンが、私たちの脳内でその行動をシミュレートし、「自分もあくびをすべき状態だ」という感覚を生み出します。これは単なる模倣ではなく、相手の心身の状態を追体験する、とても原始的な形の共感なのです。
親しい人ほどよくうつる? 感情のつながりが鍵
この共感仮説を裏付ける、とても興味深い発見があります。それは、「誰から」あくびがうつるか、という点です。
研究によれば、あくびの伝染は、見知らぬ人よりも知人、知人よりも友人や家族といった、感情的なつながりが強い相手からの方がはるかに起こりやすいことが分かっています。これは「感情バイアス仮説」と呼ばれ、あくびの伝染が単なる視覚的な反応ではなく、相手との絆の強さに応じて変わる社会的な現象であることを示しています。
この現象は、オン・オフのスイッチではありません。むしろ、音量のボリュームダイヤルのようなものです。見知らぬ人のあくびは、私たちの脳にとって小さなささやきかもしれませんが、大切な家族のあくびは、無視しがたい大きなシグナルとして届くのです。
さらに面白いのは、この「うつるあくび」が、他者の心を理解する能力(「心の理論」と呼ばれます)が発達する4〜5歳頃の子どもから現れ始めるという事実です。このことは、あくびの伝染が、私たちの社会性や共感能力の発達と深く結びついていることを物語っています。
種を超えた絆〜動物たちが教えてくれること〜
この不思議な伝染は、人間だけのものではありません。私たちの身近な友達である動物たちも、興味深い証拠を見せてくれます。
特に有名なのが犬の研究です。複数の研究で、犬は見知らぬ人のあくびよりも、毎日を一緒に過ごす飼い主のあくびに対して、より強く反応し、あくびを「もらう」ことが示されています。これは、犬と人間の間に存在する強い絆が、種を超えた共感の形で現れている可能性を示唆しています。
また、私たちに最も近い親戚であるチンパンジーも、同じような行動を見せます。彼らもまた、見慣れた仲間のあくびにはよくつられますが、知らない個体のあくびにはあまり反応しません。この事実は、あくびの伝染という行動が、社会的な動物に共通する、進化的に古いルーツを持つものであることを教えてくれます。
もちろん、科学の世界では常に議論が続いています。近年の研究では、犬のあくびと共感の直接的な結びつきに疑問を呈するものもあります。こうした議論は、目に見えない「共感」という心を、どうやって客観的に測るのかという、科学の面白さと難しさそのものを浮き彫りにしています。
あくびにまつわる意外な話

共感の話から少しだけ寄り道して、あくびそのものに関する面白い事実をいくつかご紹介しましょう。
「酸素不足説」は間違いだった
まず、最も有名な誤解を解いておきます。「あくびは脳の酸素が足りないから出る」という話、聞いたことありませんか?実はこれ、1987年に行われたロバート・プロヴァイン氏らの研究によって、はっきりと否定されています。実験では、高濃度の酸素や二酸化炭素を吸っても、あくびの回数に変化は見られませんでした。
人生で最初のあくび、それはお腹の中で
では、私たちの「最初のあくび」はいつなのでしょうか。驚くべきことに、それは母親のお腹の中にいる、妊娠11〜20週頃にはもう始まっているのです。これは、あくびが後から学ぶ行動ではなく、私たちの体に深く刻み込まれた、とても原始的な生理反応であることを示しています。
このお腹の中のあくびは「自発的あくび」と呼ばれ、誰かからうつる「伝染性あくび」とは区別されます。この違いが、実は重要なヒントになってきます。
あくびを「武器」にした人たち
最後に、あくびを戦略的に使った人物の話を。将棋の升田幸三名人は、大事な一手を指す前にあくびをすることで知られていました。また、俳人の高浜虚子も、句を詠む前にあくびをしたと言います。彼らにとってあくびは、眠気のサインではなく、むしろ脳を最高の状態に整えるための儀式だったのかもしれません。
その謎を解く鍵が、次にご紹介するもう一つの仮説に隠されています。
脳のクーリングシステム?体の知恵としてのあくび

あくびは、脳に内蔵されたラジエーター
共感仮説が「心」の側面からあくびに迫るものだとすれば、もう一つの有力な説は、より直接的に「体」の機能に焦点を当てます。その名も「脳冷却仮説」。
この説を提唱する科学者たちは、あくびを「脳に内蔵されたラジエーターのスイッチが入る瞬間」のようなものだと考えています。私たちの脳は、パソコンのCPUのように、活動すればするほど熱を発生させます。そして、脳は熱にとても弱く、最適なパフォーマンスを発揮できる温度範囲はごくわずかです。
この仮説によれば、あくびは過熱した脳を冷やすための、とても巧妙な仕組みなのです。その仕組みは主に二つです。
血流の促進:あくびで顎を大きく、力強く開くことで、顔周りの筋肉が収縮し、脳への血流が一時的に増加します。これにより、脳に溜まった温かい血液が押し流されます。
冷たい空気の吸入:同時に、冷たい外気を深く吸い込むことで、鼻や口の周辺を流れる血液が冷やされます。その冷やされた血液が脳へと送られ、脳全体の温度を下げるのです。
「ちょうどいい温度」が証明する脳冷却
この脳冷却仮説を裏付ける、とても説得力のある証拠が「サーマル・ウィンドウ(最適温度領域)」と呼ばれる現象です。
プリンストン大学のアンドリュー・ギャラップ氏らの研究チームは、あくびの頻度が外気温と不思議な関係にあることを発見しました。もしあくびが脳を冷やすためなら、外の空気が体温と同じくらい暑い時には、冷たい空気を吸い込んでも冷却効果は期待できません。逆に、凍えるほど寒い時には、冷たすぎる空気を吸い込むのは体に害をもたらす可能性があります。つまり、あくびによる冷却が最も効率的に働く「ちょうどいい」温度があるはずです。
研究の結果、まさしくその通りでした。あくびの頻度は、外気温がおよそ20℃前後の時にピークに達し、それより暑すぎても寒すぎても減少したのです。
この仮説を検証するために行われた、オーストリアのウィーンとアメリカのアリゾナでの比較研究は見事です。ウィーンでは冬より夏に、逆に乾燥したアリゾナでは夏より冬にあくびの回数が増えました。季節や日照時間ではなく、両地域であくびが最も多かったのは、気温が20℃前後の時だったのです。これは、あくびが脳の温度調節という物理的な目的を持っていることの強力な証拠と言えるでしょう。
2つの仮説比較
| 特徴 | 共感仮説 | 脳冷却仮説 |
|---|---|---|
| 主な機能 | 社会的絆の強化、コミュニケーション | 生理的な脳の温度調節 |
| 中心的な仕組み | ミラーニューロンの活動、無意識の模倣 | 血流増加と冷気吸入による脳温低下 |
| 主な引き金 | 他者のあくびを見る・聞く・考える | 脳の温度上昇 |
| 最も強力な証拠 | 親しい人ほどうつりやすい | 外気温約20℃で頻度が最大化 |
| 進化上の起源 | 高度な社会性を持つ種で発達 | ほとんどの脊椎動物に見られる古い反射 |
2つの仮説は対立していない?
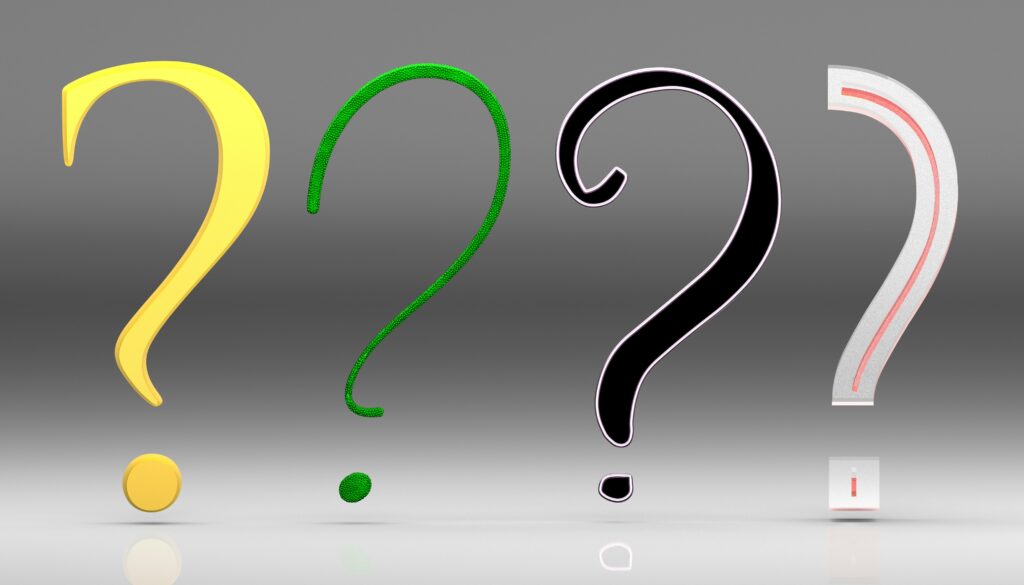
さて、私たちは二つの有力な仮説を見てきました。一つは「心」のつながりを語る共感仮説、もう一つは「体」の仕組みを語る脳冷却仮説。これらは全く別の話なのでしょうか?それとも、どこかでつながっているのでしょうか。
進化が重ね着した機能
最も美しい答えは、これら二つの説が対立するものではなく、一つの物語の異なる側面を説明している、と考えることです。それは、進化の過程で起きた「機能の重ね着」のような物語です。
まず、大元となる原始的な機能は、脳の冷却という生理的な目的(自発的あくび)でした。これは多くの動物に見られる基本的な生命維持システムです。
しかし、人間のように高度な社会を作る動物にとって、仲間が「今、脳の温度が上がって、注意力が落ちかけている」という内部状態を知らせるサインは、とても価値のある情報でした。そこで、この「脳の冷却」という目に見える行動が、集団の注意レベルを揃えるための強力な社会的シグナルとして使われるようになったのです。
群れの一員があくびをするのを見て、他のメンバーもつられてあくびをすることで、集団全体の脳が「クールダウン」し、警戒態勢を同時にリフレッシュする。これは、外敵から身を守る上で、計り知れない進化的な利点となったでしょう。
つまり、脳冷却という生理的な土台の上に、共感という社会的な機能が重ね着され、その実行プログラムとして脳の神経回路が配線された——この多層的なモデルこそが、あくびの伝染の全体像を最もよく説明してくれるのです。
つられ笑いとカメレオン効果
この「伝染」という現象は、あくびだけの特別なものではありません。私たちの周りには、あくびの「いとこ」と呼べるような、様々な社会的伝染が存在します。
その代表格が「つられ笑い」です。誰かが楽しそうに笑っていると、理由も分からないのにつられて笑ってしまった経験は誰にでもあるでしょう。これもまた、ミラーニューロンの働きが関わっており、笑い声が伝染することで、集団内に一体感と安心感を生み出し、社会的な絆を強める効果があります。
さらに、会話中に相手が無意識に脚を組んだり、顔に触れたりすると、自分も同じ仕草をしてしまう「カメレオン効果」と呼ばれる現象もあります。これらはすべて、私たちが社会的な動物として、無意識のうちに周囲と自分を同調させ、円滑な人間関係を築くために備わった、見えない糸のような仕組みなのです。
意志では止められない? 脳の自動プログラム
伝染性のあくびのもう一つの特徴は、その「抗いがたさ」です。あくびがうつりそうになった時、「我慢しよう」とすればするほど、かえって強い衝動に駆られたことはありませんか?
イギリスのノッティンガム大学の研究チームは、この衝動が脳の「一次運動野」と呼ばれる、体の動きを指令する領域の興奮しやすさと関連していることを突き止めました。つまり、伝染性のあくびは、私たちが意識的にコントロールできる範囲の外にある、かなり自動化された本能的なプログラムなのです。
この発見は、トゥレット症候群など、本人の意思とは無関係に模倣的な動きが現れる症状の解明にもつながる可能性があると期待されています。
おわりに
会議室での一つのあくびから始まった私たちの旅は、脳の奥深く、そして人類進化の遥かな道のりへと広がりました。
結局のところ、あくびはなぜうつるのか?その問いに対する完璧な単一の答えは、まだ見つかっていません。共感の役割を重視する研究もあれば、年齢などの他の要因がより重要だと指摘する研究もあり、科学の探求は今も続いています。
しかし、確かなことがあります。次にあなたが誰かのあくびを目にした時、あるいは自分自身があくびをした時、その見え方は少しだけ変わっているはずです。
そこに見えるのは、もはや単なる眠気や退屈のサインではありません。
それは、高性能な脳を最適な状態に保つための、古くから受け継がれてきた生命の知恵の現れです。
それは、社会的な動物として生き抜くために、仲間と状態を同期させてきた、私たちの進化の歴史のこだまです。
そして何より、それはミラーニューロンによって織りなされる、私たちを互いに結びつける共感という見えない糸の証なのです。
あくびは、失礼な行為などではありません。それは、私たちの体が無意識のうちに奏でる、人間という存在の生物学的な奥深さと、その根源的な社会性を物語る、美しくも不思議な証しなのです。
【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】
PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?
参考
- あくびがうつる理由 | 野毛整骨院|横浜市中区(関内駅・桜木町駅)の整骨院新
- Why Is Yawning Contagious? | Psychology Today
- どうせ影響されるなら…ミラーニューロンの使い方|ペスハム@【多動迷子コーチング】 - note
- 「私」を映し出す「ミラーニューロン」 - 聖書と科学 - WATV
- “見てるだけで、なぜか伝わる”——ミラーニューロンが支える共感と学びのメカニズム - note
- Individual Variation in Contagious Yawning Susceptibility Is Highly ...
- Auditory Contagious Yawning Is Highest Between Friends ... - Frontiers
- 友だちのあくびは、なぜわたしにうつるの? | ヒト | 科学なぜなぜ110番 | 科学 - 学研キッズ
- 人のあくびはイヌにもうつる!? | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
- 飼い主さんのあくびがうつることも? 犬のあくびの意外な理由
- 犬にもあくびがうつる?犬と人のシンクロが科学的に証明された!
- 人から犬へのあくびの伝染は共感の表れではない【研究結果】 | わん
- ヒト、ライオン、ジュゴンも......あくびはなぜ伝染する?|Lifestyle - フィガロジャポン
- The thermoregulatory theory of yawning: what we know from over 5 years of research - PMC
- YAWNS ARE COOL - Frontiers
- 【Vol.5】胎動ってなんでしょう?その疑問とフシギ(No.5) 彡横浜戸塚から発信 | 小川クリニック
- 胎児のなぜ?【医師監修】 - ヒロクリニック
- あくびの生物学的意義と伝染機序 - 日本医事新報社
- あくび、何のため? - 大阪市西区の歯医者なら - 新町プラザ歯科
- 先生!あくびってなんのためにあるの? - つじファミリークリニック
- Why Do We Yawn? A Closer Look - Dr. Mayank Shukla
- Yawning to cool the brain
- A Thermal Window for Yawning in Humans - NSUWorks
- A thermal window for yawning in humans: yawning as a brain cooling mechanism - PubMed
- 【雑学心理学】なぜ笑いはつられるのか?|ZATU-学 - note
- 同調行動の心理とその影響:賢く活かす方法|Communication Catalyst - note
- 9月4日 あくびがうつる現象の脳科学(9月11号Current Biology掲載論文) - AASJホームページ
- あくびはなぜ伝染しやすいのか、その謎を科学的に解説
- Contagious Yawning May Not Be Linked to Empathy; Still Largely Unexplained