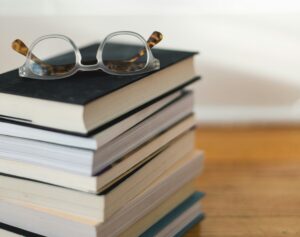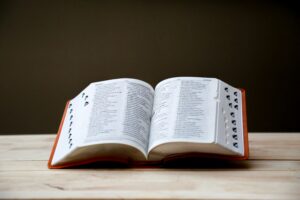エスカレーターで片側を空ける理由とは?「見えない手すり」が語る社会の心理【空けるのは右側? 左側?】

朝の喧騒に満ちた巨大ターミナル駅。無数の人々が、まるで意思を持った一つの奔流のように、改札からホームへと吸い込まれていきます。その流れがエスカレーターの前に差し掛かった瞬間、不思議な光景が広がります。
誰の指示もなく、一言の会話も交わされることなく、人々は自然と二つの列に分かれるのです。片方は静かに立ち止まる人々の列、もう片方は足早に駆け上がっていく人々のための、がらんとした空間。
私たちは、互いに見知らぬ赤の他人でありながら、なぜこれほどまでに正確に、この暗黙のルールに従うのでしょうか。この誰もが経験している「当たり前」の光景にこそ、私たちの社会を動かす、深く、そして面白い力学が隠されています。
- 1. 二つの都市と、世界を巡る物語
- 1.1. 東京「左立ち」の深い文化的ルーツ
- 1.2. 大阪「右立ち」の意図的な近代化
- 1.3. 境界の曖昧さが示す文化の流動性
- 1.4. グローバルな視点と「大阪のパラドックス」
- 1.5. 国家アイデンティティの文化的装置
- 2. 機械の中の幽霊〜最初の乗客を探して〜
- 2.1. 忘れられた技術的制約
- 2.2. 戦時下での習慣の強化
- 2.3. 「舶来のマナー」の日本への旅
- 2.4. 社会規範のライフサイクル
- 3. 見えざる契約〜群衆が生み出す力〜
- 3.1. 「共有知識」という名の接着剤
- 3.2. 同調圧力と多元的無知の罠
- 3.3. エスカレーターという「規範エンジン」
- 4. 効率のパラドックスと安全性のジレンマ
- 4.1. 効率という名の幻想
- 4.2. 二つの効率性という社会哲学の対立
- 4.3. 安全性とアクセシビリティという至上命題
- 4.4. マジョリティの利便性とマイノリティの権利
- 5. 「ナッジ」と条例〜変わりゆく暗黙のルール〜
- 5.1. 変化への挑戦
- 5.2. 条例による制度的アプローチ
- 5.3. 埼玉の経験と名古屋の学習
- 5.4. 「当たり前」を解体する難しさ
- 6. おわりに〜エスカレーターは社会を映す鏡〜
- 6.1. 複雑なタペストリーが織りなす社会
- 6.2. 正解のない問いが示すもの
- 6.3. 見えざる糸で結ばれた社会契約
- 6.4. 参考
二つの都市と、世界を巡る物語

日本におけるエスカレーターの「片側空け」問題で最も有名なのが、関東と関西の立ち位置の違いでしょう。
- 東京を中心とする関東:「左立ち・右空け」
- 大阪を中心とする関西:「右立ち・左空け」
この違いは、しばしば東西の文化的な差異を象徴する例として語られます。
東京「左立ち」の深い文化的ルーツ
東京の「左立ち」の起源として有力視されているのが、「武士の作法」に由来するという説です。江戸時代、武士は刀を左腰に差していました。そのため、鞘同士がぶつかり無用な争いを避けるため、自然と左側通行の習慣が根付いたと言われます。
この歴史的な身体感覚が、現代の道路交通法(日本は左側通行)にも受け継がれ、エスカレーターでも無意識のうちに左側に立つようになった、というわけです。これは、深い文化的な記憶が現代の行動様式に影響を与えている可能性を示唆しています。
大阪「右立ち」の意図的な近代化
一方、大阪の「右立ち」は、より近代的で意図的な起源を持ちます。そのきっかけは、1967年に阪急電鉄(当時、京阪神急行電鉄)が梅田駅に長いエスカレーターと動く歩道を設置した際に、「お急ぎの方のために片側を空ける」ようアナウンスを始めたことにあります。
そして、この習慣が決定的に定着したのは、1970年に開催された大阪万博でした。世界中から訪れる人々を迎えるにあたり、「国際標準」に合わせるという意識から、右立ち・左空けが推奨されたのです。
ここには、歴史的な慣性から生まれた東京のルールと、近代化と国際化を意識して人為的に導入された大阪のルールという、興味深い対比構造が見て取れます。
境界の曖昧さが示す文化の流動性
しかし、この境界線は明確な一本線で引かれているわけではありません。鉄道沿線での調査によれば、文化圏が接する地域では、立ち位置が徐々に変化していく様子が観察されています。
例えば、京都は関西にありながら東京と同じ左立ちが主流であり、滋賀もその影響を受けています。名古屋は左立ちが基本ですが、明確なルールがないと感じる人もいます。
この「境界の曖昧さ」は、文化的な規範が固定されたものではなく、人々の移動や相互作用の中で常に揺らぎ、混じり合っていることを示しています。
グローバルな視点と「大阪のパラドックス」
視点を世界に広げると、さらに面白い事実が浮かび上がります。大阪が目指した「国際標準」は、実はその名の通り、世界の大半の地域で採用されているルールなのです。
| 都市・地域 | 立ち位置 | 歩行側 | 車両通行区分 | 起源・背景の可能性 |
|---|---|---|---|---|
| ロンドン(英国) | 右 | 左 | 左側通行 | 初期設計、戦時下の要請 |
| パリ(フランス) | 右 | 左 | 右側通行 | 車両通行区分と一致 |
| ニューヨーク(米国) | 右 | 左 | 右側通行 | 車両通行区分と一致 |
| ソウル(韓国) | 右 | 左 | 右側通行 | 車両通行区分と一致 |
| 北京(中国) | 右 | 左 | 右側通行 | オリンピックを機に導入 |
| 台北(台湾) | 右 | 左 | 右側通行 | 車両通行区分と一致 |
| シドニー(豪州) | 左 | 右 | 左側通行 | 車両通行区分と一致 |
| 大阪(日本) | 右 | 左 | 左側通行 | 万博を機に国際標準を導入 |
| 東京(日本) | 左 | 右 | 左側通行 | 武士の習慣、車両通行区分と一致 |
この表から明らかなように、世界の大多数の国、特に車両が右側通行の国では、「右立ち・左空け」が一般的です。追い越し車線が左側にあるという日常的な感覚が、エスカレーターの利用法にも反映されていると考えられます。
ここで際立つのが、ロンドンと関東の「例外性」です。どちらも左側通行の国・地域でありながら、世界の主流とは独自のルールを採用しています。この事実は、問いの立て方を根本から変えます。「なぜ関東と関西は違うのか?」という問いは、より深く、「なぜ左側通行の地域は、世界的なパターンから逸脱する傾向があるのか?」という普遍的な謎へと昇華されるのです。
国家アイデンティティの文化的装置
このグローバルな文脈は、もう一つの重要な側面を照らし出します。大阪や北京における片側空けルールの導入が、万博やオリンピックといった国家的な一大イベントと密接に結びついている点です。
これらのイベントは、国が世界に対して自らの姿を披露する、いわば国際的な舞台です。その舞台の上で、整然としたエスカレーターの利用風景は、その国が近代的で、秩序があり、洗練されていることを示すための、安価で効果的なパフォーマンスとなります。
つまり、片側空けというルールは、単なる効率性の追求や習慣の結果ではなく、国家のアイデンティティを演出し、ソフトパワーを誇示するための「文化的な装置」としての役割を担ってきたのです。
機械の中の幽霊〜最初の乗客を探して〜
エスカレーターの片側空けという習慣の起源を遡ると、その源流は20世紀初頭のロンドンに行き着く可能性が高いです。当時、世界最先端の都市であったロンドンの地下鉄に、この新しい機械が導入されたことがすべての始まりでした。
忘れられた技術的制約
最も有力な説は、初期のエスカレーターが持っていた特異な設計に起因するというものです。1911年にアールズ・コート駅に設置された最初期のエスカレーターの一つは、降り口が現代のようにまっすぐではなく、斜め(くし状)になっていました。
乗客は進行方向に対して横向きに降りる必要があり、その際、自然と左足を先に出す形になりました。この動作をスムーズに行うためには、右側に立っている方が都合が良かったのです。
忘れ去られた過去の技術的制約が、一世紀以上にわたる人々の行動様式を決定づけたとすれば、それはまさに「機械の中の幽霊」と呼ぶにふさわしいでしょう。
戦時下での習慣の強化
この習慣は、第二次世界大戦中にさらに強化されたという説もあります。ロンドン地下鉄の駅は巨大な防空壕として利用され、負傷者や軍関係者が迅速に移動できるよう、エスカレーターの片側を常に確保しておく必要がありました。
実際に、「右側に立ち、左側を空けるように」と呼びかけるポスターが貼られ、平時における利便性のためのマナーが、戦時下における緊急性のためのルールへと変容したのです。
加えて、初期のエスカレーターには手すりが片側(右側)にしかなかったものも存在し、物理的に右側に立つことを促していました。
「舶来のマナー」の日本への旅
こうしてロンドンで生まれた「右立ち・左空け」の習慣は、やがて世界へと広がっていきます。日本においては、戦後の高度経済成長期に、この「舶来のマナー」が輸入されたと考えられます。
当時の日本では、欧米の文化や生活様式が憧れの対象であり、海外渡航者などを通じて、その洗練されたマナーが紹介されました。新聞の投書欄には、欧米の駅設備と比較して日本の遅れを嘆く声がたびたび掲載されたといいます。
このような社会的な背景があったからこそ、大阪万博の際に阪急電鉄が「国際標準」として右立ちを呼びかけたとき、人々はそれを近代的でスマートな行動様式として、比較的スムーズに受け入れたのでしょう。
社会規範のライフサイクル
ここには、一つの社会規範がたどる興味深いライフサイクルが見て取れます。
- テクノロジーによって誕生:ロンドンの事例のように、特定の技術的制約(斜めの降り口)への適応として規範が生まれる
- 文化として成熟:技術が時代遅れになった後も、行動様式だけが残り、人々はその起源を忘れたまま習慣として受け継ぐ
- アイデアとして移植:成熟した文化が、まったく異なる文脈を持つ別の社会(大阪など)に、洗練された文化として移植される
エスカレーターの片側空けルールは、まさにこの「誕生・成熟・移植」というプロセスを完璧に体現した、生きた文化的遺物なのです。
見えざる契約〜群衆が生み出す力〜

なぜ、法律でも規則でもないこの「片側空け」ルールが、これほどまでに強力な拘束力を持つのでしょうか。その答えは、社会心理学を通して見えてきます。
「共有知識」という名の接着剤
このルールが維持される核心には、「共有知識(Common Knowledge)」というゲーム理論の概念があります。これは単に「皆がルールを知っている」という状態ではありません。
「皆がルールを知っているということを、皆が知っている」状態であり、さらに「『皆がルールを知っているということを、皆が知っている』ということを、皆が知っている」というように、無限に入れ子構造になった相互認識の状態を指します。
エスカレーターの場面に当てはめてみましょう。あなたが左側(関東の場合)に立つのは、単にルールを知っているからだけではありません。「後ろから来る人も、右側を歩くための通路だと認識しているだろう」と予測するからです。
そして、もし自分が右側に立ち止まれば、その人の通行を妨げ、無言の圧力や、時には舌打ち、あるいは直接的な注意を受けるかもしれないと考えます。
つまり、「皆が左立ちをする」という状況では、自分もそれに従うことが、摩擦を避けるための最も合理的な選択となるのです。この強力な相互予測の網の目こそが、ルールを自己強化させ、逸脱を困難にしています。
同調圧力と多元的無知の罠
この合理的な選択を後押しするのが、「同調圧力」という人間の根源的な心理です。特に、駅のような匿名の公共空間では、人々は周囲の行動に合わせることで安心感を得ようとします。
「決められた」側と逆の場所に立つことは、悪意がなくとも集団の中で悪目立ちし、不快な感覚を伴います。エスカレーターは、この同調のメカニズムがリアルタイムで作用する、小さな社会実験の場なのです。
さらに興味深いのは、「多元的無知(Pluralistic Ignorance)」という現象です。これは、集団の多くのメンバーが、内心ではある規範に疑問を感じていたり反対していたりするにもかかわらず、他の誰もがその規範を受け入れていると誤って信じ込み、結果として全員がその規範に従い続けてしまう状況を指します。
エスカレーターに関する調査では、回答者の大多数が「歩行は危険なのでやめた方がよい」と考えている一方で、同じく大多数が「実際に歩いてしまうことがある」または「歩く人のために片側を空けてしまう」と答えています。
この「本音(危ないと思う)」と「建前(空けてしまう)」の間に存在する巨大なギャップこそが、多元的無知の典型例です。誰もが「本当は両側に立つべきかもしれない」と思いながらも、「周りが皆、片側を空けているから、それが期待されている行動なのだろう」と推測し、不本意ながらルールに従ってしまいます。
エスカレーターという「規範エンジン」
そして、エスカレーターという機械そのものが、こうした社会規範を生成・強化するのに非常に適した構造を持っている点も見逃せません。
エスカレーターは、広場のように自由な移動が許される空間とは異なり、人々を狭く、直線的で、一方通行の空間に閉じ込めます。そこでは、自分の行動がすぐ後ろの人物に直接的かつ即座に影響を与えます。そして、全員の目的は「もう一方の端に着く」という一点で共有されています。
このような高圧的で単純化された社会的環境は、「こちらに立つ、あちらを歩く」というようなシンプルな二元論的ルールが生まれ、摩擦を減らすための調整メカニズムとして絶大な価値を持つ場となります。
したがって、エスカレーターは社会規範が演じられる単なる受動的な舞台ではなく、その生成と強化を促す「規範エンジン」とでも言うべき、能動的な触媒として機能しているのです。
効率のパラドックスと安全性のジレンマ

長年にわたり、「片側空け」は急ぐ人のための「効率的」な慣習だと信じられてきました。しかし、その大前提は、近年、効率性と安全性の両面から根本的な挑戦を受けています。
効率という名の幻想
この慣習の効率性に疑問を投げかけた象徴的な出来事が、2016年にロンドンのホルボーン駅で行われた社会実験です。混雑が激しいことで知られるこの駅で、ロンドン交通局は利用者にエスカレーターの両側に立つよう呼びかけ、歩行を禁止しました。
その結果は驚くべきものでした。ラッシュ時の輸送能力が、片側空けの時と比較して約30%も向上したのです。
なぜこのような逆説的な結果が生まれるのでしょうか。交通渋滞の専門家によれば、その理由は歩行者と静止者の密度の違いにあります。歩行者は安全のために前の人との間に十分なスペース(パーソナルスペース)を必要とします。
そのため、同じ長さのエスカレーターでも、「歩行レーン」に収容できる人数は、「静止レーン」にびっしりと並んだ人数よりもはるかに少なくなります。結果として、歩く人の割合が極端に高くない限り、片側を遊ばせておくことはシステム全体の輸送効率を低下させるボトルネックとなるのです。
多くの駅で目にする、静止側だけに長い行列ができ、歩行側はまばら、という非効率な光景は、この理論を裏付けています。
二つの効率性という社会哲学の対立
この現象は、私たちの社会における二つの異なる「効率」の概念の衝突を浮き彫りにします。
| 効率性の種類 | 対象 | 評価指標 | 片側空けでの状況 |
|---|---|---|---|
| 主観的・個人的効率 | エスカレーターを駆け上がる個人 | 移動時間短縮 | ✓ 確実に向上 |
| 客観的・全体的効率 | システム全体 | 輸送能力最大化 | ✗ 低下する |
片側空けの慣習は、前者の「急ぐ個人のための効率」を最大化しようとする暗黙の合意に基づいています。一方で、両側立ちの推奨は、後者の「システム全体の輸送量」を最大化しようとする試みです。
つまり、エスカレーターの乗り方をめぐる議論は、公共空間という限られたリソースを、少数の個人の緊急性に奉仕させるべきか、それとも多数の集団の全体最適に奉仕させるべきか、という二つの異なる社会哲学の間の代理戦争とも言えるのです。
安全性とアクセシビリティという至上命題
現代において「両側立ち」が推奨される最大の理由は、効率性以上に、安全性とアクセシビリティ(誰もが利用しやすいこと)への配慮にあります。
そもそも、エスカレーターは歩行を前提に設計されていません。建築基準法で定められた階段の蹴上(一段の高さ)の基準とは異なり、エスカレーターの段差は不規則で高いため、つまずきや踏み外しのリスクが高いのです。
また、緊急停止した際の衝撃は想像以上に大きく、手すりに掴まっていなければ転倒・転落する危険性が非常に高くなります。
マジョリティの利便性とマイノリティの権利
そして何より重要なのは、この「片側空け」という暗黙のルールによって、移動が困難になっている人々が存在するという事実です。
病気や障がい、怪我などにより、体の片側が不自由な人は、特定の手すりにしか掴まることができません。例えば、右半身に麻痺がある人は、左側の手すりに頼らざるを得ません。
しかし、関東の「左立ち・右空け」ルールの中では、その左側は静止レーンとなり、右側の手すりを使うことを強要されます。彼らにとって、人々が善意で空けている「歩行レーン」は、感謝すべき配慮ではなく、利用を阻む冷たい壁となるのです。
この事実は、マジョリティの利便性のために生まれた慣習が、いかにマイノリティの安全を脅かしうるかという、社会の普遍的なジレンマを突きつけています。
「ナッジ」と条例〜変わりゆく暗黙のルール〜

長らく自明とされてきた「片側空け」の慣習は、今、大きな転換期を迎えています。全国の鉄道事業者や自治体は、この根深い社会規範を変えようと、様々な試みを続けています。
変化への挑戦
その動きの代表格が、全国の鉄道事業者60社局以上が共同で実施する「エスカレーター『歩かず立ち止まろう』キャンペーン」です。駅の至る所にポスターが掲示され、アナウンスが流れますが、その効果は限定的だという声も多くあります。
第3章で見たように、強力な同調圧力と共有知識によって支えられた慣習は、単なる呼びかけだけで覆すのは極めて困難なのです。
条例による制度的アプローチ
そこで登場したのが、より強制力のある「条例」によるアプローチです。2021年10月、埼玉県は全国で初めて、エスカレーター利用者の「立ち止まり義務」を定めた条例を施行しました。続いて2023年10月には名古屋市も同様の条例を施行し、この動きは全国的な注目を集めました。
しかし、この二つの条例は、そのメッセージの伝え方によって、異なる結果を生んだことが分析されています。
埼玉の経験と名古屋の学習
埼玉県の当初のキャンペーンは「立ち止まろう」という呼びかけに重点を置いていました。その結果、多くの人が左側(関東ルール)で立ち止まるようにはなったものの、右側は依然として空いたままとなり、かえって歩きやすい環境が維持されてしまった側面がありました。
この経験から学んだ名古屋市は、より具体的で行動を直接促すメッセージを採用しました。それが「左右両側に立ち止まろう!!」というキャッチコピーです。これは、単に歩行を禁止するだけでなく、「両側に立つ」という代替行動を明確に提示するものでした。
物理的に両側が塞がれれば、歩きたくても歩けません。この行動経済学で言うところの「ナッジ(nudge、そっと後押しする)」的なアプローチは、埼玉の事例よりも効果的に人々の行動を変容させたと評価されています。
この二つの都市の経験は、社会規範を変えるためには、単なる禁止(Don't)ではなく、望ましい行動の提案(Do)がいかに重要かを示す、貴重な教訓となっています。
「当たり前」を解体する難しさ
それでもなお、「片側空け」の慣習は根強く残っています。その理由は、この慣習が「共有知識」の強固な城壁に守られているからです。
新しい「両側立ち」ルールが定着するためには、自分一人がそれを実行するだけでは不十分です。「周りの誰もが、これからは両側に立つだろう」と、全ての人が相互に確信できる状況が生まれなければなりません。
そのためには、名古屋市のアプローチのような強力な介入や、大多数の人々が一度に新しい行動を経験するような社会的イベントが必要となります。
この長く続く移行期間は、社会のルールがいかにして作られるかについての重要な示唆を与えてくれます。それは、公式なトップダウンのルール(法律や条例)と、非公式なボトムアップのルール(慣習やマナー)との間の、絶え間ない綱引きのプロセスなのです。
エスカレーターの上で繰り広げられる日々の小さな攻防は、まさにその縮図なのです。
おわりに〜エスカレーターは社会を映す鏡〜
エスカレーターの片側をなぜ空けるのか――。この素朴な疑問から始まった私たちの旅は、いつしか時空を超え、文化や心理の深層を探る壮大な探求となっていました。
もはやエスカレーターは、単に人を運ぶ機械ではありません。それは、私たちの社会そのものを映し出す、不思議な鏡なのです。
複雑なタペストリーが織りなす社会
この鏡を覗き込むと、様々なものが見えてきます。私たちはそこに、ロンドンの地下鉄で生まれた、今や忘れ去られた過去との繋がりを見ます。私たちはそこに、見知らぬ他人同士が、衝突を避け、円滑な社会を築こうとする、秩序への無意識の渇望を見ます。
私たちはそこに、武士の時代の記憶と、万博が象徴する国際化への憧れという、日本の文化的な価値観の変遷を見ます。そして私たちはそこに、個人の「急ぎたい」という自由と、誰もが安全に移動できる社会という全体の幸福がせめぎ合う、現代的なジレンマを見ます。
正解のない問いが示すもの
片側を空けるべきか、両側に立つべきか。この議論に、唯一絶対の正解はないのかもしれません。むしろ重要なのは、この「当たり前」をめぐる議論が、今まさに私たちの社会で活発に行われているという事実そのものです。
それは、私たちの社会が、より効率的で、より安全で、そしてより公平なあり方を模索し、進化し続けている健康な証拠と言えるでしょう。
見えざる糸で結ばれた社会契約
次にあなたがエスカレーターに乗るとき、少しだけ周りを見渡してみてください。そこにあるのは、単なる人々の流れではありません。歴史と、文化と、心理が織りなす複雑なタペストリーであり、見えざる糸によって私たちを結びつけている、社会という名の不思議な契約の姿です。
そう思えば、雑踏に満ちた駅の風景も、少しだけ面白く、そしてそこにいる名もなき人々の営みが、少しだけ愛おしく感じられるのではないでしょうか。
【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】
PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?
参考
- 「歩かないで、両側に立つべき」が多数派なのに…「エスカレーターの片側空け」が終わらない根本原因【2023編集部セレクション】 そもそもは関西の鉄道会社がマナーとして推奨した - プレジデントオンライン
- エスカレーターのルール(関東、関西)|wagayaジャーナル
- エスカレーターの“立ち位置”問題 東京は左、大阪は右……でも関西圏なのに「京都」はなぜ左? その理由とは | VAGUE(ヴァーグ)
- 説明できたらすごい! 東京と大阪で立つ位置が違うのはなぜ?<エスカレーター立ち位置 - Oggi
- エスカレーター片側空けという異文化と日本人のアイデンティテ - 江戸川大学
- 「エスカレーター片側空け文化論」~新文化の行方は?~ | お役立ち情報
- エスカレーターはどっち側に立ちますか?|かじしょー - note
- エスカレーターで人は左右どちらに立つか? - 大阪教育大学リポジトリ
- 日本人の行動パターン(1)「すれ違い時の行動」と 「エスカレーターに乗る際の立ち位置」 - CORE
- エスカレーターで立つのは右? 左? 切り替わる境界線はどこ?
- 「盲導犬を蹴られる」エスカレーター片側空け問題、条例施行でどうなった? | サストモ - 知る
- 第265回 ロンドンのエスカレーターは右立ち左歩行 - - 英国ニュースダイジェスト
- エスカレーター「片側空け」奨励する国もある 日本では「歩行は危険」と禁止の方向だが… | 海外
- 世界のエスカレーター事情【イギリス・中国(北京)】 – J-WAVE 81.3 FM JK RADIO TOKYO UNITED
- エスカレーター片側空けという異文化と 日本人のアイデンティティ
- 駅のエスカレーター「両側立ち」は本当に最善か? 「元祖・片側立ち」の街が得た“結論”とは カギは自由と寛容
- エスカレーターの「左立ち」から「両立ち」へ:新しい「慣習」の形成を考える|神奈川大学
- エスカレーターの乗り方|Hercelot - note
- 集団による同調的な行動 - 名古屋学芸大学 管理栄養学部
- 同調圧力の具体例とは?日本・海外の事情や生産性との関係を解説 - ミイダス
- 「エスカレーター片側空け」における多元的無知の検証
- エスカレーターで片側をあけて乗る行為は危険なのになぜ無くならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う②- | オージス総研
- エスカレーター 「両側立ち」の名古屋ルールが世界標準に - NEWSポストセブン
- エスカレーターの豆知識 - 日立ビルシステム
- エスカレーター片側空けの歴史を踏まえた提案 - 反社会学講座
- エスカレーターは歩かないで - MASコミュニティ - 構造計画研究所
- エスカレーター内の歩行に関する基礎研究 Basic study on the walk in the escalator - 岩手県立大学
- 効果ある?「片側空け」防ぐエスカレーターの性能 どんな仕組みなのか、日立が明かす開発秘話
- エスカレーターの安全利用について - 埼玉県
- エスカレーターの片側を歩く人はブロックしていい…医師が「片側空けはマナーではなく因習」と断ずる理由 そもそも健常者が速く上がるための装置ではない - プレジデントオンライン
- エスカレーター「歩かず立ち止まろう」キャンペーンの実施について - 茨城県
- 「後ろの視線が気になって…」エスカレーターの“片側空けと歩行”をめぐる各地の規制条例に差