「エグい」の意味が変化した理由とは? 褒め言葉になった若者言葉の語源を徹底解説
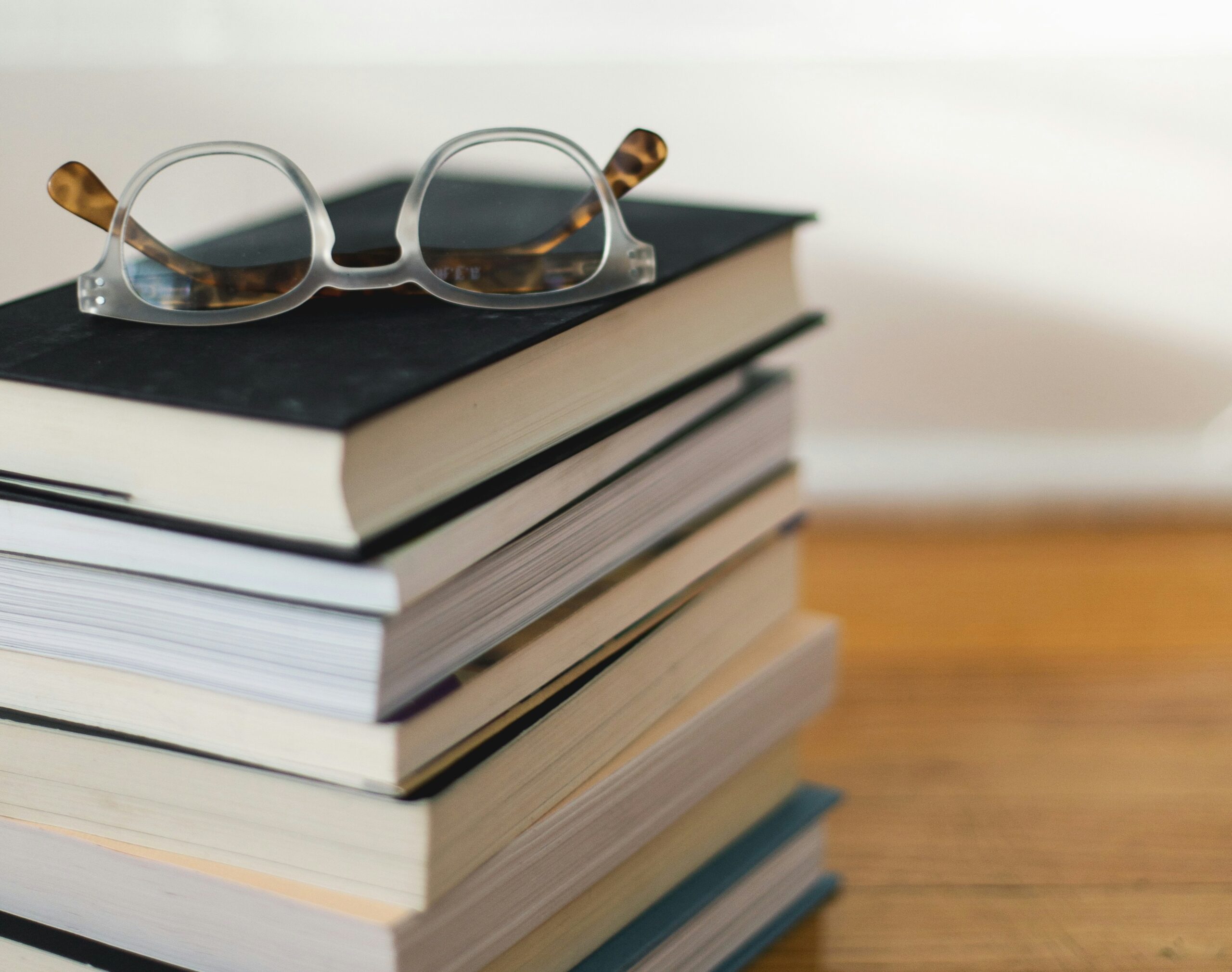
サッカーの国際試合。一人の選手が、まるでダンスを踊るようにディフェンダーたちをかわして、ゴールに迫ります。その瞬間、解説席から聞こえてきたのは、元日本代表・本田圭佑さんのこんな一言でした。
「今の突破の仕方はエグい」
え、エグい?あの「エグい」が褒め言葉?
「エグい」って、本来は気持ち悪いとか、むごいとか、そういう意味のはずですよね。それがなぜ、神業のようなプレーを褒める最高の言葉になっているんでしょう。
「最近の若者の言葉は分からない」。そう片付けてしまうのは簡単です。でも、ちょっと待ってください。この心地よい違和感こそが、面白い冒険への入り口なんです。
言葉の意味が、コインの裏表がひっくり返るように変わる。この現象は、ただの「言葉の乱れ」じゃありません。そこには、人間の心理や社会の変化、そして言葉そのものが持つ、ダイナミックなメカニズムが隠されているんです。
山菜の「えぐみ」から、人の心の「えぐさ」へ

今では最高の褒め言葉になった「エグい」。でも、そのルーツは、私たちの五感に直接訴えかける、すごく原始的な感覚にありました。
その原点は、山菜が持つ「えぐみ」です。
ワラビやタケノコをそのまま口にすると、舌や喉の奥に広がる、いがらっぽくて不快な刺激。あれが「えぐみ」の正体です。
言葉の成り立ちを見ると、もっとはっきりします。「えぐい」の語源は、ものを「えぐる(刳る)」という動詞。喉をえぐられるような強烈な不快感、それが「えぐい」という言葉の原体験だったんです。漢字で「蘞い」や「刳い」と書くことからも、その身体的なインパクトの強さが伝わってきますよね。
この言葉、実は新しくありません。平安時代の辞書『和名類聚抄』にも、すでに記述があるんです。それほど昔から、この不快な味覚は日本人の食生活に根付いた感覚でした。
そして、言葉の進化でよくあるパターンなんですが、この具体的な「身体の感覚」は、やがて抽象的な「心の感覚」へと広がっていきます。
舌や喉にとって不快な味が、人の心にとって不快な言動を表す言葉になったんです。
江戸時代には、「思いやりがない」「あくが強い」といった、人の性格を指す使い方がすでに確立していました。作家の鈴木三重吉の作品には、「では何か…、えぐい事でもお言いなしたのですかい?」という一節が出てきます。ここでの「えぐい」は、明らかに相手の心を傷つけるような、冷たい言葉を指しています。
この流れは現代まで続きました。ポジティブな意味で使われるようになる直前まで、「エグい」は主にネガティブな文脈で使われていたんです。
「えぐい描写」と言えば、目を背けたくなるような残酷なシーン。「来週のシフトがエグい」と言えば、超過酷な勤務状況。
このように、「エグい」は具体的な身体感覚(味覚)から、それを比喩として使った抽象的な精神作用(残酷さ、ひどさ)へと広がってきました。口の中の不快感が、心の不快感へ。このメタファーによる意味の広がりこそが、言葉が豊かになっていく基本的なプロセスの一つなんです。
このしっかりとした「負」の土台があったからこそ、後のポジティブな意味への大ジャンプが可能になったと言えるでしょう。
「ヤバい」という先輩〜意味が反転する言葉のお手本〜
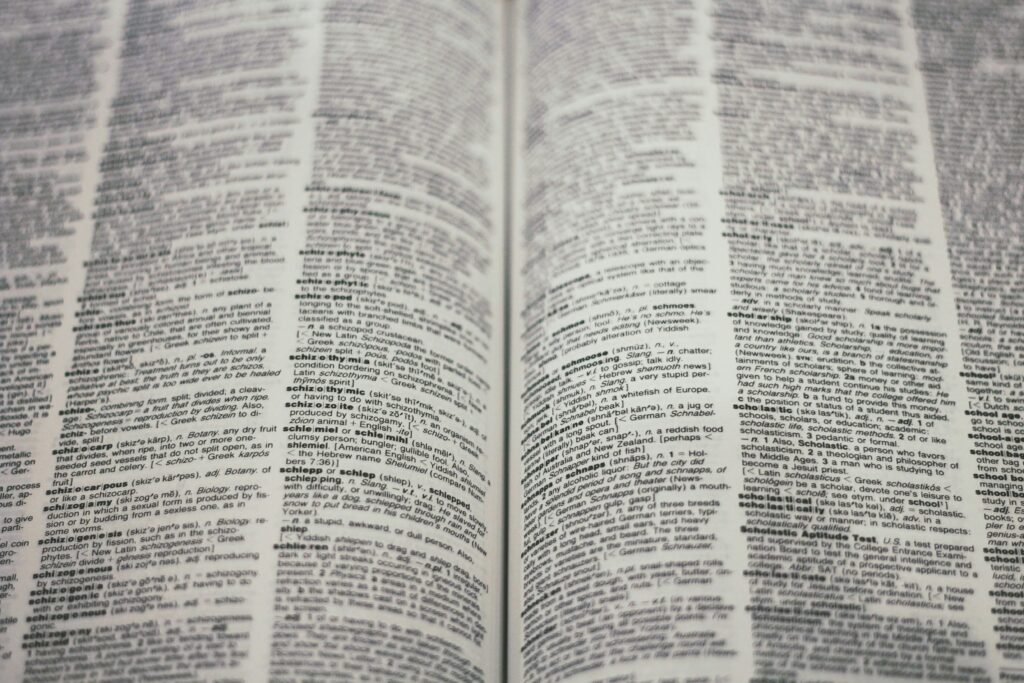
「エグい」が褒め言葉になるという現象。実は、日本語のスラング史で突然変異じゃありません。もっと身近な「先輩」が、その変化の道筋をすでに示していました。
その言葉とは、「ヤバい」です。
今や「ヤバい」は、「めちゃくちゃ美味しい」から「超まずい」、「最高にかっこいい」から「絶望的に危険」まで、文脈次第でプラスとマイナスの両極端な意味を表現できる万能な言葉として定着しています。
でも、この言葉の出自も、「エグい」に負けず劣らず、日陰の道を歩んできたんです。
「ヤバい」の語源は、江戸時代の犯罪者たちが使っていた隠語にさかのぼると言われています。有力な説が二つあります。
一つは、牢屋の看守を意味する「厄場(やば)」に由来するという説。捕まりそうになった盗人たちが、「厄場の世話になる=危ない」という意味で「やばい」を使い始めたというもの。
もう一つは、非合法な賭博の温床になることもあった弓の射的場「矢場(やば)」に近づく危険性を指したという説です。
どちらにしても、その出発点は「危険が迫っている」「法に触れるようなまずい状況」という、完全にネガティブな意味でした。
このアンダーグラウンドな言葉が、大きく運命を変えるのは20世紀も終わりに近づいた頃です。
1980年代後半の辞書には、まだ「危ない」といった否定的な意味しか載っていませんでした。でも、1970年代から音楽業界などのサブカルチャーで使われ始め、1990年代に入ると若者たちの間で「すごい」「素晴らしい」といった肯定的な意味で爆発的に広まります。
そして2006年、ついに大手国語辞典『大辞林』が、従来のネガティブな意味に加えて、「すごい。自身の心情が、ひどく揺さぶられている様子」という新しい意味を追加。その意味の反転が公に認められたんです。
この「ヤバい」が歩んだ道のりは、「エグい」の未来を予言していたかのようです。
共通するパターンは以下の通りです。
- 元々は、はっきりネガティブな意味を持つ言葉だった
- 若者やサブカルチャーの中から、正反対のポジティブな意味で使われ始めた
- だんだん一般化して、文脈によってプラスにもマイナスにもなる「すごく強い」を表す言葉へと変化した
この二つの言葉は、単に似た変化をしただけじゃありません。そこには、スラングが持つ「ライフサイクル」と、若者文化が常に求める「新鮮さ」という、もっと深い関係性があるんです。
「ヤバい」はあまりにも広く、長く使われすぎました。その結果、本来持っていた「危険」な香りが薄れて、誰もが使う便利な言葉へと「陳腐化」してしまったんです。
言語学者の新野直哉さんが指摘するように、使い古された言葉はインパクトを失います。若者文化は、常に新鮮で、より強い刺激を持つ表現を求めます。
そこに現れたのが「エグい」でした。
「ヤバい」の汎用的な「すごさ」では物足りなくなった世代が、より強烈で、身体感覚に訴えかけるようなインパクトを持つ「エグい」を、新たな最上級の表現として見つけ出し、採用したんです。
つまり、「エグい」は「ヤバい」の後継者。スラングの流行と衰退という、終わることのないサイクルの産物なんです。
この構造を理解すると、一見バラバラに見える言葉の変化が、実は一定の法則性を持って繰り返されていることが見えてきます。
変化の法則〜言語学が解き明かす「意味の昇進」〜
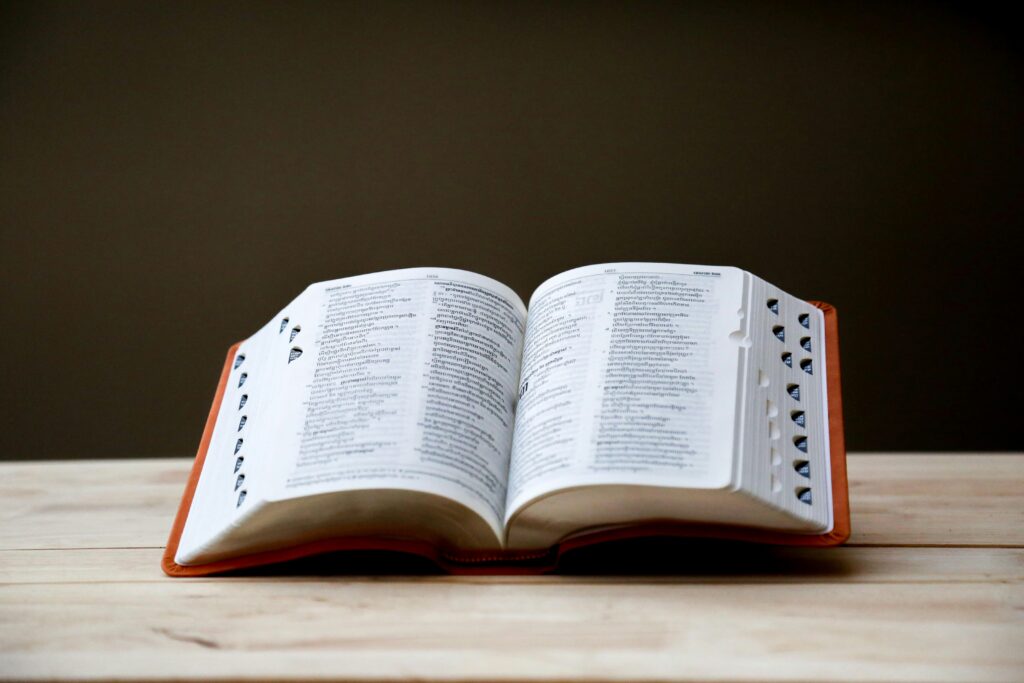
「エグい」や「ヤバい」に見られる劇的な意味の変化。言語学の世界では、これを「意味変化(semantic change)」と呼んで、ごく自然で普遍的な現象として研究しています。
言語学者は、言葉の変化を「乱れ」や「衰退」とは考えません。むしろ、社会や文化のニーズに応じて言葉が自分を適応させていく、生命力あふれる証拠だと見るんです。
この意味変化の中でも、「エグい」のケースはとくに面白いパターンを示しています。専門的には「意味の向上(amelioration)」と呼ばれます。
これは、元々ネガティブだった言葉や、中立的だった言葉の意味が、時代と共にポジティブな方向へと格上げされる現象を指します。まさに、言葉の「昇進」ですね。
この現象をもっと深く理解するために、その反対のプロセスも見てみましょう。それは「意味の堕落(pejoration)」と呼ばれ、かつては良い意味や中立的な意味だった言葉が、ネガティブな意味を帯びるようになる現象です。
例えば、英語の "silly" は、かつて「祝福された」「幸せな」という意味でした。でも時を経て「愚かな」という今の意味に変化しました。また、"mistress" は元々「家庭を切り盛りする女性、女主人」という敬意のこもった言葉でしたが、今では主に「愛人」というネガティブな文脈で使われます。
では、なぜ「エグい」のようなネガティブな言葉が、正反対のポジティブな意味へと「昇進」するんでしょうか。
そのメカニズムの鍵を握るのが、「誇張(hyperbole)」や「皮肉(irony)」といった表現方法です。
想像してみてください。規格外に美味しい料理を食べた人が、その衝撃を表現するために「うますぎて、もはやエグい」と言ったとします。
これは、「常識を超えたレベルの美味しさ」を、あえてネガティブな極端さを表す言葉で表現する、一種の誇張表現です。あまりの素晴らしさに、感覚が麻痺して、一種の不快感すら覚えるほどの衝撃。そんなニュアンスが込められています。
このような使い方が繰り返されるうちに、「うますぎて」の部分が省略されて、「この料理、エグい」だけでも「最高に美味しい」という意味が通じるようになります。
言葉が本来持っていたネガティブな意味は文脈の中で薄れて、代わりに「常識を超えた、規格外の」という「すごく強い」を強調する機能だけが前面に出てくるんです。
英語の "terrific"(素晴らしい)や "tremendous"(途方もない)も、元をたどれば "terror"(恐怖)や "tremble"(震える)といった、恐怖に関連する言葉でした。
これらもおそらく、「恐ろしいほど素晴らしい(terrifically good)」といった誇張表現として使われる段階を経て、やがて単体でポジティブな意味を持つようになったと考えられます。
つまり、「エグい」の意味の反転は、言葉を使う人たちが、既存の言葉では表現しきれないほどの強烈な感動や賞賛を伝えようと、言語的な工夫を凝らした結果なんです。
それは、言葉の破壊じゃなく、むしろ創造的な作り直しと言えるでしょう。
世界規模で見る「悪い」が「良い」を意味するとき
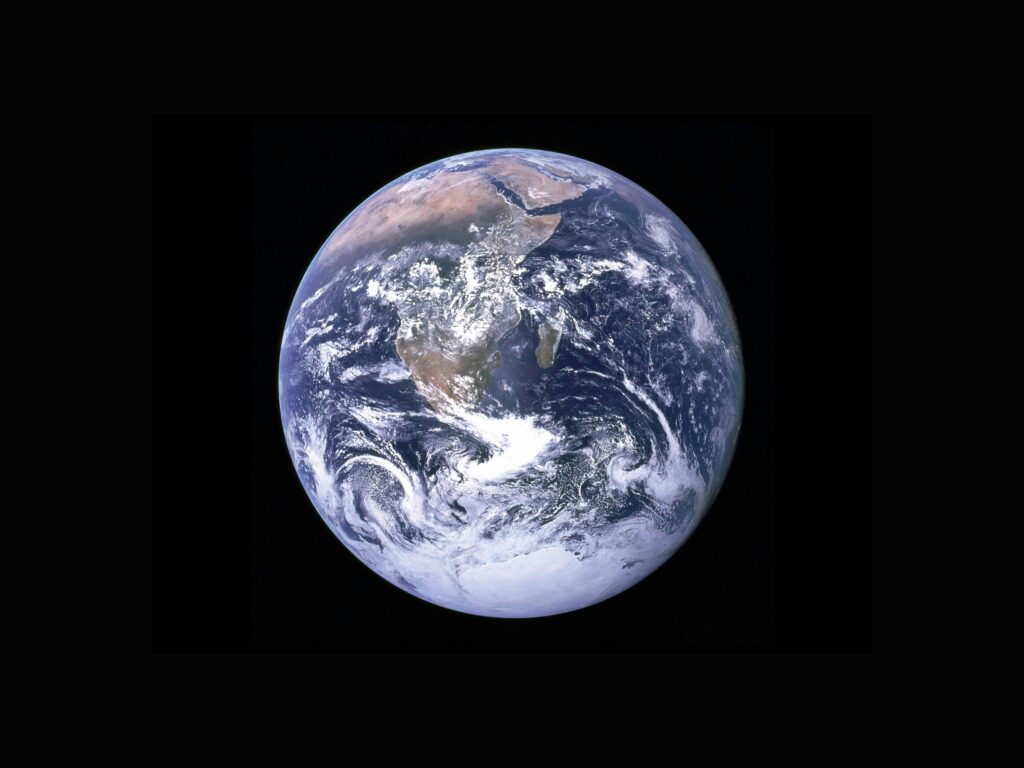
「エグい」や「ヤバい」のように、ネガティブな言葉がポジティブな意味に変わる現象。これ、決して日本語だけの特別なケースじゃありません。
海を越え、言語や文化が違っても、人類は驚くほど似た言葉遊びをしているんです。とくに、若者文化から生まれるスラングの世界では、この「意味の反転」は世界共通の現象と言っても過言じゃありません。
英語のスラングに目を向けると、そこには「エグい」の兄弟とも言える言葉たちが山ほど存在します。
- Sick(シック): 「病気の」「気分が悪い」という本来の意味から転じて、「最高にかっこいい」「信じられないほど素晴らしい」という意味で使われます。「あのスケボーの技、ヤバかったね!」を "That skateboard trick was sick!" と表現するのは、その典型です。
- Wicked(ウィキッド): 「邪悪な」「意地悪な」という意味を持つこの言葉は、とくにアメリカのニューイングランド地方などで、「とても良い」「素晴らしい」という強調語として使われます。
- Bad(バッド): 最も象徴的な例の一つが "bad" でしょう。「悪い」という基本的な意味とは正反対に、ジャズ文化やアフリカ系アメリカ人の話し言葉に由来して、「すごく良い」「かっこいい」「イケてる」という意味で使われてきました。マイケル・ジャクソンの名曲『Bad』のタイトルが、その好例です。
その他にも、「病気の」を意味する "ill"、「不快な」を意味する "nasty"、「正気でない」を意味する "insane"、「殺し屋」を意味する "killer" など、数え切れないほどあります。
これらの言葉はすべて、元々のネガティブな意味が持つ「普通じゃない」「常識を超えた」というニュアンスを利用して、ポジティブな意味での「規格外の素晴らしさ」を表現しているんです。
意味が反転した言葉の比較表
| 言語 | 言葉 | 元々のネガティブ/中立的な意味 | 現代のポジティブなスラングの意味 |
|---|---|---|---|
| 日本語 | エグい | 味が渋い、むごい、気味が悪い | 信じられないほど凄い、素晴らしい |
| 日本語 | ヤバい | 危ない、不都合だ、法に触れる | 最高、素晴らしい、強烈な |
| 英語 | Sick | 病気の、気分が悪い、病的な | 最高にかっこいい、素晴らしい |
| 英語 | Wicked | 邪悪な、道徳に反する | 素晴らしい、見事な |
| 英語 | Bad | 悪い、質の低い | とても良い、かっこいい、スタイリッシュな |
この表が示すのは、単なる偶然の一致じゃありません。それは、言語や文化は違えど、若者たちが自分たちのアイデンティティを形作る上で、共通の言語戦略を使っていることの証なんです。
英語の例を見ると、"sick" がスケーターやサーファー文化から、"bad" や "ill" がジャズやヒップホップ文化から生まれたように、これらの言葉の多くは特定のサブカルチャーを発生源としています。
社会言語学の研究によれば、若者スラングの重要な機能の一つは、仲間内だけで通じる「暗号」を作り出すことです。グループへの帰属意識を高め、大人や他の集団との間に境界線を引くんです。
誰もが知っている言葉の意味を意図的にひっくり返すことは、この目的を達成するための超効果的な手段。部外者が聞けば誤解するだろうこの言葉遣いは、内と外をはっきり区別して、仲間内の連帯感を強くするんです。
つまり、世界中で見られる「意味の反転」は、各地の若者たちが、それぞれの場所で「自分たちの言葉」を創り出そうとした結果、期せずして同じ答えにたどり着いた、文化的な収斂進化の美しい一例なんです。
「言語実験室」としての若者文化

ここまで「エグい」のルーツから世界的な広がりまでを見てきました。最後に、最も重要な問いに答えましょう。
それは、「なぜ、そして誰が」このような言葉の変化を牽引しているのか、という問いです。
その答えは、ここまで何度も触れてきた通り、「若者文化」という巨大なイノベーションのエンジンにあります。
若者にとって、言葉は単なるコミュニケーションの道具じゃありません。それは、自分のアイデンティティを形作り、仲間との絆を確かめ、社会における自分の立ち位置を表現するための、超重要なツールなんです。
大人たちが使う「正しい」言葉から少しだけズレた、自分たちだけの言葉を持つこと。それ自体が、自立と所属の証になるんです。
若者言葉が持つ機能について、研究者の米川明彦さん(2009)はいくつかの点を挙げていますが、とくに重要なのが以下の3つです。
- 娯楽機能: 会話をもっと楽しく、刺激的にするための機能です。仲間内で盛り上がる独特の「ノリ」を重視して、言葉遊びそのものを楽しみます。単に「すごい」と言うよりも、「エグい」と言った方が、よりドラマチックで遊び心があって、感情の振れ幅を大きく表現できますよね。
- 連帯機能: 同じ言葉を共有することで、「自分たちは仲間だ」という一体感を生み出します。特定の言葉を知っているかどうかが、そのコミュニティへの参加資格のようにも機能するんです。
- 言語経済: 複雑な感情や状況を、短くインパクトのある一言で表現する効率性です。「言葉では言い表せないほど、常識を超えていて、衝撃的で、素晴らしい」という感情の奔流を、「エグい」の一言に凝縮できるのは、コミュニケーションにおける大きな利点です。
そして現代では、この言語の実験と普及のスピードを、デジタルメディアが爆発的に加速させています。
かつては学校の教室や街角でゆっくりと広がっていた新しい言葉が、今や一人のYouTuber(例えば、「えぐいて」を広めた『チャンネルがーどまん』)の発言や、TikTokのショート動画、SNSのミームを通して、あっという間に全国、さらには世界へと拡散していきます。
若者文化は、かつてないほど巨大で高速な「言語実験室」と化しているんです。
ここで、もう一歩踏み込んで考えてみましょう。「すごい」から「ヤバい」へ、そして「エグい」へと、なぜより過激でインパクトの強い言葉が求められるんでしょうか。
それは、情報と刺激に満ち溢れた現代社会における、一種の「感情の軍拡競争」と見ることができます。
毎日、膨大な量のコンテンツに触れて、あらゆる「すごい」ものを見慣れてしまうと、ありふれた賞賛の言葉では、心が動かなくなってきます。本当に心を揺さぶられた時の「規格外の感動」を表現するためには、より強く、既存の言葉のスケールを振り切るような新しい表現が必要になるんです。
「ヤバい」がその役割を担っていました。でも、あまりの多用によってその価値がインフレを起こしました。
そこで登場したのが、味覚という身体感覚に根ざした、より根源的で強烈なインパクトを持つ「エグい」だったんです。
この言葉の変遷は、単なる流行り廃りじゃありません。それは、刺激に慣れてしまった現代人が、それでもなお本物の感動を誰かに伝えようと、必死に言葉を探して、磨き上げている営みの記録なんです。
おわりに
「エグい」という一言から始まった私たちの旅は、山菜の苦味から始まって、江戸時代の人間模様を垣間見て、言語学の法則を発見して、さらには世界中の若者たちの声に耳を澄ませてきました。
もう、私たちの目には「エグい」という言葉が以前と同じようには映らないはずです。
それは、単に意味が反転した変なスラングじゃなく、こんな多層的な物語を含んだ「生きた文化の結晶」として見えてきます。
- 人間の思考が、具体的な身体感覚から抽象的な概念へと飛躍する、壮大なメタファーの歴史
- 一つの言葉が流行して、陳腐化して、そして新しい言葉にその座を譲る、スラングの栄枯盛衰のサイクル
- ネガティブな言葉がポジティブな意味へと昇進する「意味の向上」という、言語の普遍的なメカニズム
- 若者たちが、アイデンティティを確立して、仲間との絆を深めるために繰り広げる、創造的な言語遊び
- そして、ありふれた言葉では表現しきれないほどの感動を、何とか伝えようとする人間の切実な願い
次にあなたが耳慣れない言葉や新しい使い方に出会った時、戸惑いや批判じゃなく、好奇心と共感を持ってその背景に思いを馳せることができるでしょう。
それは、「言語の変化」というリアルタイムで進行する文化の進化を、目の前で目撃する喜びに他なりません。
言葉は、決して静的なルールの集まりじゃありません。それは、私たち人間が社会を営んで、感情を交わして、文化を紡いでいく中で、絶えず形を変えて、呼吸し続ける生命体です。
その変化の一つ一つに、人間の営みの面白さ、滑稽さ、そして愛おしさが詰まっています。
言葉の変化を理解することは、世界の変化を理解すること。そして、その変化を面白がって、愛おしむことができたなら、私たちの日常は、ほんの少しだけ豊かで、彩り深いものになるんじゃないでしょうか。
【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】
PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?
参考
- プラスにも使われる「エグい」 - 毎日ことばplus
- 「ヤバい」と「エグい」 | 慶應丸の内シティキャンパス(慶應MCC)
- 若者の間で流行の「えぐいて」の意味とは?「えぐい」「えぐいてぇ」との違いは? 由来・例文・類語・最新若者言葉もご紹介! - Oggi
- 「えぐい」「やばい」「すごい」に見る言葉の"世代交代" 全部ほぼ同じ意味だが"発展段階"が異なる! - 東洋経済オンライン
- 21世紀の「ヤバい」はマジでヤバい|フォレスト出版 - note
- ヤバイの語源は江戸時代の射的場・牢屋!? - えいすう総研
- 語源がヤバい?「やばい」という日本語は江戸時代の犯罪者たちの隠語だった? - Japaaan
- 江戸時代から使われている「やばい」。その語源は牢屋? 射的場?/毎日雑学 | ダ・ヴィンチ
- 「やばい」は「すごい」?語源・由来は江戸時代から?|HALMEK up(ハルメクアップ)
- SNSで広がる新しい形容詞 :: 光村図書出版
- ヤバい - 飯間浩明 - 考える人
- SNS時代の言語変化と「言語の劣化」〜言葉のフォーマット化で、言語化力が衰える - note
- 流行語・新語の変遷における原因とその問題点
- ことばの源を探る ことばの獲得と新たな言語の誕生から
- 水野太貴「ことばの変化は『差異化』こそが原動力――社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」 - 中央公論.jp
- 語の意味変化と社会変化
- 「セクハラ」「妻さん」…新しいことばは社会に何をもたらすのか? 『ことばが変われば社会が変わる』より|じんぶん堂
- Term for when a negative word is used positively? - English Stack Exchange
- The semantic change of positive vs. negative adjectives in Modern English
- How do good words turn bad? - Cambridge University Press
- Origins of English: Amelioration and Pejoration - Daily Kos
- Words That Changed From Negative to Positive Meanings (or Vice Versa) - Mental Floss
- A Terrific Paper: A Corpus Study of Amelioration and Pejoration in Adjectives Related to Fear - DiVA portal
- Sick!" When Negative Words Have Positive Meanings | Engoo Blog
- Discover Negative Adjectives with Positive Meanings in English: A Unique Linguistic Twist
- When did sick become a positive term? : r/etymology - Reddit
- YOUTH SLANG AND IDENTITY: A SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE | International journal of artificial intelligence
- Semantic Study of the Impact of the Use of Slang on the Social Identity of Adolescents in Indonesia - Journal of Hunan University Natural Sciences
- Youth slang | Language and Popular Culture Class Notes - Fiveable
- ことばにみる日本とアメリカの大学生 - CORE
- 広告表現における若者言葉の有効性 - 駒澤大学
- 言語意識から見た若者ことば使用の要因 - CORE
- THE USE OF SLANG AMONG YOUNG PEOPLE AS A REFLECTION OF SOCIAL PROCESSES IN THE LANGUAGE - Web of Journals






