「チョコミント」は歯磨き粉の味?好き嫌いが真っ二つに分かれる理由を科学する

コンビニエンスストアのアイスクリーム売り場で、ふと目に留まる爽やかな緑色のパッケージ。そう、チョコミント味です。手に取ろうとした瞬間、隣にいた友人から「え、歯磨き粉の味のアイスなんて信じられない!」という声が聞こえてきた経験はありませんか?
一方で、チョコミント愛好家からは「あの絶妙なコントラストがたまらない」「夏の暑い日には最高のリフレッシュ」といった熱烈な支持の声も。この小さなフレーバーを巡って、なぜこれほどまでに人々の意見が真っ二つに分かれるのでしょうか。
実は、この現象の背景には、私たちの味覚と脳の仕組みに関する、とても興味深い科学的な理由が隠されているのです。
- 1. チョコミント論争の現状〜データで見る「好き嫌い」の実態〜
- 1.1. チョコミント好き嫌いの実際の割合は?
- 1.2. チョコミント派 vs 歯磨き粉派〜対立の構造〜
- 1.3. チョコミント市場の拡大〜数字で見る人気の実態〜
- 2. チョコミントの意外な歴史〜大人の味から若者の象徴へ〜
- 2.1. 世界でのチョコミントの歴史
- 2.2. 日本上陸とその後の変遷
- 2.3. 海外との文化的違い
- 3. 科学が解明する「好き嫌い」の謎
- 3.1. なぜ「歯磨き粉の味」と感じるのか?味覚記憶のメカニズム
- 3.2. なぜミントで好みが分かれるのか?メントールの科学的メカニズム
- 3.3. なぜチョコミントは緑色?色が与える心理的影響
- 3.4. 脳科学から見た「美味しさ」の本質
- 4. 苦手克服からQ&Aまで〜チョコミントとの付き合い方〜
- 4.1. チョコミント苦手な人でも食べられる?克服のヒント
- 4.1.1. 段階的なアプローチ
- 4.1.2. おすすめの商品選び
- 4.2. よくある疑問〜チョコミントQ&A〜
- 5. チョコミントだけじゃない!好き嫌いが分かれる食べ物たち
- 5.1. 遺伝的要因によるもの
- 5.2. 文化的要因によるもの
- 6. おわりに〜多様性への扉としてのチョコミント論争〜
- 6.1. 参考
チョコミント論争の現状〜データで見る「好き嫌い」の実態〜
まず、実際のところチョコミントの好き嫌いはどの程度分かれているのでしょうか。複数の調査結果や市場データから、その複雑な実態を見てみましょう。
チョコミント好き嫌いの実際の割合は?
マイナビニュースの調査(2017年)では、「どちらでもない」が46.7%で最多となり、「好き」(19.7%)と「嫌い」(17.4%)が拮抗。C-United株式会社の調査(2024年)では、食べたことがある人の約88%が「好き」と回答し、特に30代の支持率が93%と最も高い結果に。
地域別に見ると、東北地方が好き派の割合で全国1位、近畿地方が最も低いという調査結果もあります。
この差は調査対象や質問方法の違いによるものですが、「好き」と「嫌い」が明確に存在し、どちらでもない層も多いことがデータから伺えます。
チョコミント派 vs 歯磨き粉派〜対立の構造〜
- チョコミント愛好派の主張: 「ミントの爽快感と甘いチョコのバランスが好き」(67%)、「チョコのパリパリ感が好き」(48%)、「ミントグリーンの色が可愛い」(32%)
- 歯磨き粉派(批判派)の主張: 「歯磨き粉のような味がする」(最多)、「口の中がスースーするのが苦手」、「薬のような味で食べ物として認識できない」
チョコミント市場の拡大〜数字で見る人気の実態〜
日本のミントフレーバーチョコレートの市場は着実に拡大しており、2019年4~6月期は8億円を超え、前年同期比15%増、5年前の実に2.3倍強となっています(インテージ 食品SRIデータ)。
この成長の背景には、「チョコミン党」と呼ばれる熱心なファン層の存在と、SNSでの話題性、そして商品の多様化があります。
チョコミントの意外な歴史〜大人の味から若者の象徴へ〜
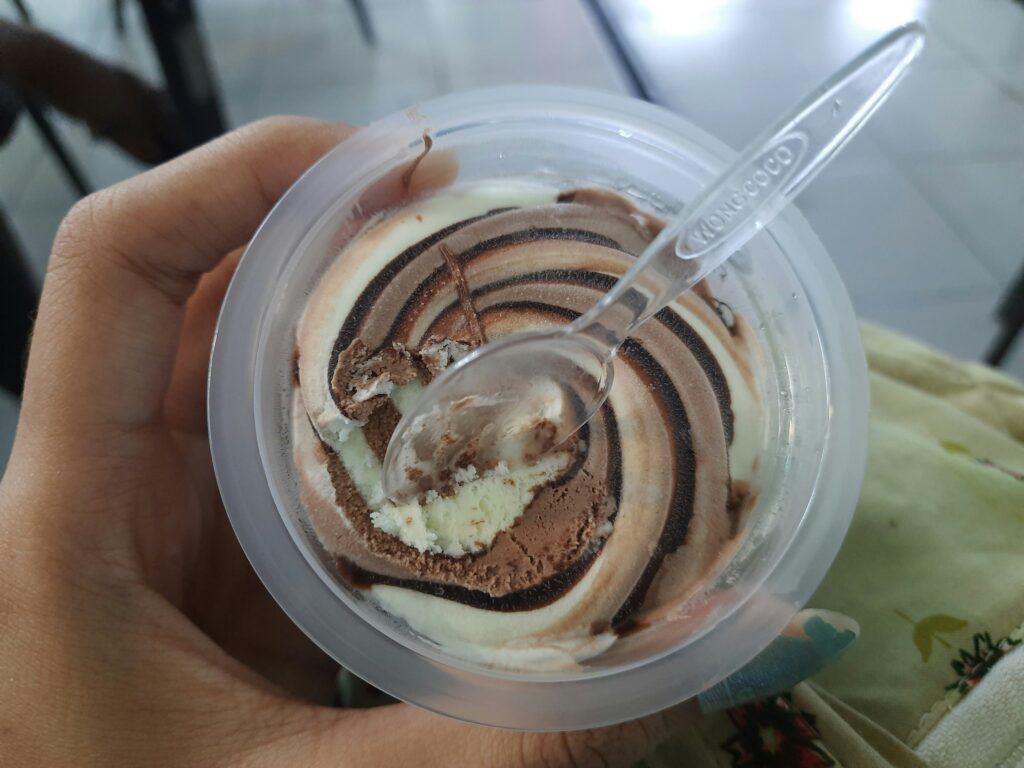
世界でのチョコミントの歴史
チョコレートとミントの組み合わせの歴史は意外に古く、1931年にイギリスのベンディックス社が販売したチョコレートが最初という説があります。しかし、チョコミント風味の「グラスホッパー」というカクテルは1900年から1920年代の間に誕生しており、アイスクリームよりも歴史が古いことが分かっています。
日本上陸とその後の変遷
現代のようなアイスクリームとしてのチョコミントが登場したのは、1945年にアメリカでサーティワンアイスクリームの前身であるバスキン・ロビンスがオープンした時からとされています。
日本への上陸は1974年4月23日、東京・目黒にサーティワンアイスクリーム1号店がオープンした時です。泉麻人氏の『おやつストーリー』によると、当時は「毒々しく見えたのか売れ行きは芳しくなかった」とされていますが、次第にその新鮮さが話題となり、人気商品となりました。
海外との文化的違い
興味深いのは、海外と日本でのチョコミントの位置づけの違いです。イギリスやヨーロッパでは、チョコミントは「大人のもの」で夏限定ではありません。一方、日本では若者を中心とした「チョコミン党」という独自の文化が生まれ、SNSでの連帯感やフォトジェニックな要素が人気を支えています。
科学が解明する「好き嫌い」の謎
なぜ同じものを口にしても、感じ方が全く異なるのでしょうか。その答えは、私たちの体と脳、そして記憶の仕組みに隠されています。
なぜ「歯磨き粉の味」と感じるのか?味覚記憶のメカニズム
大阪大学大学院歯学研究科の豊田博紀准教授の研究により、味覚嫌悪記憶の消去に関わる脳メカニズムが明らかになりました。多くの人が初めてミントの味を体験するのは歯磨き粉を通じてです。幼少期に形成されたこの記憶は、成人になってもミントを「清潔感」「口腔ケア」と強く結びつけて認識させます。
調査結果でも、全体の約42%が「小学生の時」にチョコミントを好きになったと回答しており、幼少期の体験がその後の好みを大きく左右することが分かります。
なぜミントで好みが分かれるのか?メントールの科学的メカニズム
ミントの主成分である「メントール」が引き起こす冷感の秘密は、「TRPM8」と呼ばれるイオンチャネルにあります。自然科学研究機構生理学研究所の研究によると、TRPM8は本来、冷たい温度で活性化しますが、メントールによっても活性化されます。このため、実際には温度が下がっていないにも関わらず、脳は「冷たい」という信号を受け取るのです。
また、マンダム株式会社の研究開発によると、メントールの量が増えるとTRPA1という別の受容体まで刺激し、痛みなどの不快刺激を感じてしまうことが分かっています。この閾値には個人差があり、これがチョコミントに対する感じ方の違いを生む要因の一つとなっています。
なぜチョコミントは緑色?色が与える心理的影響
多くの人が疑問に思うのが、なぜチョコミントが鮮やかな緑色をしているかということです。実は、ミントエキス自体は無色透明ですが、チョコミントアイスクリームはミント色で着色して清涼感を演出しています。日本では1974年のサーティワンアイスクリーム上陸時、「この青いアイスは何だ!?」と衝撃を受ける人も多く、当初は毒々しく見えて売れ行きが芳しくなかったという記録が残っています。
脳科学から見た「美味しさ」の本質
最新の脳科学研究では、食べ物の好き嫌いは単純な味覚の問題ではなく、記憶、感情、そして社会的な影響が複合的に作用した結果であることが明らかになっています。
医療法人松田脳神経外科クリニックの解説によると、「私たちが味と考えているものはかなりの部分が風味であり、嗅覚がもたらすもの」で、「味は味覚と違って、脳が複数の感覚(すなわち味覚・嗅覚・音)によって"つくられる"多感覚の構成概念」なのです。
苦手克服からQ&Aまで〜チョコミントとの付き合い方〜

科学的な背景を理解した上で、チョコミントとの上手な付き合い方を探ってみましょう。
チョコミント苦手な人でも食べられる?克服のヒント
段階的なアプローチ
オモコロブロスの実験では、「ピーチミント味」のキットカットを使った検証で、チョコミント苦手勢の4人中3人が「イケる!」と判断したという結果が報告されています。
おすすめの商品選び
- ミント控えめの商品を選ぶ:「チョコ強め、ミント弱め」の配合から始める
- 冷たい状態で食べる:常温よりも冷やした方がミントの刺激が和らぐ
- チョコが隠れているタイプ:キットカットのようにミントがチョコに包まれているもの
よくある疑問〜チョコミントQ&A〜
Q: チョコミントが苦手な人は味覚がおかしいの?
A: 全くそんなことはありません。TRPM8受容体の感受性や幼少期の味覚記憶には個人差があり、苦手なのは自然な反応です。
Q: 大人になれば好きになる?
A: 可能性はあります。20代の約47%が複数回食べて好きになったというデータもあり、味覚は変化することがあります。
Q: なぜ日本では夏限定なの?
A: アイスクリームから広まったことと、日本人の季節限定商品を好む傾向が影響しています。海外では年中販売されています。
Q: チョコミントの健康への影響は?
A: メントールには清涼感以外にも、鎮痛効果や消化促進効果があることが研究で示されています。
チョコミントだけじゃない!好き嫌いが分かれる食べ物たち
チョコミント以外でも、似たような現象は数多く存在します。
遺伝的要因によるもの
- パクチー(コリアンダー): 遺伝的要因により、石鹸のような味を感じる人が一定数存在
文化的要因によるもの
- ブルーチーズ: 「腐敗臭」と「熟成香」の境界線上で評価が分かれる
- 甘納豆: 豆の甘さに慣れ親しんだ文化圏とそうでない地域で受容度が大きく異なる
これらの例からも分かるように、私たちの「美味しさ」の感覚は、生理学的な要因と文化的な要因が複雑に絡み合って形成されているのです。
おわりに〜多様性への扉としてのチョコミント論争〜
チョコミントを巡る論争は、一見すると些細な食べ物の好みの問題に見えます。しかし、その背景を科学的に解き明かしていくと、そこには人間の感覚がいかに複雑で、個人の体験がいかに多様であるかという、深い真実が隠されていることが分かります。
「歯磨き粉の味」と感じる人も、「絶品スイーツ」と感じる人も、どちらも間違っているわけではありません。それぞれが、自分自身の生理的特性と人生経験を通じて構築した、固有の味覚世界を生きているのです。
TRPM8受容体の個人差、幼少期の味覚記憶、文化的背景、そして脳が複数の感覚を統合して作り上げる「美味しさ」の認識。これらすべてが組み合わさって、私たちそれぞれの「チョコミント観」が形成されているのです。
次回、コンビニでチョコミントを見かけたときには、そのパッケージの向こうに広がる、味覚の科学と文化の物語に思いを馳せてみてください。
幼き日の思い出から高級スイーツへ、ソフトクリーム偏愛者が語るその奥深さ
大衆的で高級品でもある、私たちにとって身近なスイーツの一つであるソフトクリーム。見た目や味、素材、製造方法など、知れば知るほど奥深いその魅力に迫る。
参考
- C-United株式会社「チョコミントに関する調査」プレスリリース
- マイナビニュース「チョコミントって好き? 「嫌いじゃないけど好きでもない」が46.7%で最多に」
- ちそう「チョコミント味はまずい?好き派・嫌い派の割合やそれぞれの言い分を徹底調査!」
- 自然科学研究機構 生理学研究所「マウスTRPVイオンチャネルにメントールが作用する構造の解明」
- 株式会社マンダム「五感とは違う感覚センサー TRP(トリップ)チャネル」研究開発情報
- 大阪大学ResOU「嫌いだった食べ物を好きになる脳の不思議」
- 医療法人松田脳神経外科クリニック「味覚の脳科学「おいしいと感じる仕組み」」
- 東洋経済オンライン「チョコミント「苦手な人」が多いのに人気の理由 実は世界の歴史的には大人受けする味だった」
- オモコロブロス「チョコミント好き嫌い論争を終わらせる嘘みたいなお菓子」






