「プロフィール帳」に何書いた?サイン帳文化と"手書きのSNS"の思い出

「好きな食べ物は?」「将来の夢は?」「私のことをひとことで表すと?」
学生時代、友達から手渡されたカラフルな小さな手帳を前に、ペンを持つ手が止まったことはありませんか?プロフィール帳やサイン帳と呼ばれるこの文化は、多くの人にとって青春の思い出の一部です。
しかし、よく考えてみると不思議な文化でもあります。なぜ私たちは、決められた項目に沿って自分のことを書き、相手のことを知ろうとするのでしょうか?そして、なぜこの小さな手帳は、デジタル時代の今でも特別な意味を持ち続けているのでしょうか?
手帳="手書きのSNS"? 2つの自己表現を比べてみる
プロフィール帳を現代の視点で見直すと、実は「手書きのSNS」とも呼べる存在であることが見えてきます。
現代のSNSプロフィールでは、アイコン写真や自己紹介文、投稿履歴などから相手を知ろうとします。一方、プロフィール帳では「好きな色」「嫌いなタイプ」といった定型項目を通じて相手を理解しようとします。
興味深いのは、両者ともに「自分をどう見せるか」という自己プロデュースの側面を持ちながら、そのアプローチが正反対だということです。SNSは無限の自由度がある代わりに、プロフィール帳は限られた枠組みの中での表現を求めます。この制約があるからこそ、「好きな動物」という項目ひとつにも、書き手の人柄や価値観が凝縮して現れるのです。
なぜ日本でサイン帳文化が根付いたのか?
プロフィール帳・サイン帳文化のルーツを辿ると、興味深い背景が見えてきます。
この文化は1970年代から1980年代の「交換日記」や「サイン帳」に起源を持ちます。当初はシンプルな情報交換ツールでしたが、1990年代から2000年代にかけて、よりカラフルでデザイン性の高いものに進化し、小学生や中学生の間で大ブームとなりました。
日本でこの文化が特に定着した背景には、集団重視の学校文化があります。クラス替えや卒業という「別れ」の瞬間に、お互いを知り、つながりを保とうとする強い願いが、プロフィール帳という形で結実したのです。SNSもない時代だったので、連絡先を残すうえでもとても重宝された実用的な側面もありました。
あの項目には深い意味があった?プロフィール帳の不思議な質問たち
「好きな色」「嫌いなタイプ」「将来の夢」——プロフィール帳の項目を改めて眺めてみると、実に巧妙に設計されていることがわかります。
これらの質問は、心理学でいう「パーソナリティの多面的把握」を実現する構造になっています。表面的な好み(好きな食べ物、色)から始まり、価値観(座右の銘、尊敬する人)、そして内面の深い部分(コンプレックス、恋愛観)まで、段階的に相手を理解できるよう配置されているのです。
特に興味深いのは「私のことをひとことで表すと?」という項目です。これは実際には、書き手ではなく書いてもらう相手に自分がどう映っているかを知る、いわば「他者からの視点」を収集する仕組みです。現代のSNSが「いいね」の数で承認欲求を満たすとすれば、プロフィール帳は友達からの直接的な言葉で自己肯定感を育んでいたのです。
あの独特な項目はこうして生まれた
プロフィール帳でおなじみの「血液型」欄は、実は日本独特の文化です。1970年代に血液型占いがブームになった影響で定着し、「性格を知る手がかり」として重視されるようになりました。
また、「今とっても欲しいナイスなものといえば?」のような独特な表現は、当時の若者文化やファッション雑誌の影響を受けています。「ナイス」という形容詞は1990年代の流行語で、プロフィール帳にもその時代の言葉遣いが色濃く反映されているのです。
さらに興味深いのは、時代とともに項目内容が変化していることです。昔は「好きな人のイニシャル」や「告白したことがあるか」程度だった恋愛関連の質問が、現在では「つきあったことがあるか」「キスをしたことがあるか」といったより踏み込んだ内容になっているそうです。
何を書けばいい?懐かし項目で振り返る「あの頃の私」
プロフィール帳を前にして、誰もが一度は「何を書こう?」とペンを止めた経験があるのではないでしょうか。ここでは、懐かしい定番の項目をいくつかピックアップし、「あの頃の私」を思い出す旅にご案内します。
- 「将来の夢」の欄:ケーキ屋さん、漫画家、サッカー選手…あの頃、純粋な気持ちで書いた夢を思い出してみませんか?今見返すと微笑ましいその夢に、今の自分に繋がる「好き」の原点が見つかるかもしれません。
- 「好きな人のイニシャル」の欄:最も書くのに緊張したこの項目。正直に書きましたか?それとも、友達の名前でカモフラージュしたり、あえて誰も知らないようなキャラクターのイニシャルを書いたりしませんでしたか?小さな工夫に、あの頃の甘酸っぱい記憶が蘇ります。
- 「好きな言葉」の欄:当時流行っていたJ-POPの歌詞や、漫画の名セリフを書いた人も多いはず。Mr.Childrenの壮大な歌詞、SPEEDのちょっと背伸びしたフレーズ、あるいは『スラムダンク』の名言。あなたの青春の「アンセム」は何でしたか?
世界にもあった「手書きの自己紹介文化」
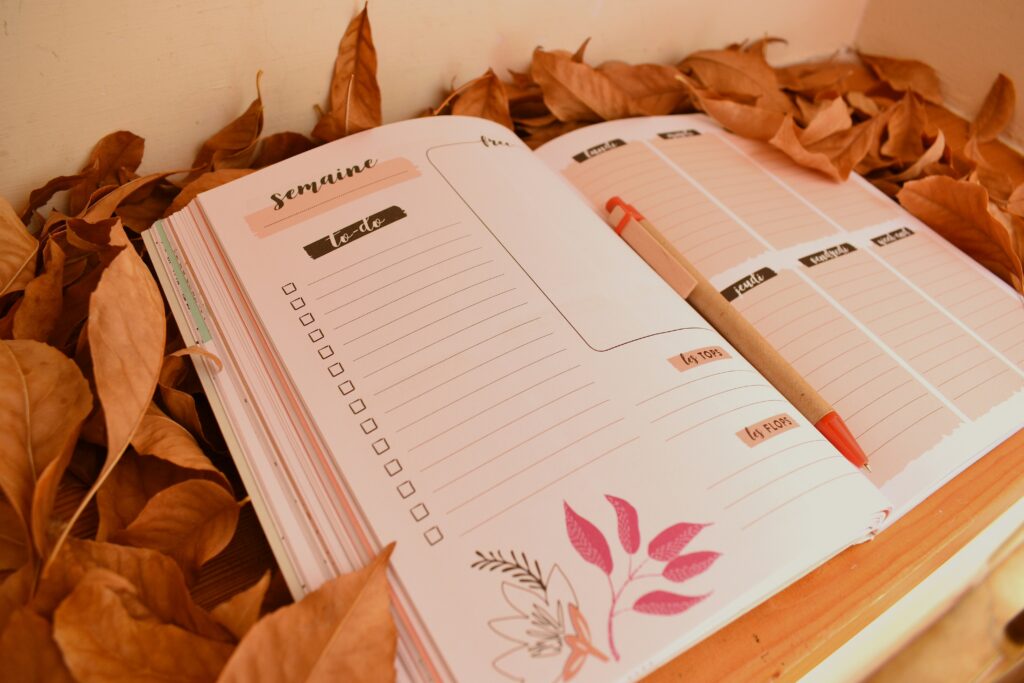
プロフィール帳のような文化は、実は日本だけのものではありません。アメリカの学校には「Yearbook」という卒業アルバムがあり、そこに友達からのメッセージを書いてもらう文化があります。ヨーロッパでは「Friendship Book」と呼ばれる友情を記録する小さな冊子が存在します。
ただし、これらと日本のプロフィール帳が決定的に異なるのは、「定型項目への回答」という構造です。欧米の文化がフリーフォーマットのメッセージ中心なのに対し、日本のプロフィール帳は「型にはまった自己表現」を特徴としています。
デジタル時代に見直される「手書きの価値」
2020年からのコロナ禍において、プロフィール帳が再流行したという興味深い現象がありました。感染対策のため学校生活で思うようにコミュニケーションが取れなかった生徒たちの間で人気を博したのです。
デジタル疲れが叫ばれる現代において、手書きのプロフィール帳は「スローコミュニケーション」の価値を体現しています。SNSのように瞬時に「いいね」で反応するのではなく、一文字一文字丁寧に相手のことを考えながら書く時間。その時間こそが、深いコミュニケーションを生み出していたのです。
「推し活」で進化するプロフィール帳の新しいかたち
コロナ禍をきっかけに再注目されたプロフィール帳ですが、その文化は今、最も熱いカルチャーである「推し活」の世界で、形を変えてさらに進化を遂げています。そこには、デジタルとアナログが融合した新しいコミュニケーションの形がありました。
- SNS用の「推しプロフ」:自分の「推し」への愛を語るためのプロフィール帳テンプレートが、SNS上で数多く配布されています。「推し始めたきっかけ」「推しの好きなところ3つ」「好きなコンビ」といった項目を埋めて画像として投稿し、同じファンとの交流を深めます。
- イベントでの名刺代わり:作成した「推しプロフ」をカードサイズで印刷し、ライブやファンイベントの会場で他のファンと交換する「名刺」のような使い方が広まっています。手書きの一言を添えることで、デジタルな繋がりだけでなく、リアルな交流のきっかけにもなっています。
小さな手帳に込められた、大きな人間関係の知恵
プロフィール帳という文化を振り返ると、そこには現代のコミュニケーションが失いかけている大切なものが詰まっています。
制約があるからこそ生まれる創意工夫。手書きだからこそ伝わる温かさ。そして、相手のことを知りたいという純粋な好奇心——これらはSNS時代の今でも、いえ、今だからこそ価値のあるコミュニケーションの原点なのかもしれません。
あの小さな手帳は、実は人と人とのつながりを大切にする知恵の結晶だったのです。デジタルな今だからこそ、その価値がより鮮明に見えてくるのではないでしょうか。
【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】
PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?






