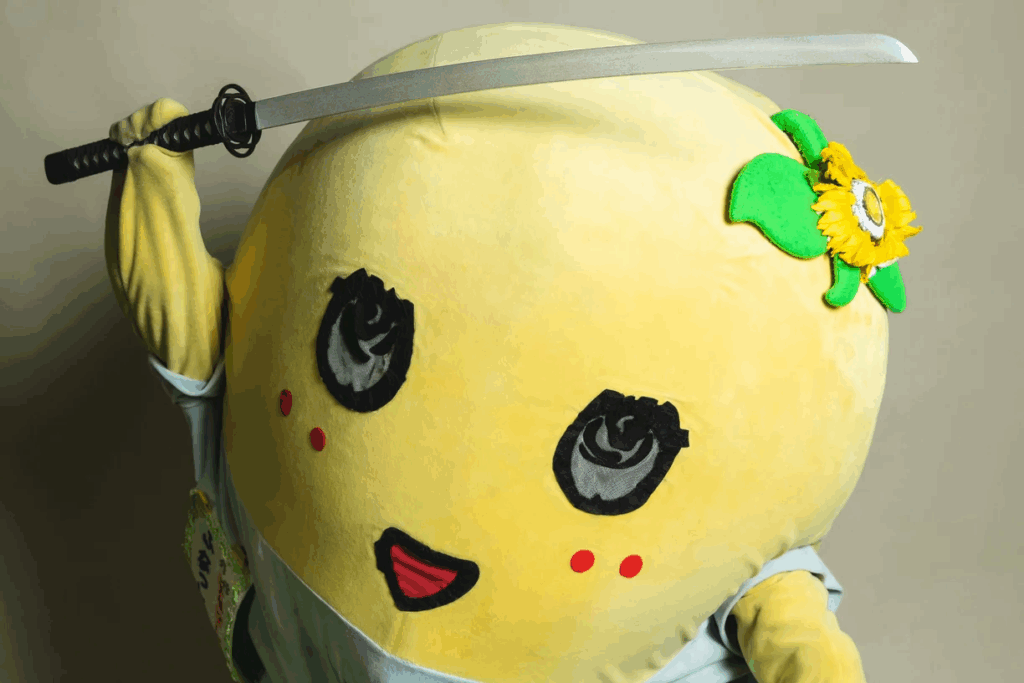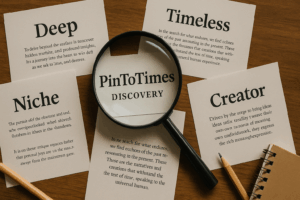消されたものたちの記憶—日本刀と暗渠が教える「失われた世界」

ある日、ふなっしーの日本刀への情熱と、暗渠マニアックスの髙山英男氏の暗渠への愛を続けて読んでいたとき、編集部内で小さな衝撃が走りました。
梨の妖精と暗渠マニア。日本刀と地下水路。どう考えても接点がなさそうなこの組み合わせに、驚くほど深い共通点があることに気づいてしまったのです。
それは単なる「継続性」や「独自の美学」といった表面的な類似ではありません。もっと根源的な何か。二人が愛しているのは、実は同じ種類の「何か」なのではないか…そんな仮説が浮かび上がってきました。
二人が共有しているもの。それは「消されたもの」「隠されたもの」「失われたもの」への、切ないまでの愛情です。
暗渠の魅力伝道 vol.1 ~暗渠のどこが好きなのか。暗渠とは?~
暗渠に関するさまざまな情報を発信し続ける、髙山英男・吉村生によるユニット「暗渠マニアックス」による連載企画。第一回は髙山英男が語る「暗渠とは?」。
歴史に消された記憶
ふなっしーの語りの中で、私たちが最も心を動かされたのは、GHQによる刀狩りのエピソードでした。
「第二次世界大戦後にGHQが『日本の家、どこに行っても刀があるぞ! これやべぇんじゃねぇか?』ってことで、非武装化のために刀を押収したんですよ。何百万本という刀が折られて海に投棄されたり、アメリカ兵がお土産変わりに国へ持って帰っちゃったり。国宝級の刀でも同じ扱いだったと知ったときは、びっくりしたなっしよ」
髙山氏もまた、失われた川について語ります。「多くの開渠は都市の近代化とともに暗渠になった。東京で言えば、昭和の高度経済成長期以降に暗渠化された所がとても多い」。そして、暗渠を眺めるとき「開渠だった頃はどんなだったのだろう、なぜ暗渠にされてしまったのだろうという疑問が浮かんでくる」と。
二人が愛するものは、いずれも社会の大きな力によって「消された」ものです。戦後の非武装化政策によって失われた刀。都市開発によって地下に埋められた川。どちらも、かつては日常に当たり前のように存在していたのに、ある時期を境に、多くの人の視界から消えてしまった。
偏愛研究の文脈では、対象への愛着や継続性が語られることが多いのですが、二人のケースで際立つのは「失われたものを取り戻そうとする」という、より能動的で、ある種の使命感にも似た姿勢です。
ふなっしーは「そんな時代背景から、刀の存在自体が忘れられていた時代もあったんです。それから月日が経って、再び注目されるようになったのは嬉しいなっしな」と語ります。髙山氏は暗渠を辿ることで「過去の川の姿や川と人との関わりが目の前(あるいは脳内)に広がる、小さなタイムトリップ」を体験していると言います。
二人は、消された記憶を蘇らせようとしているのです。
真贋を超えた先にあるもの
ふなっしーの日本刀偏愛において、最も象徴的なエピソードがあります。
最初に52万円で購入した「村正」。YouTubeで妖刀村正の動画を見て、勢いでヤフオクで購入したその刀は、鑑定の結果、村正ではなく「別の刀匠の作」だったのです。
普通なら、これは失望する出来事でしょう。52万円も払って買った刀が偽物だった——そう考えることもできます。
しかし、ふなっしーはこの結果をどう受け止めたのか。記事からは、失望や後悔の言葉は一切出てきません。それどころか「52万もしたんだからこの刀について徹底的に調べてやろうと思って」と、さらに深く刀の世界に入り込んでいくのです。
ここには、偏愛者の持つ独特の認識の在り方が表れているように思います。
「本物か偽物か」という二項対立は、実は偏愛者にとってそれほど重要ではないのかもしれません。重要なのは、その対象と向き合う中で自分が何を感じ、何を学び、どう変化していくかです。
村正という「名前」が欲しかったわけではない。その刀を通して、刀という文化、日本の歴史、職人の技術、そして時間の流れそのものと対話したかった。だから、鑑定結果がどうであれ、その刀は価値を失わないのです。
髙山氏の暗渠愛にも、似た構造があります。
暗渠を辿るとき、すべての経路が完全に判明するわけではありません。「たいていどこかで、都市開発の波に飲まれその経路が見た目上わからなくなっている部分がある」。つまり、暗渠探しは常に不完全さを孕んでいます。
しかし、髙山氏はその不完全さを嘆くのではなく、むしろそこに知的な快楽を見出しています。「残されたピースを現場でコツコツと拾い集めながら川の経路を特定していく。『この場所があの場所と川で繋がっていたのか!』などといった思わぬ発見も経ながら、ついに元の流れが全て1つの経路に繋がった時、自分の脳内にこれまでと違った地図が出来上がっていることに気づく」
完全な真実、完璧な復元——そういうものを求めているのではない。痕跡を辿り、推理し、想像する、その過程そのものに価値がある。
二人とも、対象の「完全性」や「真正性」を超えた場所で、愛を育んでいるのです。
探偵としての偏愛者
ふなっしーと髙山氏に共通するもう一つの特徴は、彼らが「探偵」のような思考をしていることです。
髙山氏は暗渠を「街を舞台にした壮大なジグソーパズル」と呼びます。そして、その解き方を明確に説明しています。
水面を塞ぐ蓋、道の蛇行、高低差、土地や交差点の名前、取り残された橋跡や護岸跡、銭湯や染工所——これらすべてが「暗渠サイン」という手がかりになる。「消えてしまった川の全体像を推理する手がかりであり、街を舞台にした壮大なジグソーパズルのピースなのである」
この推理のプロセスには、論理的思考と想像力の両方が必要です。目の前にある断片的な証拠から、かつての全体像を復元していく。ミッシングリンクを埋めるために、地形、歴史、人々の生活様式についての知識を総動員する。
ふなっしーの刀への向き合い方にも、同じような探偵的思考が見られます。
刀の地鉄や刃文といった物理的特徴から、製作過程を推理する。「刀って、職人さんがもととなる鉄の塊を何ヶ月もかけて製鉄して、それを刀匠さんが何ヶ月もかけて作刀して、研ぎ師さんが研いで。やっっっと完成するもの」。この製作工程の理解は、単なる知識の習得ではなく、刀に込められた時間と労力を「読み解く」行為です。
そして、最初に買った村正が別の刀匠の作だったという「事件」も、ふなっしーにとっては新たな推理のきっかけになりました。では、この刀は誰が、いつ、どのように作ったのか? そういった探求が、さらなる学びへと繋がっていく。
杉山昂平氏らの余暇研究では、趣味における興味の深まりには専門的なスキルや知識の獲得が重要だと指摘されています。しかし、ふなっしーと髙山氏のケースで興味深いのは、その知識獲得の方法が「探偵的推理」という形を取っていることです。
与えられた情報を受動的に吸収するのではなく、断片的な手がかりから能動的に真実を構築していく。この知的な緊張感と達成感が、偏愛をより深いものにしているように思います。
時間の地層を掘る行為
二人の偏愛には、独特の時間感覚があります。それは、過去と現在が重層的に存在しているという感覚です。
髙山氏の表現が、これを端的に示しています。「水は残らずとも川の魂が残っていると考えて、ここではこれも暗渠と呼ぶことにする」
物理的には水が流れていない。でも、かつて川だった「魂」は残っている。過去は完全に消え去ったわけではなく、現在の地層の下に、静かに眠っている。暗渠を辿る行為は、その眠っている過去を掘り起こし、現在の表面に浮かび上がらせることなのです。
ふなっしーが刀に感じるのも、同じような時間の重層性です。「悠久の時を経てふなっしーのもとに来てくれた、という感動」。
刀は単なる物体ではありません。それは、何百年も前に作られ、様々な人の手を経て、今、ふなっしーの手元にある。その時間の重みを、ふなっしーは「いま刀を手にしている瞬間」に感じ取っているのです。
この時間感覚は、現代社会が通常持つ時間感覚とは大きく異なります。
私たちは普段、「過去は過去、現在は現在」という直線的な時間の中で生きています。過去は終わったもの、もう戻れないもの。現在は今ここにあるもの。それらは明確に区別されています。
しかし、偏愛者の時間感覚は違う。過去と現在は、対象を媒介として、同時に存在しうるのです。
髙山氏が暗渠を眺めるとき、そこには現在のアスファルトの道と、かつて流れていた川が、同時に「見えて」います。ふなっしーが刀を手にするとき、そこには今の自分と、何百年も前にこの刀を作った刀匠が、同時に「存在して」います。
これは単なる想像や妄想ではありません。認知科学的に見れば、知識と想像力を用いて過去の状態を再構成し、それを現在の知覚と重ね合わせる、高度な認知活動です。
そして、この時間の重層性こそが、二人に独特の世界観をもたらしているのです。
妄想と論理の往復運動
髙山氏は、暗渠観察に二つの視点があると語ります。「だから視点」と「として視点」です。
「だから視点」は論理的・左脳的な見方です。「川だからこうなった」「こうなった、なぜならば川だったから」という因果関係を読み解く。細長い公園や駐輪場、手作りの階段、道路テクスチャの違い——それらが「川だった証拠」として論理的に理解される。
一方、「として視点」はもっと自由で創造的です。暗渠脇の草花を「水の豊かな川辺に萌え咲く花」として見る。暗渠上のごみを「川の淀みに集まり浮かぶ芥」として見る。現在のアスファルトの道を、今もある川として眺める。
興味深いのは、髙山氏がこの二つの視点を対立するものとしてではなく、相補的なものとして捉えていることです。「世界を構成するロジックと、そしてロジックを超えて自らが創るマジックと、両方の景観がまばゆく広がるのである」
論理だけでは、世界は味気ない。妄想だけでは、根拠がない。両方を行き来することで、豊かな世界が立ち上がってくる。
ふなっしーの刀への向き合い方にも、同じ構造があります。
一方では、刀の地鉄や刃文を科学的・技術的に理解しようとする。製作工程、素材、時代による違い——それらを論理的に学んでいく。
しかし同時に、ふなっしーはこう語ります。「作り手がこの刀や焼き物で表したいものは宇宙のすべてなんじゃないか? と考えるようになったなっし。作品のなかに閉じ込められている花鳥風月を感じるようになったというか」
これは論理を超えた、詩的で形而上学的な理解です。刀の中に「宇宙のすべて」を見る。それは科学的に証明できることではないけれど、ふなっしーにとっては確かな実感なのです。
二人とも、論理と妄想、科学と詩、分析と直感——そういった二項対立を往復しながら、対象への理解を深めています。
そして、この往復運動こそが、偏愛を単なる知識の蓄積や感情的な執着とは異なる、より複雑で豊かなものにしているのかもしれません。
視野拡張の連鎖メカニズム
二人の語りの中で、特に印象的なのは「一つのことを深めたら、世界が広がった」という体験の共有です。
ふなっしーの場合、その連鎖は驚くほど広範囲に及んでいます。
日本史好き → 村正(刀匠)への興味 → 日本刀全般への偏愛 → 焼き物への関心 → 茶道 → 華道
刀から焼き物へ。その接続は、古田織部という人物を通じてなされました。「古田織部という武将。千利休の弟子でもあり、茶人としても知られている人なんですけど、古田が発案した織部焼を調べはじめたら楽しくなって」
そして、焼き物と刀の共通点を発見します。「どちらも鉱物から作られるものだし、窯に入れたあとは焼き上がるまで出来が分からない、仕上がりは成り行きに任せる! ってところも似ているなっし」
刀と焼き物が「鉱物」「窯」「成り行き」というキーワードで結びつく。この発見が、さらに次の扉を開く。「いまでは刀と同じくらい焼き物も増えて、毎日好きな器でお抹茶を立てるのが日課になっているなっし」。茶道へ。そして「花も生けるんです」——華道へ。
髙山氏の場合も、暗渠を起点に世界が広がっています。
暗渠を辿る → 銭湯や染工所に気づく → 地域の歴史が見えてくる → 行政境界の意味が理解できる → 都市の構造が立体的に見えてくる
「暗渠サイン」として挙げられている要素を見てください。橋跡、護岸跡、銭湯、染工所、特定の寺社、行政境界——これらはすべて、最初は暗渠の「手がかり」として注目されたものです。しかし、それらに注目していくうちに、それぞれが独自の意味と歴史を持つことに気づいていく。
なぜこの場所に銭湯があるのか? なぜこの寺社はここにあるのか? そういった問いが、暗渠の探求から自然に生まれてくるのです。
この視野拡張のメカニズムには、ある種の法則性があるように思います。
一つのことを深く掘り下げていくと、必然的に関連する領域が見えてくる。そして、その関連領域を理解するために、さらに別の知識が必要になる。気づけば、最初に興味を持った対象から、かなり離れた場所まで旅をしている。
しかし重要なのは、この広がりが散漫なものではないということです。ふなっしーにとって、刀も焼き物も茶道も華道も、すべて「鉱物」「窯」「成り行き」「花鳥風月」といった、共通のテーマで繋がっています。
髙山氏にとって、暗渠も銭湯も寺社も行政境界も、すべて「水の流れ」という一本の糸で結ばれている。
専門性を深めることと視野が広がることは、しばしば矛盾すると思われがちです。一つのことに集中すれば、他のことが見えなくなる——そう考えられることが多い。
しかし、二人の体験は、それが誤解であることを示しています。一つのことを本当に深く掘り下げると、その対象は必然的に他の領域と繋がっていて、結果として世界全体への理解が深まるのです。
死生観の変容
ふなっしーの語りの中で、最も心を打たれる言葉があります。
「刀を好きになってからは、生きる意味も考えるようになったなしよ。ふなっしーにとって日本刀は、そんな豊かさを与えてくれた存在なっし」
そして、こうも語ります。「刀に出会って『死生観』も変わったなっしな」「いつ死んでも悔いなく生きようと思う様になった」
偏愛が趣味や嗜好を超えて、生き方そのもの、死との向き合い方そのものを変えている。
なぜ、日本刀への愛が死生観の変容にまで繋がるのか。
一つには、先ほど述べた時間の重層性があるでしょう。何百年も前に作られた刀を手にするとき、ふなっしーは自分という存在の儚さと、同時に、何かがずっと受け継がれていく連続性を感じているのかもしれません。
自分は死ぬ。でも、この刀は残る。そして、また誰かの手に渡り、愛される。そういう時間の流れの中に、自分も位置づけられているという感覚。
もう一つには、「森羅万象」への気づきがあります。
「作り手がこの刀や焼き物で表したいものは宇宙のすべてなんじゃないか?」「もういまは月が明るいだけで嬉しいし、ぜんぜん見向きもしなかった道端の花に目がいったりとか」
刀を通して、世界の見え方が変わった。些細なことに美しさを見出せるようになった。日常の中に、以前は気づかなかった豊かさがあることに気づいた。
この変化は、単に「感受性が高まった」というだけではないように思います。もっと根本的な、世界との関わり方そのものが変わったのではないでしょうか。
髙山氏の場合、死生観についての直接的な言及はありませんが、暗渠を通して「時間の流れ」や「変化」について深く考えていることは明らかです。
川は流れていた。それが暗渠になった。でも、その記憶は残っている。すべては変化し続けるけれど、完全に消え去るわけではない——そういう、諸行無常と不変の真理が共存する世界観が、暗渠観察から見えてくるのかもしれません。
二人とも、偏愛を通して、生と死、変化と永続、一瞬と永遠——そういった根源的なテーマと向き合っているように感じます。
対象の二重性
最後に触れておきたいのは、二人が愛する対象が持つ「二重性」です。
刀は、武器であり美術品です。人を殺すための道具であり、同時に、美しさを鑑賞する対象です。実用性と芸術性。暴力と美。この相反する二つの性質が、一つの物体の中に同居しています。
ふなっしーは刀を「武器のイメージも根付いているけど、もとは各家庭で代々受け継いできたお守りのような位置付けだったなっしな」と語ります。武器/お守り。殺すもの/守るもの。これもまた、対照的な二面性です。
暗渠もまた、二重の存在です。
それは川であり、道路です。水が流れる場所であり、人が歩く場所です。自然であり、都市です。過去であり、現在です。
髙山氏の「として視点」は、まさにこの二重性を楽しむ態度と言えるでしょう。アスファルトの道を、同時に川として見る。二つの現実を重ね合わせる。
この二重性こそが、二人の偏愛を深く、複雑で、豊かなものにしているのかもしれません。
単純に「良いもの」「美しいもの」を愛するのではない。矛盾や葛藤を孕んだ、複雑な存在を愛する。その複雑さを受け入れ、楽しむ。
刀が武器であることを否定せず、でも美術品としても愛する。暗渠が川でなくなったことを嘆きながら、でも今の姿も楽しむ。
この二重性への寛容さ、あるいは積極的な享受が、偏愛者の持つ成熟した態度のように思います。
それぞれの孤独を想う
ここまで、二人の共通点を分析してきました。しかし同時に、二人それぞれが抱えてきた孤独についても、思いを馳せずにはいられません。
ふなっしーは「刀好きあるあるなその現象」として「刀が刀を呼ぶ現象」を語ります。「ふなっしーもなるべく増やさないように努力はしていますけど!! 気がついたら増えているなっしなー」
この言葉には、コレクションが増え続けることへの葛藤が滲んでいます。周囲からは「また買ったの?」と言われているかもしれない。自分でも「増やさないように」と思っているのに、止められない。
60振り以上の刀を持つということは、それだけの金銭的な投資をしているということです。一振り52万円。決して小さな額ではありません。きっと、周りの人からは理解されない出費だったでしょう。
髙山氏が記事の冒頭で語る言葉も、切実です。
「『一般的な趣味嗜好からちょっと外れたもの』を愛する人ならわかっていただけるだろう。自分の愛するものを人に伝える難しさを。そしてその愛を伝える機会の希少さを」
この「伝える難しさ」は、多くの偏愛者が感じていることでしょう。暗渠の魅力を語っても、多くの人は「地下の水路の何が面白いの?」と思うかもしれない。道路のテクスチャの違いに興奮しても、共感してくれる人は少ない。
でも、髙山氏は「PinTo Timesに感謝を申し上げたい」と記しています。伝える機会を得られたことへの、深い感謝。
二人とも、きっと長い間、この孤独と付き合ってきたのだと思います。理解されない寂しさ。共有できない喜び。一人で向き合い続けることの、静かな辛さ。
でも同時に、その孤独があったからこそ、愛が深まった面もあるのかもしれません。誰かに理解してもらうためではなく、ただ自分が愛するから愛する。その純粋さが、二人の語りから伝わってきます。
現代社会における「消されたもの」への偏愛
二人の偏愛を現代社会の文脈で考えると、ある種の社会的な意味が見えてきます。
私たちが生きる現代社会は、常に「新しいもの」を求めます。最新のテクノロジー、新しいトレンド、革新的なサービス。古いものは価値が低いとされ、捨てられ、忘れられていきます。
効率性と生産性が重視される中で、無駄なものは排除されます。都市開発のために川は暗渠化され、非武装化のために刀は没収される。それらは「合理的」な判断として行われました。
しかし、そこで失われたものは、本当に「無価値」だったのでしょうか。
ふなっしーと髙山氏の偏愛は、その問いを投げかけているように思います。
消されたもの、隠されたもの、忘れられたもの——それらにも、確かな価値がある。ただ、その価値は、数値化できないし、すぐに役立つわけでもない。だから、見過ごされてしまう。
でも、偏愛者はそれを見過ごしません。一見無価値に見えるものの中に、深い意味と美しさを見出します。
杉山昂平氏らの研究では、シリアスレジャーとしての趣味は専門的な知識と継続的な関与を特徴とすると指摘されています。しかし、ふなっしーと髙山氏のケースで重要なのは、その専門性が「失われたもの」の価値を再発見し、社会に提示する行為になっているということです。
二人は、単に個人的な趣味を楽しんでいるだけではありません。社会が捨て去ったものを拾い上げ、その価値を証明しています。
ふなっしーが刀の魅力を語ることで、戦後忘れられていた日本刀文化への関心が高まるかもしれない。髙山氏が暗渠を辿ることで、都市開発で失われた川の記憶が蘇るかもしれない。
偏愛者は、現代社会の「忘却」に抗う、静かな抵抗者なのかもしれません。
おわりに
今回、日本刀を愛するふなっしーと、暗渠を愛する髙山英男氏の語りを重ね合わせることで、私たちPinTo Times編集部は、偏愛の新しい側面を発見しました。
それは「失われたもの」「消されたもの」「隠されたもの」への、深く切実な愛です。
二人は、社会の大きな力によって視界から消されたものを、探偵のように追いかけています。断片的な痕跡から全体像を推理し、時間の層を掘り起こし、論理と想像力を駆使して、失われた世界を蘇らせようとしています。
そして、その過程で、二人自身の世界観が変容していきました。視野が広がり、死生観が変わり、日常の些細なことに美しさを見出せるようになった。
偏愛は、単に「好きなものがある」という状態ではありません。それは、世界との関わり方そのものを変える、深い認識の変容なのです。
今回の分析を通じて、私たちはいくつかの問いを抱えるようになりました。
他にも「失われたもの」への偏愛を持つ人たちがいるのではないか。廃墟、古い建築、消えゆく方言、失われつつある職人技——そういったものに惹かれる人たちの中に、ふなっしーや髙山氏と同じような構造の偏愛があるのではないか。
また、「消されたもの」への偏愛と、「現在進行形で存在するもの」への偏愛とでは、何が違うのか。喪失の経験は、偏愛にどのような影響を与えるのか。
さらに、探偵的な思考、推理する快楽は、他の偏愛者にも共通するのか。不完全さを受け入れ、真贋を超えていく態度は、どのような心理的メカニズムから生まれるのか。
これらの問いに答えるためには、さらに多くの偏愛者の声を聞く必要があります。
PinTo Times編集部は、これからも偏愛者たちの語りに耳を傾け続けます。その中から、偏愛という現象の本質を、少しずつ明らかにしていきたいと思います。
そして、偏愛者たちが「消されたもの」に光を当てるように、私たちも、見過ごされがちな偏愛者たちの声に光を当てていきたいのです。
失われた世界への探偵たちの物語は、まだ始まったばかりです。