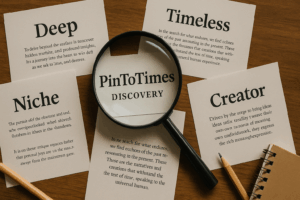それ、こだわり? それとも偏愛?──目的と意味のあいだで

一見よく似た「こだわり」と「偏愛」
「このコーヒー豆しか飲まないんです」 「文房具は全部、あのメーカーで揃えていて」 「最近はこの通り道じゃないと気持ち悪くて」
そんな話を耳にすると、偏愛と似ているように思える。強い執着や習慣を貫く姿勢には、たしかに近い要素がある。けれど、偏愛者と日々接してきた私には、それだけを偏愛と呼ぶのはどうしても違和感が残る。似ている。けれど、違う。
こだわりは、自分の生活や感覚を整えるための選択に近い。偏愛は、自分でも説明がつかない“震え”をなんとか言葉にしようとする営みだ。表面的な行動は似ていても、その奥の構造はまったく別物に見える。
こだわりは再現できるし、説明もしやすい。偏愛は非合理で、他人には伝えにくい。そもそも、伝えるためにあるわけでもない。それは「自分にしか聞こえない周波数」をずっと受信しているようなもの。意味があるのかどうかはわからない。けれど、そのノイズが消えたら日常の支えがごっそり失われる。偏愛は、静かで確かなかたちで生活の中に根を下ろしている。
「こだわり」は、ベネフィットが前提にある
こだわりは明快だ。理由がはっきりしている。
「書きやすいからこのペン」 「この道が一番速いから」 「このスニーカーが一番疲れにくいから」
つまり、そこには機能性や目的合理性といったベネフィットがある。たとえば「音質にこだわってケーブルに投資する」という人がいたとする。その背景には「よりクリアに聴きたい」「このジャンルの音楽に最適」という理由がある。こだわりは“良くするための選択”であり、再現可能で、他者にも伝わる論理を持っている。
自己基準を確立し、それに沿って生活を整えるのがこだわりだ。合理的で、筋が通っていて、説明がしやすい。深めればマニアックにはなるが、それでも「良い理由」が存在している点が、偏愛との決定的な違いになる。
「偏愛」は、その人にしか通じない論理でできている
偏愛は、他人にはわからない理由で続いていく。たとえば──
「自動販売機の良さって優しさなんですよ」 「火曜サスペンスごっこを続けることが恩返しになるんです」 「地図を見れば暗渠かどうかわかるようになりました」
外から見れば突拍子もない。けれど本人にとっては切実だ。共通するのは、他者にはスムーズに理解されない論理で動いているということ。偏愛者自身も「なぜこんなに気になるのか」を自分に問い続けている。その語りは「これがいいでしょ?」ではなく「どうしても離れられない」という自問に近い。
さらに、こだわりと大きく違うのは持続力だ。こだわりは合理的だから、条件が変わればあっさり終わる。「もっと良いものが出たから」「状況に合わなくなったから」。合理的であるほど、終わる理由もすぐに見つかる。
偏愛は違う。理由がないからこそ続いてしまう。「なぜか惹かれてしまう」「忘れられない」。目的がないから、終わるきっかけもない。時間が経つほど根を張っていく。合理的なものほど長く続かない一方で、偏愛は説明不能だからこそ持続してしまう。そこに、静かで強い熱が宿る。
「語ること」は、自己理解のためにある
偏愛者は語ることがある。だがそれは、誰かに理解してほしいからではない。語ることで自分の偏愛の輪郭を確かめようとしている。言葉にすることで、少しだけ理由に近づいたり、逆にわからなさをはっきりさせたりする。偏愛の語りは、外向きのプレゼンではなく内向きの探索だ。
テンションが高まって思わず話してしまう瞬間もある。だがその直後に「空気読めてなかったな」「話すことじゃなかった」と自己嫌悪に陥ることもある。偏愛が語られるのは、他者のためではなく自己理解のため。この複雑さが偏愛を偏愛たらしめている。
「熱」と「冷静さ」が同居している
偏愛者は熱狂しながらも、自分を俯瞰している。夜中に検索履歴を埋め尽くし、同じ曲を何十回も聴き返し、展示が終わっても図録の紙を触って記憶を呼び戻す。その一方で「やりすぎだよな」「引かれるかも」と冷静な自分もいる。偏愛者は、自分の感覚が社会の温度とずれていることを知っている。ただ、そのズレに敏感であるだけだ。
情熱と知性が同居しているのが偏愛だ。心が動きすぎる自分と、それを理解しようとする自分、さらにそれが他者にどう見えるかを察知する自分。その重層性こそが、こだわりとは異なる深さを生む。
それは、こだわりでは説明できなかった
こだわりには理由がある。偏愛には意味がある。こだわりは整える行為。偏愛は探していく行為。
こだわりが「生活を良くする工夫」だとすれば、偏愛は「まだ知らない自分を見つけるための営み」に近い。他者には伝わらないが、自分にはどうしても無視できない。説明もできないし、共有もされない。けれど、それがなければ自分ではなくなる。
どうやら偏愛は、自分の“好き”の輪郭に名前を与え続ける営みらしい。その営みが少しずつ世界のピントを変えていく。派手さでは測れない、静かな熱。だからこそ、他人の偏愛に触れるたびに、自分の中の“好き”にも耳を澄ませたくなるのだ。
もしかすると、この記事を読んだあとに、あなた自身の“好き”にも目を向けてみるのも面白いかもしれない。それがこだわりなのか、偏愛なのか。答えはひとつではなくても、その問いを立ててみることが、世界の見え方を変えるきっかけになるはずだ。