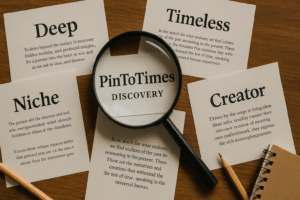継続する愛の、3つの真実。魔女っ子おもちゃと昆虫、異なる偏愛に宿る共通の核心

「子供のようにいつかおもちゃを卒業してしまうことも無いのだから」と語る魔女っ子おもちゃコレクターのちずるさん。「デザインとして完成されていて、曖昧な部分が一つもない」と虫の美しさを語るラッパーの呂布カルマさん。
この2人の言葉を聞き比べていると、偏愛という現象の輪郭が少しずつ見えてくる。それぞれの愛の対象は全く違うのに、愛し方そのものには驚くほど似た特徴がある。偏愛者とは一体どのような人たちなのか。2つの異なる愛から、その本質に迫ってみたい。
呂布カルマに訊く、正しい虫の愛し方【前編】
ラッパーの呂布カルマはかつての虫嫌いを克服し、今では虫の飼育が毎シーズンの楽しみになっているほど。話を伺うと、呂布カルマの人生の哲学までもが浮かび上がってきた。
プリティでマジカル!だけじゃない、魔女っ子おもちゃの奥深き世界。【前編】
魔女っ子おもちゃを収集し、原作ではなく“玩具そのもの”の愛を綴ったブログを発信し続けるちずるさんが、魔女っ子おもちゃの歴史とその魅力をたっぷりと語る。
「卒業」という概念の不在
ちずるさんが印象的に語ったのは、「魔女っ子おもちゃ好き卒業のタイミングが訪れず」という体験だった。多くの人が何らかのきっかけで子供時代の興味から離れていく中で、彼女だけはその瞬間が来なかった。それどころか、大人になってからの方がより深く、より情熱的にこの世界に向き合っている。
呂布カルマさんの場合は少し異なる。20代半ばまでは一般的な「虫嫌い」だったが、富士山のレイブでヤママユガと出会った瞬間から虫への愛が始まった。そしてその愛は今や毎シーズンの楽しみとして定着し、「暖かくなったら芋虫と、今年はカマキリも飼いたい」と自然なリズムの一部になっている。
2人に共通するのは、偏愛が一時的な熱狂ではなく、生活に深く根ざした継続的な関係性だということだ。株式会社マルハンの調査によると、小学校卒業までに偏愛を見つけた人は、その後も長期間にわたって愛を持続させる傾向が高いという結果が出ている¹。ちずるさんの体験は、まさにこの傾向を体現している。
興味深いのは、この継続性が意識的な選択というよりも、自然発生的なものであることだ。ちずるさんは「卒業のタイミングが訪れず」と表現し、呂布カルマさんは虫との出会いを「流れ星的なうれしさ」と感じている。偏愛者にとって、その愛は努力して維持するものではなく、気がつけばそこにあるもののようだ。
対象への独自の美学
ちずるさんの偏愛で特に興味深いのは「原作<おもちゃ」という価値観だ。一般的なファンとは逆で、「作品のファンだからおもちゃを買うのではなく、どんなおもちゃが展開するのか楽しみだから作品をチェックする」という関係性を築いている。彼女にとって魔女っ子おもちゃは、アニメの付属品ではなく、それ自体が主役の存在なのだ。
さらに興味深いのは、彼女が玩具の時代変遷を詳細に分析していることだ。80年代の「キャラ顔主張ファンシー時代」から2000年代の「デジタルデバイス時代」まで、各時代の特徴を技術的・美学的観点から捉えている。これは単なる収集ではなく、一つの文化史研究に近い視点と言えるだろう。
呂布カルマさんも同様に、独自の美学を持っている。虫に感情移入することはなく、「ある種の鑑賞物として捉えている」と語る。彼が虫に惹かれるのは、「左右対称の美しさ」や「機能美を追求しているような」デザイン性に対してだ。特に印象的なのは、「こんなの、誰かがデザインした以外ないじゃん」という表現で、虫の形態に「神の意思」のようなものを感じ取っている。
2人とも、対象が持つ一般的な価値や文脈を超えて、独自の評価軸で世界を見ている。ちずるさんはアニメの人気やストーリーよりも玩具の造形やデザインの進化に注目し、呂布カルマさんは虫の生態的役割よりも視覚的完成度に心を奪われる。この独自の美学こそが、偏愛者を他のファンと区別する重要な要素なのかもしれない。
理解の境界線という現実
しかし、偏愛者の道には避けて通れない現実がある。ちずるさんは「大人の魔女っ子おもちゃファンは滅茶苦茶に少ない」状況を冷静に分析している。当時の玩具が高値で取引されているため新規参入が困難で、「魔女っ子おもちゃコレクターへの道は間口が非常に狭い」ものになっている。彼女は一人で愛を貫いているが、その孤独感は言葉の端々に滲み出ている。
呂布カルマさんの場合、より身近な場所での理解の壁に直面している。「これだけ熱っぽく虫への愛を語っても、一番近くにいる嫁さんのことも納得させられないっていうのは、本当に無力感がある」という言葉には、偏愛者が感じる深い孤独が表れている。最も身近な人にすら理解してもらえない辛さは、偏愛者に特有の体験かもしれない。
心理学者の岸正龍氏は、偏愛について「あくまでも自分とその対象の閉じた世界」であり、「その偏愛を誰かに押しつけた瞬間にウザい人になってしまう」と指摘している²。偏愛者は自分の愛を分かち合いたい気持ちと、それが理解されない現実の間で、常に複雑な感情を抱えているのだろう。
それでも2人は、その理解の境界線を受け入れながら愛を続けている。ちずるさんは新規のファンが増えにくい現状を客観的に分析しつつも収集を続け、呂布カルマさんは家族の協力を得られない制約の中でも虫への愛を語り続けている。この現実との向き合い方にも、偏愛者の特質が表れているように思う。
偏愛者という存在が照らし出すもの
2人の体験を追いかけていると、偏愛者が単に「好きなものがある人」ではないことがわかる。ちずるさんは魔女っ子おもちゃを通して玩具業界の文化史を記録し、呂布カルマさんは虫を通して都市生活に生態系への気づきをもたらしている。
特に興味深いのは、2人とも偏愛を通して日常の認識を変えていることだ。ちずるさんにとって新作の玩具情報は生活の「ワクワク」の源泉であり、呂布カルマさんにとって虫との出会いは「街の解像度が上がった」体験をもたらしている。「この木があるってことは、この虫がいるかもしれない」という視点は、都市空間に新しい発見を与えている。
実際に偏愛者の3人に2人(66.6%)が幸福感を感じているという調査結果¹も、偏愛が人生の充実感に寄与していることを示している。偏愛者は、自分だけの価値基準で世界を見つめ、そこから継続的な喜びを得ている人たちなのかもしれない。
現代社会における偏愛者の意味
情報が溢れ、注意が散漫になりがちな現代において、偏愛者のような深い集中力と持続的な関心を持つ人々の存在は、ある種の希少性を持っているように思える。シカゴ大学の研究では、生涯を通じて情報収集活動を続けた人ほど認知能力が高い傾向が見られたという報告もあり²、偏愛者が示す持続的な探求心や観察力は、認知機能の維持にも寄与している可能性がある。
ちずるさんが語る玩具業界の変遷への洞察や、呂布カルマさんが発見する虫の美学は、それぞれの分野における貴重な記録でもある。偏愛者は、専門的な研究者とは異なる角度から、文化や自然についての深い理解を蓄積している。
また、2人の体験から見えてくるのは、偏愛が流行や外的評価に左右されない安定した価値基準を提供していることだ。自分なりの美学で世界を見つめ続ける姿勢は、精神的な自立につながっているように見える。
偏愛の始まりと育ち
偏愛はどのように生まれるのだろうか。ちずるさんの場合、祖母が買ってくれた「ピンクなネイルグロス」との出会いが原点にある。呂布カルマさんは富士山のレイブで動けない状況でヤママユガをじっと見つめたことがきっかけだった。
興味深いのは、どちらも偶然の出会いから始まっていることだ。計画的に偏愛者になったわけではなく、日常の中での小さな発見や体験が、やがて深い愛情に育っていった。偏愛は、おそらく誰にでも起こりうる小さな奇跡なのかもしれない。
ただし、すべての人が偏愛者になるわけではない。多くの人は途中で興味を失ったり、他のことに関心が移ったりする。偏愛者になるには、最初の発見を大切に育て続ける何かが必要なのだろう。
2人の体験を聞いていると、偏愛者は特別な能力を持った人というよりも、普通の感性を大切に育て続けた人のように思えてくる。子供の頃の素直な驚きや好奇心を、大人になっても手放さなかった人たちなのかもしれない。
偏愛者の声を聞き続けることの意味
今回、魔女っ子おもちゃと昆虫という全く異なる2つの偏愛を比較することで、偏愛という現象に共通する3つの真実が見えてきた。「卒業」という概念の不在、対象への独自の美学、そして理解の境界線という現実。
これらの共通点は、偏愛が単なる趣味や嗜好を超えて、その人の世界観や生き方に深く根ざした愛情の形であることを示している。偏愛者は、自分だけの価値基準で世界を見つめ、そこから継続的な発見と喜びを得ている人たちなのだ。
PinTo Times編集部として、今後もさまざまな偏愛者の声に耳を傾けていきたいと思う。特に探求したいのは、偏愛者同士がどのような共通の心理的メカニズムを持っているのか、そして偏愛が人生の各段階でどのように変化し、深化していくのかという点だ。
また、偏愛者が現代社会とどのような関係を築いているのかも重要なテーマだ。理解されにくさという課題を抱えながらも、偏愛者はどのようにして自分の愛を表現し、時には他者と分かち合っているのか。そこには、現代社会を生きる私たちにとって大切な示唆が含まれているように思う。
偏愛者の体験には、情報過多で注意散漫になりがちな時代において、一つのことを深く愛し続ける意味と価値が込められている。編集部として、これからも偏愛者の皆さんの声を丁寧に記録し、その豊かな世界を読者の皆さんと分かち合っていきたい。
参考文献
¹ 株式会社マルハン「【偏愛】こそ、現代日本人の『幸福の源』!」調査結果, 2024年
² 岸正龍「なぜいま偏愛なのか? 趣味が脳に与える影響」, 2024年
呂布カルマに訊く、正しい虫の愛し方【前編】
ラッパーの呂布カルマはかつての虫嫌いを克服し、今では虫の飼育が毎シーズンの楽しみになっているほど。話を伺うと、呂布カルマの人生の哲学までもが浮かび上がってきた。
プリティでマジカル!だけじゃない、魔女っ子おもちゃの奥深き世界。【前編】
魔女っ子おもちゃを収集し、原作ではなく“玩具そのもの”の愛を綴ったブログを発信し続けるちずるさんが、魔女っ子おもちゃの歴史とその魅力をたっぷりと語る。