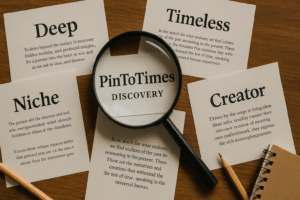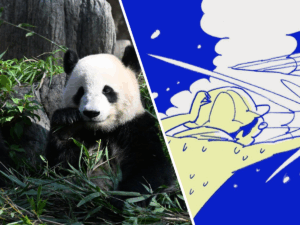「やかん亭」店主と路上園芸家が示す!「一点集中」がひらく豊かな世界と「はみだし者」の美学

一杯のラーメンと一輪の草花が教えてくれた、偏愛の5つの扉
37年間毎日インスタントラーメンを食べ続ける大和一郎さんと、街角の植物を愛で続ける村田あやこさん。一見何の接点もない2つの偏愛の世界を眺めていると、なんだか不思議な既視感を覚える。
この2人が歩む道のりには、私たちがまだ気づいていない「偏愛の法則」が隠されているのではないだろうか。
一日一麺、底なしインスタントラーメン沼。
一日一麺を37年間続けてきた生粋のインスタントラーメン偏愛者・大和一郎。その偏愛ぶりはとどまるところを知らず、「やかん亭」という専門店まで出店してしまうほど。全国のインスタントラーメンを食べてきたからこそわかる、さまざまな魅力、商品の変遷を語ります。
はみだすものたちに魅せられて。〜路上園芸を愛で続けていたら見えてきた街の素顔〜
街中の路上にはみだす園芸や植物を「路上園芸」と称し、愛で続ける路上園芸鑑賞家・村田あやこ。独自の視点で楽しむ趣味が次第に偏愛へ、そして現在は路上園芸鑑賞家として出版やイベントなどの活動も行っている彼女だからこそ語れる、「路上園芸」から見る街の素顔。
第一の扉:予期せぬ出会いという始まりの魔法
大和さんのインスタントラーメン愛は、高校生の時の交通事故による記憶喪失から始まった。名前も忘れるほどの記憶を失った中で、なぜか毎回手に取るカップ麺。ドクターが「何かあるかも?」と毎日食べさせたことで、少しずつ記憶が戻ってきたという。
一方、村田さんの路上園芸との出会いは、会社を辞めて人生の方向性を模索していた20代半ばのこと。植物で空間を装飾する仕事を考えていた時に、ふと目に入った商店裏手の鉢植えに心を奪われた。「雨風で風化したプランターの中で、もともと植えたらしき植物と、それを凌ぐ密度で茂る、勝手に根ざしたらしき植物」が織りなす風景に。
この2つのエピソードから見えてくるのは、偏愛は人生の隙間に突然現れるということだ。順風満帆な日常の中ではなく、むしろ何かが欠けた状態や、人生の迷いの中で、運命的な出会いが起こっている。
私も振り返ってみると、自分の大切な「好き」の多くは、予定していた道筋から外れた時に出会ったものだった。実際、日本認知科学会が編集した『創造性はどこからくるか』では、創造性が「他者との協同や外化など、偏在する外部資源との相互作用なくしては成り立たない」ことや、「アイデアの『生みの苦しみ』は単なる停滞ではない」ことが明らかにされている¹。偏愛者の皆さんも、そんな経験があるのではないだろうか。
第二の扉:見落とされているものへの愛おしさ
大和さんが本格的にインスタントラーメンの世界にのめり込んだきっかけは、国鉄労働組合が活動資金のために販売していた「こくろうラーメン」との出会いだった。「正直いうとお世辞にもおいしいとはいえないラーメンだった」と本人も認めているが、「インスタントラーメンにこんな使い方があったのか!」という驚きと、「一部の地域の方しか知らない『ご当地感』」に異常な魅力を感じてしまったという。
村田さんが魅力を感じるのは、商業施設の美しい植栽ではなく、「ガードレールやフェンスの下、マンホール蓋の小さな穴、郵便ポストの足もと、舗装のひび割れ」に自然発生的に根ざしている小さな植物たち。整えられた園芸ではなく、「生活とともに育まれてきた肩の力が抜けた緑の風景」に心を奪われている。
2人とも、世の中の多くの人が見向きもしない、むしろ「はみだしもの」として扱われがちなものに深い愛情を注いでいる。メジャーなものより、マイナーなもの。完璧なものより、ちょっと不完全なもの。管理されたものより、勝手に生まれたもの。
これは偏愛者の大きな特徴の一つかもしれない。みんなが注目するものではなく、見落とされがちなものにこそ、かけがえのない価値を見出す目を持っている。
第三の扉:記録することで生まれる物語
大和さんは食べ終わったインスタントラーメンのパッケージをずっと収集している。それは「皆さんのアルバムのようなもの」で、昔のパッケージコレクションを見ていると「ああ、この時はこんなことがあったなぁ〜」と過去の自分に戻れるタイムマシン的な存在だという。
村田さんは路上園芸の写真を撮り続け、それに独自のキャッチコピーをつけてSNSで発信している。「転職鉢」「植物のふりした妖怪」といった言葉遊びのような表現で、自分が感じた魅力を言語化していく。「すべっているかもしれない、ただの一人脳内大喜利大会」と謙遜しながらも、その言語化によって共感の輪が広がっていった。
偏愛者の多くは、ただ愛するだけでなく、その愛を形として残そうとする。写真、コレクション、文章、データベース。形はさまざまだが、愛の証拠を積み重ねていく行為そのものが、偏愛をより深いものにしているように思う。
大和さんのパッケージコレクションが「タイムマシン的な存在」となっているのも、記憶と愛着対象との深い結びつきを表している。
そして面白いのは、その記録がやがて個人的な思い出を超えて、時代や社会を映す貴重な資料になっていくことだ。大和さんのパッケージコレクションは「時代を映す鏡」となり、村田さんの路上園芸観察は「街の素顔」を浮き彫りにしている。
第四の扉:隙間から見える世界の真実
大和さんはインスタントラーメンを通じて、日本社会の変遷を読み解いている。庶民の食べ物であるインスタントラーメンは、「味やパッケージにその時代時代の流行やトレンドをとり入れなければ多くの人に買ってもらえない」。だからこそ、それらを見続けることで時代の空気感がつかめるのだという。
村田さんは路上園芸から、都市の隠れた構造を発見している。「そこに生えた植物の様子から、街の様々な隙間が可視化される」。大通りではなく小道に、中心ではなく周縁に、街の本当の顔が現れるのだと語る。
2人とも、自分の愛するものを通じて、社会の見えない部分を炙り出している。それは決して大上段に構えた社会批評ではなく、日々の小さな観察の積み重ねから自然に浮かび上がってくる洞察だ。
偏愛には、社会の隙間に光を当てる力がある。みんなが見ているメインストリームではなく、脇道や裏側から世界を眺めることで、違った景色が見えてくる。これは偏愛者だけが持つ特権的な視点なのかもしれない。
村田さんの路上園芸観察は、都市空間の新しい読み方を私たちに教えてくれる。
第五の扉:愛を仕事にする勇気
大和さんは37年間の偏愛を経て、ついに「やかん亭」というインスタントラーメン専門店を開業した。「日本でもレアなご当地インスタントラーメンだけを取り扱っているセレクトショップ」として、自分が本当においしいと思ったものだけを並べている。
村田さんは路上園芸についてライターとして記事を書き、ついには路上園芸をテーマにした本まで出版するに至った。「人生何が起こるかわからない」と振り返っているが、好きなことを続けていたらいつの間にか仕事になっていたという自然な流れがある。
2人とも、偏愛を社会に向けて発信し、それを通じて生計を立てるまでに発展させている。これは偏愛者の一つの理想形かもしれない。
ただし、彼らが「好きを仕事に」したのは、最初からそれを目指していたわけではない。むしろ、愛し続けていたら自然とそうなったという感じがする。打算的な計算ではなく、純粋な愛情を注ぎ続けた結果として、社会がその価値を認めてくれたのだ。
それぞれの生き方を想う
大和さんと村田さんの話を読んでいると、なんだかほっとした気持ちになる。それはなぜだろうか。
一つには、2人とも等身大の人間として描かれているからだと思う。完璧な専門家ではなく、偶然の出会いから始まって、試行錯誤しながら愛を深めてきた普通の人。私たちと同じように迷ったり悩んだりしながら、でも好きなものに対しては一途に向き合い続けている。
もう一つは、2人の愛情に打算がないことだ。インスタントラーメンも路上園芸も、決して世間的に「意識高い」趣味ではない。むしろちょっと変わった趣味として見られがちなものを、堂々と、そして心から愛している。その純粋さが、見ている側の心を動かすのだろう。
そして何より、2人とも愛するものを通じて、世界をより豊かに見せてくれる。インスタントラーメンという身近な食べ物が時代の鏡だなんて、考えたこともなかった。街角の雑草が都市の隙間を可視化するなんて、思いもよらなかった。
偏愛者は世界の見方を教えてくれる先生なのかもしれない。
偏愛者として生きるということ
ただ、偏愛者として生きることには、時として孤独感が伴うことも事実だ。自分の好きなものを理解してもらえない寂しさ。「なんでそんなものにハマってるの?」という言葉に傷つくこともある。大和さんも村田さんも、きっとそんな経験をしてきたはずだ。
それでも彼らが愛し続けるのは、その対象が彼らにとってかけがえのないものだからだ。偏愛者にとって、愛するものは単なる趣味を超えて、自分らしさの一部になっている。
大和さんの「やかん亭」を訪れる人たちは、大和さんの情熱に触れることで、新しい世界を知る喜びを感じているはずだ。村田さんの路上園芸観察も、読者に都市の新しい見方を教えてくれる。偏愛者は、自分の愛を通じて、他の人に新しい視点を提供している。
現代社会における偏愛の意味
SNSが普及し、情報が溢れる現代社会。みんなが同じようなものを「いいね」し、似たようなトレンドを追いかけている。そんな中で、大和さんや村田さんのような偏愛者の存在は、とても興味深い。
彼らは、みんなが見向きもしないものに価値を見出し、丁寧に愛を注ぎ続けている。もし偏愛者がいなかったら、世界はもっと画一的で退屈な場所になってしまうかもしれない。
また、表面的な情報のやり取りが主流の時代に、一つのものを長期間にわたって深く愛し続けている。37年間毎日インスタントラーメンを食べ続けるという大和さんの継続力には、現代人が忘れがちな「深く知ることの豊かさ」が表れている。
偏愛者たちの継続的な探求姿勢は、現代的な職人精神の表現なのかもしれない。
さらに、彼らは日常の中に隠れている美しさや面白さを見つけ出し、私たちに気づかせてくれる。路上園芸の魅力を語る村田さんの言葉を読むと、明日からの街歩きが少し楽しくなりそうだ。
偏愛という小さな冒険
この記事を読んでくださっているあなたの中にも、きっと何か心を動かされるものがあるのではないだろうか。
もしかしたら、それは大和さんのインスタントラーメンのように身近な食べ物かもしれない。もしかしたら、村田さんの路上園芸のように、普段は見過ごしてしまいそうな小さな発見かもしれない。もしかしたら、まだ出会っていない何かかもしれない。
2人の偏愛者から見えてくるのは、どちらも偶然の出会いから始まって、試行錯誤しながら愛を深めてきたということだ。大和さんは記憶喪失がきっかけで、村田さんは人生の方向性を模索していた時期の出会いだった。
偏愛の始まりは、何かに心を動かされる素直な気持ちと、それを大切に思い続ける気持ちからのようだ。
時には「なんでそんなものが好きなの?」と言われて寂しい思いをすることもあるかもしれない。でも、その愛は本人をより豊かにし、時には誰かの世界を広げることにもつながっていく。
大和さんのインスタントラーメン愛が「やかん亭」となって多くの人に新しい出会いを提供しているように。村田さんの路上園芸観察が本となって、都市の新しい見方を教えてくれているように。
最後に
一杯のインスタントラーメンと一輪の路上の草花。どちらも、多くの人が見過ごしてしまいそうな、ささやかな存在だ。
でも、そんな小さなものに深い愛を注ぎ続けた大和さんと村田さんの人生は、とても豊かで魅力的に見える。2人の分析を通じて、私たちPinTo Times編集部にとっても新しい発見がたくさんあった。
今回の分析で見えてきた「予期せぬ出会いから始まる偏愛」「記録することで深まる愛」「隙間から見える世界の真実」といったテーマは、きっと他の偏愛者の中にも共通して見つかるものかもしれない。
私たちは今後、さらに多くの偏愛者に出会い、話を聞いていきたいと思っている。偏愛の始まり方にはどんなパターンがあるのか。偏愛者はどのように孤独感と向き合っているのか。偏愛が人生に与える影響はどこまで広がっているのか。
また、偏愛者同士の組み合わせによって見えてくる新しい共通点や、まったく異なる偏愛の形もあるだろう。時代や世代によって偏愛の表現方法は変わっているのか。現代のデジタル社会は偏愛のあり方をどう変えているのか。
大和さんと村田さんから教えてもらった「隙間から始まる愛の物語」をきっかけに、私たちはこれからも偏愛者たちの声に耳を傾け、その奥深い世界を探求していきたい。
きっと、まだ私たちが知らない偏愛の形や、偏愛者たちだけが知っている世界の見え方が、たくさんあるはずだから。
参考文献
¹ 日本認知科学会・阿部慶賀(編)『創造性はどこからくるか: 潜在処理,外的資源,身体性から考える』共立出版, 2019年
https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10003214.html
参考文献
¹ 日本認知科学会・阿部慶賀(編)『創造性はどこからくるか: 潜在処理,外的資源,身体性から考える』共立出版, 2019年
関連記事
一日一麺、底なしインスタントラーメン沼。
一日一麺を37年間続けてきた生粋のインスタントラーメン偏愛者・大和一郎。その偏愛ぶりはとどまるところを知らず、「やかん亭」という専門店まで出店してしまうほど。全国のインスタントラーメンを食べてきたからこそわかる、さまざまな魅力、商品の変遷を語ります。
はみだすものたちに魅せられて。〜路上園芸を愛で続けていたら見えてきた街の素顔〜
街中の路上にはみだす園芸や植物を「路上園芸」と称し、愛で続ける路上園芸鑑賞家・村田あやこ。独自の視点で楽しむ趣味が次第に偏愛へ、そして現在は路上園芸鑑賞家として出版やイベントなどの活動も行っている彼女だからこそ語れる、「路上園芸」から見る街の素顔。