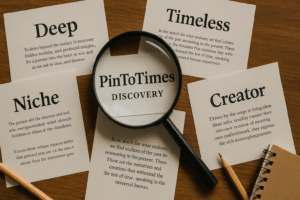応援ではなく、凝視である。―偏愛という静かな熱について

違和感の正体を、やっと言語化できたかもしれない
「「それ、推し活だね」。 取材や会話の中で、そんな言葉を耳にすることがある。 何かに夢中になっている人を見て、ついそう言いたくなる気持ちもわかる。 そして、言われた側もたいていは笑って「そうかも」と返す。けれど、そのあと小さく添えられる声がある。
「でもなんか……ちょっと違うんですよね」。
その“ちょっと”の違和感を、私はずっと追いかけてきた。 明るく健やかに、「これが好きです」と言える推し活という文化。 けれど、その語彙にすくい取られない、別の“好き”がある。
このメディアを通じて出会ってきた、いわゆる“偏愛者”たち。 誰に求められたわけでもなく、誰の役に立つかもわからない。 それでも「好き」でい続ける人たちがいた。 その語り口は、熱があるのに静かだった。 理解を求めるよりも、ただ——見つめているようだった。
一方、SNSやカルチャーの文脈でよく見る推し活には、もっと外向きの熱がある。 仲間を求めて声を上げるような、共有されることを前提にしたムーブメント。 「私はこれが好き」と旗を掲げることで、人とつながっていく営みだ。
どちらも「好き」から始まっている。 でも、その向き合い方や視線の方向は、まるで違って見える。
今日はその違いについて、私なりに言葉にしてみたいと思う。
推し活とは、“応援すること”である
推し活は、応援の文化だと思う。 誰かを支えたい、もっと見てほしい、売れてほしい——そんな願いとともに行動が生まれる。
K-POPのカムバに合わせてYouTubeの再生回数を回す。 声優の誕生日に合わせてお祝いの投稿をする。 VTuberの配信でスパチャを送り、推しに直接気持ちを届ける。
アニメのキャラクターにハッシュタグをつけて語り合い、 アクスタを痛バに詰めてイベントに遠征する。 CDや雑誌を買い、アンケートに答え、推しの「数字」をつくる。
そこには「応援する/される」という関係性がある。 “推し”とは、応援に値する存在として選ばれた誰かであり、 その応援は、個人の感情でありながらも、社会的な行為として機能している。
そしてもうひとつ、推し活には「共有」が前提としてある。 SNSを通じて仲間とつながり、共感し、熱を高めていく。 誰かと「同じ推し」を持つことで、楽しみは加速し、連帯が生まれる。
だからこそ、推し活は“明るい熱”を持つ。 自分の好きが誰かの好きとつながる喜び。 その感情が推し活を支えているのだと思う。
でも、偏愛には、それとは違う質の熱がある。
偏愛とは、“見つめつづけること”である
偏愛は、誰かに届けるためのものではなく、 ただ、その対象と向き合うための行為だと思う。
取材の中で出会ってきた偏愛者たちは、みな静かだった。 トタン屋根だけを全国で撮り歩く人。 線路脇の草木の変化を記録し続ける人。 業務用ボタンの手触りに取り憑かれたように語る人。
その語りには、他者の共感を求める熱はあまりない。 むしろ、「なぜ自分はこれに惹かれるのか?」を自分自身に問い続けるような、 内に向いたまなざしがあった。
偏愛には、評価のための言葉がないことが多い。 「美しい」でも「すごい」でもなく、ただ「気になってしまう」。 その説明できなさを抱えながら、それでも見つめ続けてしまう何か。
ある偏愛者はこう言っていた。 「最初は“好き”というより、“なぜ気になるのか自分でもわからない”という状態から始まるんです」。
“気になる”という小さな引っかかりを丁寧に追いかけていくうちに、 いつのまにかその対象が、自分の目や言葉や人生そのものの一部になっていく。
偏愛には、孤独がつきまとう。 でもそれは、寂しさではない。 誰かに見つけてもらえなくても、それでも見ていたいと思う感情。 その熱が、偏愛の根にある気がしている。
だから私は、偏愛は“応援”ではなく“凝視”だと思っている。
“共鳴”と“独語”——視線の方向がまったく違う
偏愛と推し活。 どちらも「好き」から始まっているのに、まったく違う場所へ向かっているように感じることがある。
推し活は、共鳴の文化だ。 「私もそれが好き」と言い合える仲間を求める。 誰かに届いてこそ意味がある。 その広がりこそが、推し活のエネルギーを支えている。
一方、偏愛は、独語に近い。 誰かに届かなくても構わない。 むしろ、届かないからこそ見えてくるものがあるのだと思う。
偏愛者たちの語りには、発信というより記録のような静けさがある。 それは自分の中でひとつずつ形にしていく作業であり、 共感を誘うよりも、自分との対話を深める営みに近い。
推し活は「光を当てる」行為に見える。 偏愛は「凝視する」行為に近い。
その視線の違いが、熱の質を決定づけているように思う。
なぜ偏愛は、“推し活”として消費されやすいのか
とはいえ、偏愛と推し活はときに混同されやすい。
特にSNSの中では、「好き」が常に誰かに伝えられ、 拡散されることを前提として流通しているように見える。
なにかに熱を向けている人がいれば、 「あ、それって推し活だね」と言いたくなるのも自然な流れかもしれない。
けれど、偏愛の語りは、そうした回路にうまく乗らない。
偏愛は、“なぜそれを好きなのか”の説明が難しいことが多い。 そして、そのわかりにくさこそが、偏愛を偏愛たらしめているようにも思う。
にもかかわらず、SNSの構造は「伝わりやすさ」や「共感されやすさ」を前提としている。 その文脈に置かれると、偏愛の語りはときに誤読されてしまう。
「それって、つまりは推し活だよね?」
そのひと言に、違和感を覚える瞬間がある。
偏愛は、たしかに好きの一種ではある。 でも、それを「応援」や「共有」といった形式に当てはめようとしたとき、 大事ななにかがこぼれ落ちてしまうような気がする。
偏愛は、見せるためではなく、見続けるための視線。 だからこそ、「推し活っぽさ」に包まれてしまうと、 その静けさが伝わらなくなってしまうのかもしれない。
それでも、どちらも“好き”から始まっている
ここまで語ってきたように、推し活と偏愛は、熱の向け方がまったく違う。 けれど、どちらも「好き」という感情を出発点にしている。
推し活は、「届けたい」「広めたい」「支えたい」という、外向きの熱を持っている。 偏愛は、「見つめたい」「確かめたい」「そばにいたい」といった、内向きのまなざしを持っている。
光と根。 共鳴と独語。 広げることと、深めること。
どちらも、世界と関わろうとするかたちのひとつなのだと思う。
私たちがこのメディアで偏愛を取り上げ続けているのは、 「わかってもらう」ことを目的としない熱のあり方に、 いまの社会では見失われがちな強さを感じるからだ。
もちろん、こうも思われるかもしれない。 「偏愛は誰かに届けるためのものじゃないって言いながら、記事にして発信しているじゃないか」と。
たしかに、偏愛者たちの語りはときに公開される。 けれど、その語りは「伝える」ためというより、 むしろ「自分の中で確かめる」ために言葉にされているように感じる。
偏愛とは、自分でもまだうまくつかめていない感覚を、 語りながら、考えながら、見つめ続けていく行為なのかもしれない。
それをそっと共有しようとする姿勢の中には、 派手さでは測れない、静かな強度がある。
だからこそ、私たちは偏愛者たちの語りを、「推す」のではなく、 「記録」として丁寧に受け取り、手渡していきたいと思っている。
偏愛には、自分の世界を深める力がある。 そして他人の偏愛は、ときに自分の世界のピントを変えてくれる。
読むことで、自分の見方に少しだけ揺らぎが生まれる。 見えなかったものが、見えてくる。
この文章も、そんなきっかけのひとつになっていれば嬉しい。