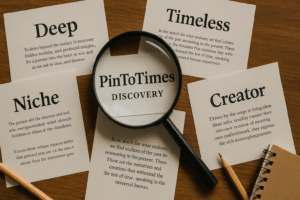偏愛が世界のピントを変える―PinTo Times編集長より

編集長 挨拶
私は、PinToTimesを運営する中で、多くの偏愛者と出会い、その語りや視点から大きな刺激と気づきを受けてきた。
その体験を編集長として記録し、PinToTimesという媒体を通じて届けていきたいと思う。
ここにあるのは、ある見方や感じ方を通して立ち上がった世界の断片。
読む人それぞれの解釈によって、新たな共鳴や発見が芽生えることを期待している。
編集長としてのピントを通して、その景色を映し直す。
私なりの解釈でしかないが、あなたの世界の見方が少しでもクリアになるなら嬉しい。
ここは、偏愛者それぞれの解釈ではなく、PinToTimesとしての解釈を示す場である。
偏愛者に出会って、世界の見え方が変わった
偏愛を銘打つメディアの編集長ではあるが、私は到底自分のことを偏愛者とは言えない。
もちろん「好きなもの」はあるが、それほどまでに細部にこだわり、考え続けてきた経験は少ない。
だからこそ、偏愛者に出会ったときの衝撃は大きかった。
対象への向き合い方が、自分とはまるで違っていたからだ。
ただ楽しむのではなく、問いを立て、考え、言葉にしていく。
その繰り返しが、独自の視点を形づくっていた。
どうやら偏愛は、ただの情熱に見えて、その奥には考え抜かれた視点の積み重ねがある。
好きである理由を追いかけていくうちに、自分自身を知ることにつながっていく。
共感してもらえるかもしれないが、他人の偏愛に触れるとき、ただ感心して終わるのではなく、自分の偏愛に照らして考えることがあるのではないだろうか。
「自分ならどうだろう」「もし同じ対象に出会ったら」と想像する。
その抽象化の心の動きは、他者を理解することと同時に、自分を深めることにもつながっている。
私自身もまた、そうした語りに触れることで、世界の輪郭が少しずつ変わっていった。
今まで見えなかった細部に意味を見いだし、考え方の幅が広がっていった。
“偏愛の偏愛者”という立場
偏愛者ではなかった私だが、偏愛という営みは強く自分の関心を惹きつけてきた。
だからこそ、これからは「偏愛の偏愛者」と名乗ってもいいのかもしれない。
自分のなかに突き抜けた偏愛があるわけではない。
けれど、偏愛を持つ人たちの姿勢や考え方に惹かれ、そこから多くを学んできた。
偏愛者ではなかった自分だからこそ、偏愛がどう見えるかを客観的に理解できる部分がある。
同時に、彼らの語りに触れることで、自分自身の世界の解像度が上がる体験もしてきた。
その両方の経験が、偏愛者とそうではない人のあいだをつなぐ視点を与えてくれている。
編集長としての立場は、その橋渡しにある。
そのまま届けるだけではなく、翻訳して読者に手渡すこと。
そういった役割もあると思っている。
PinToTimesが描くメディアの輪郭
偏愛は、「こだわり」や「熱量」といった言葉で語られることが多い。
けれど、ここで出会ってきた偏愛者の姿を見ていると、それだけでは収まりきらないと感じる。
どうやら偏愛は、ただの情熱に見えて、その奥には考え抜かれた視点の積み重ねがある。
好きである理由を追いかけていくうちに、自分自身を知ることにつながっていく。
PinToTimesでは、そんな偏愛を「流行」や「推し活」といった消費の言葉とは少し違う角度から取り上げたい。
なぜそれを好きなのか、その奥にある感覚や構造に触れてみたいと思っている。
そしてもう一つ大事にしたいのは、偏愛を語る人だけでなく、それを受け取る人の体験である。
人は他人の偏愛に出会ったとき、自然と自分の好きに照らして考えているのではないだろうか。
一見関係がないように見えても、「自分ならどうするだろう」と思い浮かべてしまう。
その心の動きから、新しい比較や理解が生まれていく。
こうしたやりとりの中に、PinToTimesの輪郭が浮かび上がる。
偏愛を語る人と、それを受け取る人の間に生まれる気づきの連鎖こそ、このメディアが描きたいものだ。
PinToTimesは、その変化をそっと後押しする場所でありたい。
“今”このメディアが必要な理由
最近の世の中では、目に見える数字が価値を決めてしまうことが多い。
再生回数やフォロワー数、売上。
大きさや速さといったものがわかりやすい評価軸になっている。
けれど、好きなものに向き合うときに大事にされている価値は、それだけではないはずだ。
考え続けること、問いを持ち続けること、時間をかけてじっくり向き合うこと。
そういう積み重ねの中にこそ、偏愛の魅力は宿っている。
さらに、偏愛は自分の世界だけに閉じない。
誰かの偏愛を目にしたとき、「自分ならどうだろう」と自然に考えてしまう。
違う視点を受け止めながら、自分の好きに照らし合わせていく。
その開かれた感覚こそが、偏愛の面白さでもある。
だからこそ、このメディアでは数字では測れないもの、誰かが大事にしてきた好きのかたちを見えるようにしていきたい。
PinToTimesは、そんな偏愛の魅力を共有する場でありたいと思っている。
読者へ ― 偏愛者へ、そしてまだ言葉にならない好きを抱える人へ
ここに書かれていることは、読む人それぞれに違ったかたちで響くと思う。
だからこそ、自分なりの共鳴や発見を見つけてもらえたら嬉しい。
まずは、好きを考え続けている人に読んでほしい。
他人の偏愛に触れることで、自分の見方を少し違う角度から捉え直せるはずだ。
そして、まだ言葉にならない好きを抱える人にとっても、ここが意味のある場であればいい。
他の人の語りが、その余白をそっと照らすきっかけになるかもしれない。
そうした気づきの積み重ねが、自分の世界の見え方を少し変えていく。
その変化こそ、PinToTimesが大切にしたい体験である。