「血液型占い」は日本人だけ?科学的根拠なき性格診断が“当たる”と感じる心理のウソとホント
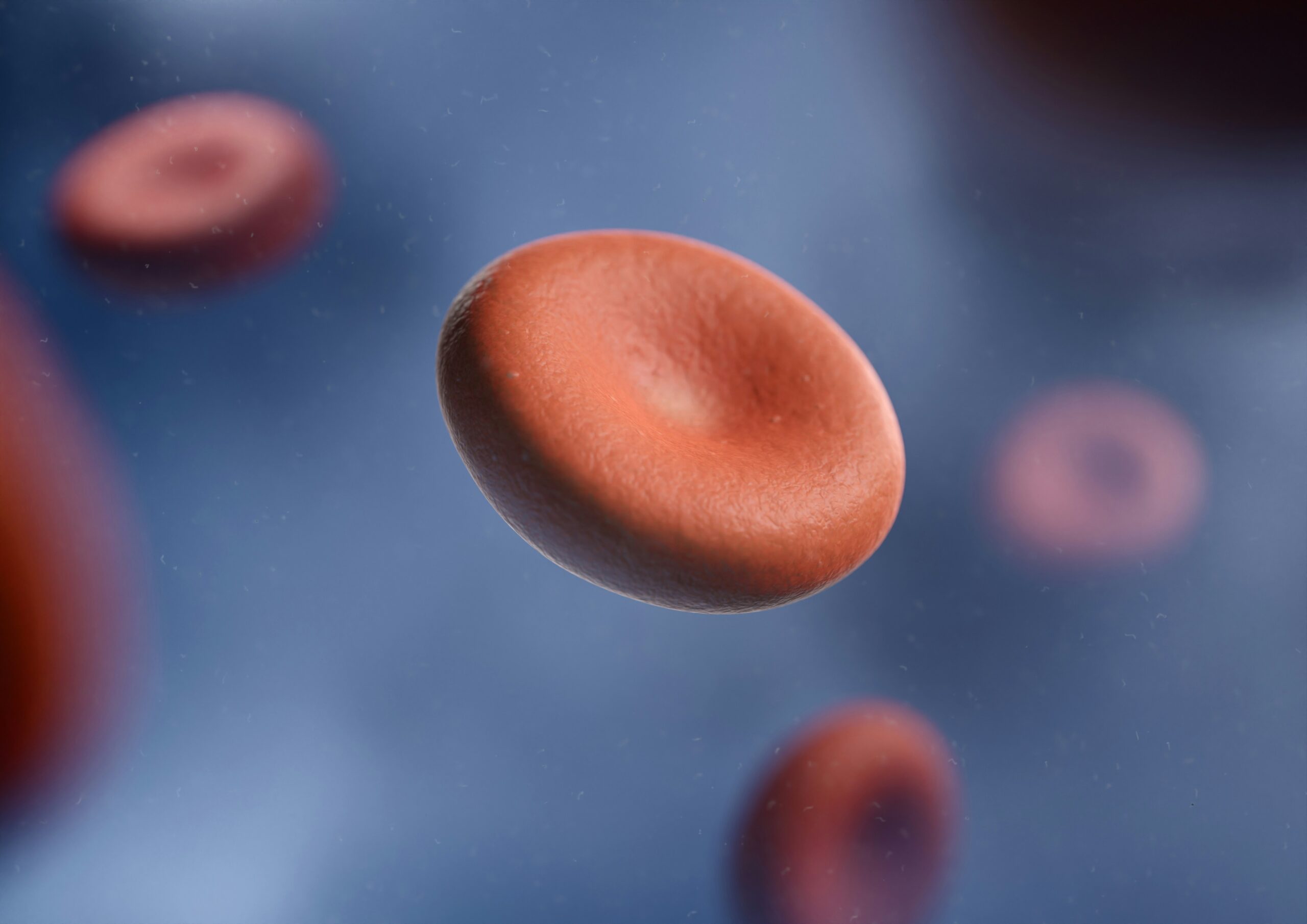
この記事でわかること
- 血液型性格診断のダークな誕生秘話 - 実は1930年代ドイツで人種差別の道具として生まれ、ナチスが「優れた民族」を証明するために利用していた衝撃の起源
- 日本軍が利用しようとした歴史 - 大日本帝国陸軍が兵士の適性判断に活用しようとし、その後科学的に完全否定された「第一次ブーム」の真相
- 一人の放送作家が起こした奇跡の復活劇 - 学問的に「死んだ」理論を、能見正比古が「相性」という切り口で国民的娯楽として蘇らせた1970年代の革命
- なぜ「当たる」と感じてしまうのか - バーナム効果、確証バイアス、予言の自己成就という3つの心理トリックが、私たちの脳を巧みに欺いている科学的理由
- 世界で見れば「非常識」な日本の特殊性 - 欧米では自分の血液型すら知らない人が多数派。なぜ日本だけがこの文化に魅了されたのか
- 血液型からMBTIへの進化 - Z世代が夢中になる新しい性格診断ツールが示す、「分類」から「自己探求」への時代の変化
初対面同士の飲み会での自己紹介。ひと通り話が終わった頃、誰かが決まって口にする質問があります。
「ちなみに、血液型は何型?」
この問いをきっかけに、「やっぱりA型は几帳面だよね」「O型はおおらかだから」といった会話が自然と弾んでいく。私たち日本人にとって、あまりにも見慣れた日常の一コマです。
しかし、この当たり前の習慣に、ふと不思議な感覚を覚えたことはないでしょうか。なぜ、科学技術が発達したこの国で、たった4つのカテゴリーがこれほどまでに人間関係に影響力を持っているのでしょう。そして、なぜこの会話がニューヨークのカフェで交わされたなら、きっと困惑した表情を浮かべられてしまうのでしょう。
この記事では、そんな日常に潜む「小さな謎」を解き明かします。血液型性格診断という、一見すると他愛ない文化の裏側に隠された、意外で、時には驚くべき歴史の旅に出かけましょう。その道のりは、20世紀初頭のドイツで生まれた科学理論から始まり、日本の軍事戦略を経て、戦後のテレビ番組が巻き起こした一大ブームへと続いていきます。
- 1. 血液型を知らない世界
- 1.1. 欧米における血液型:「医療情報」以上でも以下でもない
- 1.2. 東アジアへの影響:文化の震源地としての日本
- 1.3. なぜ日本でだけ根付いたのか
- 2. 人種差別から軍事戦略、そしてテレビの中へ
- 2.1. ドイツ優生思想という暗い源流(1910年代〜1930年代)
- 2.2. 日本での最初のブームと挫折(1920年代〜1930年代)
- 2.3. 能見正比古によるポップカルチャー革命(1970年代〜)
- 3. なぜ「当たる」と感じてしまうのか?
- 3.1. 科学的な最終結論:「関連性なし」
- 3.2. 信じてしまう心理のカラクリ
- 4. 血液型からMBTIへ〜変わらない「自分を知りたい」という願い〜
- 4.1. 新世代の性格診断ツールキット
- 4.2. シンプルな「分類」から、複雑な「探求」へ
- 5. 愛すべき「不正確な鏡」との付き合い方
- 5.1. 参考
血液型を知らない世界

この日本の「常識」が、世界的にはいかに「非常識」であるかを知るために、まずは海外に目を向けてみましょう。両者を比較することで、日本の特異な状況がより鮮明に浮かび上がってきます。
欧米における血液型:「医療情報」以上でも以下でもない
欧米の多くの国々では、血液型は純粋に医療情報として扱われています。輸血や献血、手術の経験がなければ、自分の血液型を知らない人が大半なのです。彼らにとって、血液型と性格を結びつけるという発想は、まるで星座占いで人生の重大な決断を下すのと同じくらい、奇妙なものに映ります。
実際に外国人にこの日本の習慣を伝えると、しばしば「世界に何十億人もいる人間を、たった4つの型で分類するなんて、あまりに単純すぎないか?」といった、もっともな反応が返ってきます。2011年には、ある日本の大臣が自身の失言を「B型だから」と弁明した際、海外メディアから「日本では血液型が性格に影響すると信じられているらしい」と報じられ、驚きをもって受け止められました。
東アジアへの影響:文化の震源地としての日本
一方で、お隣の韓国や台湾では、日本と同様に血液型と性格を結びつける文化が見られます。人気俳優のプロフィールに血液型が記載されたり、恋愛ドラマで血液型の相性がテーマになったりすることもあります。
しかし歴史を紐解けば、これらの地域における流行は、20世紀を通じて日本の大衆文化が強く影響を与えた結果であることが分かっています。つまり、この文化の震源地であり、主要な輸出国は、紛れもなく日本なのです。
なぜ日本でだけ根付いたのか
では、なぜ日本でだけ、これほどまでに血液型性格診断が根付いたのでしょうか。その背景には、日本の社会構造が深く関わっています。
欧米社会には、歴史的に人種、宗教、階級といった、人々を分類するための明確な指標が数多く存在しました。対照的に、比較的均質性の高い日本社会では、そうした内部的な分断線が少なかったのです。
そこに登場したのが、「血液型」という、一見すると科学的で中立的な分類法でした。それは、伝統的な身分や出身地とは異なる、近代的で誰もが参加できる新しい「自分語り」のツールとして、日本の土壌に驚くほどフィットしたのです。
人種差別から軍事戦略、そしてテレビの中へ

今日、私たちが楽しんでいる血液型占いのルーツを辿ると、その誕生にまつわる暗い歴史と、二度の大きなブームを経て大衆文化へと変貌を遂げた、劇的な進化のプロセスが見えてきます。
ドイツ優生思想という暗い源流(1910年代〜1930年代)
物語の始まりは、意外にも日本ではなく、20世紀初頭のドイツです。1900年にABO式血液型が発見されると、研究者たちは血液型の分布が人種によって異なることに気づきました。これがやがて優生思想と結びついていきます。
この流れを決定的にしたのが、ナチス・ドイツの台頭でした。彼らは自らの人種差別的なイデオロギーを正当化するため、この新しい「科学」に飛びつきました。1932年にドイツで出版された『血液型便覧』には、「ドイツ人に多い」A型を「高い知能」「勤勉」と賞賛する一方、「ユダヤ人やアジア人に多い」B型を「暴力犯罪者」などと劣った血液型として貶める記述が見られます。
血液型性格論は、その誕生の瞬間から、人種差別の道具として利用されるという暗い過去を背負っていたのです。
日本での最初のブームと挫折(1920年代〜1930年代)
この理論が日本に伝わると、教育学者の古川竹二が学問的に体系化しようと試みます。彼は1927年、日本心理学会の機関誌に『血液型による気質の研究』を発表しました。当初、この研究は新しい性格類型論として、学問的にも注目を集めます。
時を同じくして、大日本帝国陸軍もこの理論に強い関心を示し、血液型によって兵士の適性を判断し、より効率的な部隊編成に役立てようと考えました。
しかし、この最初のブームは長くは続きませんでした。法医学者の古畑種基をはじめとする科学者たちが厳密な検証を行った結果、血液型と気質の間に統計的な関連性は見出されず、その学問的妥当性は否定されます。1933年の日本法医学会総会での討論を境に、古川説は学界から姿を消し、軍での研究も中止されました。
科学の審判によって、血液型性格論は一度、完全に「死んだ」のです。
能見正比古によるポップカルチャー革命(1970年代〜)
学問の世界から忘れ去られ、約30年の時が流れた後、この死んだはずの理論を華麗に蘇らせた人物が現れました。科学者ではなく、一人の放送作家、能見正比古です。彼が1971年に出版した『血液型でわかる相性』は、ミリオンセラーとなり、第二次血液型ブームを巻き起こしました。
能見の功績は、巧みな「リブランディング」にありました。彼は、古川が用いた「気質」という硬直的で学術的な言葉を、より身近で分かりやすい「性格」という言葉に置き換えました。そして何より画期的だったのは、個人の優劣ではなく、人と人との関係性を読み解く「相性」という新しい切り口を導入したことです。
これは、高度経済成長を経て、恋愛や人間関係への関心が高まっていた世相に見事にマッチしました。能見は、優生思想に由来する「どちらが優れているか」という垂直的な序列の物語を、「それぞれに違いがあり、どう組み合わせるかが重要だ」という水平的な関係性の物語へと書き換えたのです。
この進化によって、血液型性格論は科学的な反証が難しい、主観的な解釈の余地が大きいポップカルチャーへと変貌を遂げました。それは、科学としての死を乗り越え、大衆文化として永遠の命を得た瞬間だったのかもしれません。
なぜ「当たる」と感じてしまうのか?

歴史を紐解くと、血液型性格診断が科学的に否定された過去を持つことが分かります。では、なぜ今なお、私たちの多くが「意外と当たる」と感じてしまうのでしょうか。その答えは、血液型そのものではなく、私たちの脳が持つ、巧妙で普遍的な「思考のクセ」に隠されています。
科学的な最終結論:「関連性なし」
まず、現代科学の結論を明確にしておきましょう。日本心理学会をはじめとする多くの専門機関が、大規模な統計調査を繰り返し行った結果、「血液型と性格の間に科学的に意味のある関連性は認められない」と結論づけています。性格は、血液型を決定する遺伝子とは別の、無数の遺伝的要因と、生まれ育った環境が複雑に絡み合って形成される、というのが現代科学の常識です。
信じてしまう心理のカラクリ
科学的には「無関係」であるにもかかわらず、私たちが「当たる」と感じてしまうのは、主に3つの心理効果が働いているためです。
1. バーナム効果(誰にでも当てはまるマジック)
これは、占いの基本ともいえる心理効果です。例えば、「A型のあなたは、基本的には真面目で周りに気を遣うタイプですが、親しい人の前では意外と頑固な一面を見せることがありますね」と言われたとします。多くのA型の人は「当たっている」と感じるでしょう。
しかし、この記述は非常に曖昧で、誰にでも多かれ少なかれ当てはまる内容です。真面目な人でも頑固な瞬間はありますし、その逆もまた然りです。このように、誰にでも当てはまる一般的な記述を、まるで自分だけに向けられた的確な分析だと錯覚してしまう現象がバーナム効果です。
2. 確証バイアス(見たいものだけを見るメガネ)
一度「B型はマイペースで時間にルーズだ」という思い込みを持つと、私たちの脳は無意識のうちに、その仮説を裏付ける情報ばかりを探し始めます。B型の友人が約束に遅れてくれば「やっぱりB型だから」と納得し、その記憶は強く残ります。逆に、その友人が時間通りに来たとしても、「今日は珍しいな」と例外として処理し、すぐに忘れてしまうのです。
このように、自分の信じたい仮説を肯定する情報ばかりに目を向け、反証となる情報を無視したり軽視したりする心の働きが確証バイアスです。
3. 予言の自己成就(言われた通りになる予言)
周りから繰り返し「O型だから、リーダーシップがあるね」と言われ続けると、その人は無意識のうちに「O型らしく」振る舞おうとし、実際に集団の中でリーダー的な役割を担うようになることがあります。これは、根拠のないレッテル(予言)が、人々の行動に影響を与え、結果的にその予言通りの現実を作り出してしまう現象です。
特に、協調性を重んじる日本社会では、周囲からの期待に応えようとする圧力が働きやすく、この効果が顕著に現れると考えられます。
結局のところ、血液型性格診断が「当たる」と感じるのは、私たちの知性が低いからではありません。むしろ、私たちの脳が持つ、パターンを見つけて効率的に世界を理解しようとする、極めて人間的な性質を巧みに利用しているからなのです。
血液型からMBTIへ〜変わらない「自分を知りたい」という願い〜

血液型性格診断の物語は、それ自体で完結するものではありません。それは、「自分とは何者か」「他者とどう関わればよいか」という、時代を超えた人間の普遍的な問いかけの、一つの表現方法に過ぎないのです。
新世代の性格診断ツールキット
特にZ世代を中心に人気を集めているのが「MBTI(16Personalities)」です。これは心理学者ユングの理論をベースに、個人の思考や行動のパターンを4つの指標で分析し、16のタイプに分類するもので、自己分析やキャリアプランニングの文脈で広く活用されています。
また、ビジネスの世界では「エニアグラム」も注目されています。これは人間の性格を9つの基本的なタイプに分類し、それぞれの動機や恐れ、成長の方向性などを探るツールで、チームビルディングやリーダーシップ開発などで導入されています。
シンプルな「分類」から、複雑な「探求」へ
血液型診断の魅力は、そのシンプルさと、コミュニケーションツールとしての手軽さにありました。一方でMBTIやエニアグラムは、より複雑で内省的です。それは、単に相手を「分類」して終わりにするのではなく、自分自身の内面を深く「探求」し、成長へと繋げることを目的としています。
この変化は、社会が求める人間の在り方が、「集団の中での調和」から「個としての自己実現」へとシフトしていることの表れと言えるかもしれません。血液型がグループでの円滑な関係性を築くためのツールだったとすれば、MBTIは個人が自分らしい人生を航海するための羅針盤なのです。
愛すべき「不正確な鏡」との付き合い方
人種差別の道具として生まれ、学問的に否定され、軍事利用の夢も破れ、しかし一人の放送作家の手によって国民的娯楽として蘇った。血液型性格診断が歩んできた、数奇な運命を私たちは旅してきました。
その旅を通じて見えてきたのは、この診断が科学的な「ウソ」であると同時に、私たちの社会や心理に根差した、無視できない「ホント」を映し出しているという事実です。科学的な根拠はありません。しかし、それがコミュニケーションのきっかけとなり、人間関係の潤滑油として機能してきたこともまた、紛れもない事実なのです。
この記事は、血液型診断を頭ごなしに否定するためのものではありません。むしろ、その不完全さや歴史的な背景を丸ごと受け入れた上で、このユニークな文化をより深く、そして愛おしく見つめるためのものです。
本当に面白い問いは、「血液型診断は当たるのか?」ではありませんでした。「なぜ私たちは、この不正確な鏡をこれほどまでに必要とし、楽しんできたのか?」という問いこそが、私たちの社会や人間そのものについての豊かな洞察を与えてくれるのです。
次に誰かがあなたに「血液型は何型ですか?」と尋ねたとき、あなたは心の中で、この壮大な物語を思い出しながら、微笑むことができるでしょう。そして、これまでと同じように自分の血液型を答え、会話を楽しみながらも、この不完全で、それゆえに人間らしい文化の営みを、少しだけ温かい目で見守ることができるはずです。
手品のタネを知っていても、マジシャンの巧みな手さばきに感嘆するように。その歴史と心理的なカラクリを知ることで、私たちの日常は、ほんの少しだけ面白く、そして愛おしいものになるのですから。
【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】
PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?
参考
- 血液型占いって日本だけなの?日本と海外の性格診断文化の違いを比べてみた - Wings英会話
- 相手を分かった気になって安心したいだけ? 世界中で日本人だけが“血液型”にこだわる理由
- 血液型と性格|なんばくろとびハートクリニック|大阪市 中央区(心斎橋・難波・西区)循環器内科 糖尿病内科 内分泌内科 不整脈 動悸 高血圧
- ニセ科学についてのすばらしいレジュメと「血液型性格診断」の害 - オルタナティブ・ブログ
- 血液型性格判断の概観 - 北翔大学学術リポジトリ
- 血渡型性格類型的と性格検査との関係について - 城西大学
- 【第4回】オレとオマエはA型同士!?~血液型性格分類の信ぴょう性 - 日立システムズ
- 血液型と性格 - ~疑似科学/ニセ科学の典型例の一つとして
- 血液型と性格は実際に関係あるのか?日本独自の文化から科学的根拠と相性診断まで総まとめ
- バーナム効果とは?【効果をわかりやすく】具体例、活用方法 - カオナビ人事用語集
- 〈気になる心理学〉バーナム効果とは 占いはなぜ当たる? 二面性の提示で「必ず当たる」ようにできている | 特選街web
- 【具体例あり】確証バイアスとは?発生原因から弊害、対策を解説 - ミイダス
- 確証バイアスとは?あなたの判断を狂わせる「見たいものしか見ない」心理の罠
- 若者が飛びつく性格診断「MBTI」とは?血液型診断にとって代わる魅惑の“あるある感”
- 今流行りのMBTI診断とは?? - FRANK'S飯田橋店
- Z世代で流行っている性格診断テストとは?本来のMBTI®とは別物!?流行の理由や16Personalities性格診断テストについて解説!
- エニアグラムとは?性格診断をタイ プ別に解説、ビジネスへの応用や導入企業の事例
- エニアグラムとは? 9つの性格タイプや診断を行うことで得られるメリット - PeopleWork
- 【人間関係改善】話題のエニアグラムって何?会社員が実際に職場で活用してみた!






