「読書の秋」は誰が言い出した? スポーツ、食欲、芸術との意外な違いを徹底解説

秋風が心地よくなると、私たちの心にふと浮かぶ「〇〇の秋」という言葉たち。「食欲の秋」に胸を躍らせ、「スポーツの秋」に汗を流し、「芸術の秋」に心を澄ませ、そして「読書の秋」に夜長を楽しむ。まるで秋がいくつもの顔を持つ俳優のように、様々なペルソナを演じ分けているかのようです。
実際のところ、「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」は、人々が思い浮かべる「秋」の代名詞として常に上位を占めています。これに「芸術の秋」を加えた「秋の四天王」は、もはや日本の秋の風物詩と言っても過言ではないでしょう。
しかし、これらの言葉、実はそれぞれ全く異なる「生まれ」と「育ち」を持っていることをご存知でしたか?この記事では、それぞれの「秋」が持つユニークな物語を紐解き、なぜ私たちがこれほどまでに秋を多面的に楽しむのか、その秘密に迫ります。
- 1. インテリな長男?「読書の秋」の意外な家系図
- 1.1. 始まりは、父から息子へのアドバイス
- 1.2. 文豪・夏目漱石による「いいね!」
- 1.3. 国家プロジェクトとしての「読書」
- 2. 近代生まれの弟たち? スポーツの秋と芸術の秋
- 2.1. 「スポーツの秋」は、オリンピックがくれたプレゼント
- 2.2. 「芸術の秋」はアートと気候の素敵な関係から生まれた
- 3. 抗えない本能。「食欲の秋」を動かす見えざる力
- 3.1. 大地の恵みと、私たちのDNA
- 3.2. 身体が「食べなさい」と命じるワケ
- 4. 比べてみると面白い!秋の四兄弟、それぞれのプロフィール
- 4.1. あなたにとっての「今年の秋」は?
- 4.2. 参考
インテリな長男?「読書の秋」の意外な家系図
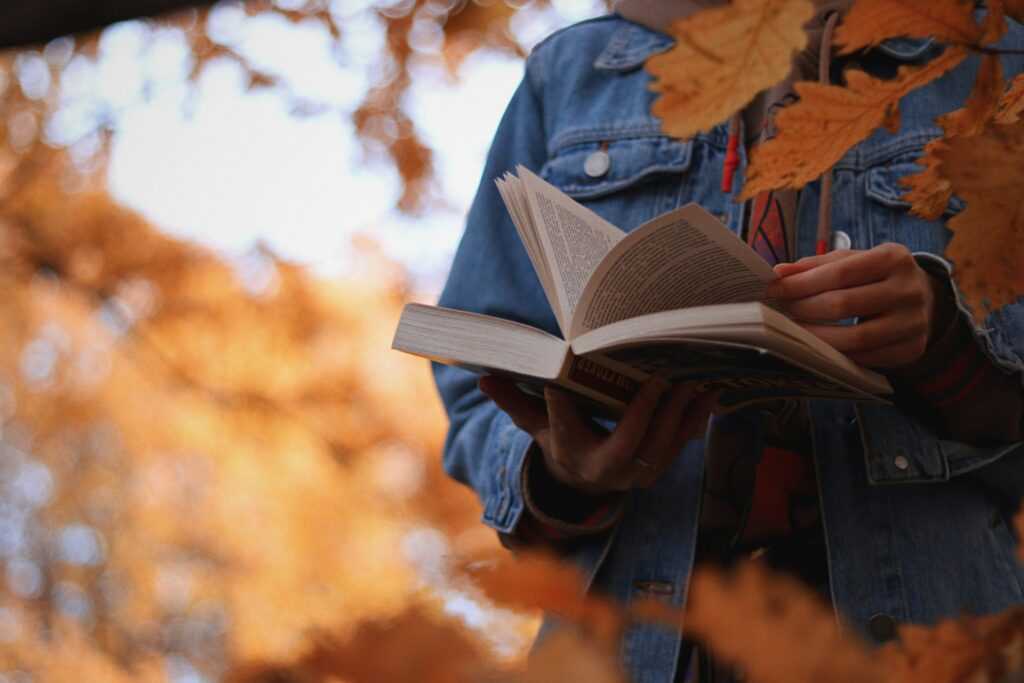
数ある「〇〇の秋」の中でも、ひときわ知的で落ち着いた雰囲気を放つ「読書の秋」。そのルーツは、驚くほど古く、そして壮大な物語を持っていました。
始まりは、父から息子へのアドバイス
物語は8世紀の中国、唐の時代にまで遡ります。高名な詩人であった韓愈(かんゆ)が、息子の学問を励ますために詠んだ詩が、すべての始まりでした。
その詩には「燈火稍可親(とうかようやくしたしむべく)」という一節があります。これは、「秋の夜は涼しくて過ごしやすいから、灯りの下で本を読むのにぴったりだよ」という、なんとも心温まるメッセージ。夏の暑さが和らぎ、静かで長い夜が訪れる秋こそ、知の探求に最適な季節だというわけです。
面白いのは、この概念が民衆の言い伝えではなく、一人の父親の愛情のこもった、そして少しばかり教育的な助言から生まれたという点です。この出自が、「読書の秋」に知的で内省的なイメージを与えているのかもしれません。
文豪・夏目漱石による「いいね!」
この古代中国のフレーズが、近代日本の私たちに届くきっかけを作ったのが、かの文豪・夏目漱石です。1908年(明治41年)に発表された小説『三四郎』の中で、登場人物がこの「燈火親しむべし」という言葉を少し気取って使ってみせるシーンがあります。
そのうち与次郎の尻が次第に落ち付いて来て、燈火親しむべしなどといふ漢語さへ借用して嬉しがる様になった。
漱石がこの言葉を取り上げたことで、難解な漢詩の一節は一躍、明治の読者にとって「粋」で「教養ある」表現として広まりました。文豪による「いいね!」が、この言葉に文化的なお墨付きを与えたのです。
国家プロジェクトとしての「読書」
そして、この流れを決定的なものにしたのが、1947年(昭和22年)に始まった「読書週間」です。終戦直後の日本で、「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」というスローガンのもと、出版社や書店、図書館などが一丸となってこの運動を始めました。
父から子への個人的なアドバイスが、文豪によって磨かれ、ついには国家再建のシンボルになる。そう考えると、「読書の秋」という言葉が持つ、どこか背筋が伸びるような雰囲気にも納得がいくのではないでしょうか。
近代生まれの弟たち? スポーツの秋と芸術の秋

「読書の秋」が持つ千年単位の歴史とは対照的に、「スポーツの秋」や「芸術の秋」は、もっと現代的で華やかなきっかけから生まれています。
「スポーツの秋」は、オリンピックがくれたプレゼント
「スポーツの秋」の誕生日は、非常に明確です。それは、1964年の東京オリンピック。夏の酷暑を避けるため、この大会は10月に開催され、その開会式が行われた10月10日は、後に「体育の日」(現在の「スポーツの日」)という国民の祝日になりました。
この国民的イベントをきっかけに、秋に運動会が開催される学校が増え、「スポーツの秋」という言葉は一気に定着しました。気象データを見ても、東京の10月はアスリートが最高のパフォーマンスを発揮するのに理想的な気候だったといいます。古代の詩から生まれた「読書の秋」とは対照的に、「スポーツの秋」は、いわばテレビ時代のスーパースター。公的で、祝祭的で、みんなで体を動かす楽しさを象徴しています。
「芸術の秋」はアートと気候の素敵な関係から生まれた
一方、「芸術の秋」は、もう少し実用的な理由から生まれました。この言葉が広まったのは、1918年(大正7年)に雑誌『新潮』で「美術の秋」という表現が使われたのがきっかけとされています。
その背景には、秋の穏やかな気候があります。実は、絵画や楽器といった繊細な芸術作品は、夏の湿気や冬の乾燥、急激な温度変化が苦手。カビが生えたり、調律が狂ったりする原因になるのです。その点、気温も湿度も安定している秋は、貴重な作品を展示・輸送するのにまさに完璧な季節。
このため、日展(日本美術展覧会)のような権威ある展覧会が秋に集中して開催されるようになり、「芸術の秋」のイメージが定着しました。アート作品そのものの「過ごしやすさ」が、私たちが芸術を楽しむきっかけになっていたとは、なんとも面白い話ですよね。
抗えない本能。「食欲の秋」を動かす見えざる力

さて、四天王の中でも最もパワフルで、私たちの本能に直接訴えかけてくるのが「食欲の秋」です。この抗いがたい魅力の裏には、文化的な理由だけでなく、科学的な根拠もしっかりと存在していました。
大地の恵みと、私たちのDNA
まず、何と言っても秋は「実りの秋」。新米、さつまいも、きのこ、サンマ、柿、梨…と、旬を迎える美味しい食材が目白押しです。昔は今のように一年中どんな食材でも手に入るわけではなかったので、収穫の季節である秋は、ごちそうが並ぶお祭りのような時期だったのです。
身体が「食べなさい」と命じるワケ
さらに、私たちの身体も、秋になると自然と食欲が増すようにできています。
- 冬ごもりの本能:動物たちが冬眠に備えて栄養を蓄えるように、私たち人間にも、寒い冬を乗り越えるために脂肪を蓄えようとする本能が備わっています。気温が下がると体温を維持するために基礎代謝が上がるため、より多くのエネルギー(=食べ物)が必要になるのです。
- 夏バテからの復活:夏の暑さで落ちていた食欲が、涼しくなると一気に回復します。その反動で、いつもより食欲旺盛に感じられることも多いようです。
- 幸せホルモンのいたずら:「セロトニン」という脳内物質には、気分を安定させ、食欲を抑える働きがあります。このセロトニンは日光を浴びることで作られるため、日照時間が短くなる秋には分泌量が減少気味に。すると、脳がエネルギーや幸福感を補おうとして、無性に炭水化物などが食べたくなることがあるのです。
読書やスポーツが私たちの「選択」であるのに対し、「食欲の秋」は、身体からの抗いがたい「命令」に近いのかもしれません。そう考えると、秋の味覚にどうしても勝てないのも、仕方ないことだと思えませんか?
比べてみると面白い!秋の四兄弟、それぞれのプロフィール
ここまで見てきたように、同じ「秋」の仲間でも、その個性は実に様々。ここで一度、彼らのプロフィールを比較してみましょう。
| 特徴 | 読書の秋 | スポーツの秋 | 食欲の秋 | 芸術の秋 |
| 生まれ | 文学的・古代:8世紀の中国の詩 | イベント主導・近代:1964年の国家的イベント | 生物学的・周期的:原初的本能と収穫サイクル | 実用的・文化的:実用的必要性と20世紀のメディア動向 |
| 性格 | 内向的・孤独 | 外向的・集団的 | 不随意的・原初的 | 観照的・企画的 |
| 動機 | 知的探求・自己啓発 | 国民の健康・一体感 | 生存本能・美食の快楽 | 美的鑑賞・作品保護 |
| 科学的根拠 | 集中力アップ:約22℃は脳の活動に最適 | 運動に最適:熱中症などのリスクが低い | 本能の目覚め:セロトニン減少や代謝上昇が食欲を刺激 | 作品に優しい:安定した温湿度が作品の劣化を防ぐ |
あなたにとっての「今年の秋」は?
「読書の秋」から「食欲の秋」まで、それぞれの「〇〇の秋」は、単なる慣用句ではなく、日本の文化や歴史、そして私たちの身体のリズムと深く結びついた、ユニークな物語の案内人でした。
最近では「睡眠の秋」や「旅行の秋」など、新しい「秋」も生まれているようです。結局のところ、「〇〇の秋」とは、短い季節を自分らしく最大限に楽しむための、日本人ならではの素敵な「言葉のフレームワーク」として、今も私たちの暮らしの中で生き続けているのです。
【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】
PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?
参考
- 『 の秋』… 皆さんはどの秋がお好き? | エンジニア派遣、製造業アウトソーシングのDPT
- 「〇〇の秋」なぜ秋だけ? 今さら聞けないことを内緒でチェック! - ASOPPA
- 「〇〇の秋」といえば思いつくものランキング! 大学生に聞いてみた - マイナビ学生の窓口
- 【秋と言えば?】食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋…6割以上が新たなことに挑戦しやすい季節!どう過ごす? - ヤマワケJOURNAL - WeCapital
- 「秋といえば…」連想するものランキング!この秋どう過ごす?スポーツの秋、芸術の秋 - Kufura
- なぜ読書は秋なの?由来やおすすめジャンルから楽しむコツまで徹底解説 - アルマ・クリエイション
- 「読書の秋」その由来と楽しみ方 | 日本の良品を届ける鴻月【公式サイト】
- 「読書の秋」と「三四郎」 - ほんだらけ
- 2012/07/24(火)安東省菴書「韓愈符読書城南詩横巻」 - 筆記~書の虎の巻
- なんで「読書の秋」なの?その由来にせまる! - ブックオフオンラインコラム
- 秋といえば読書! でも、どうして「読書の秋」なの? - ウェザーニュース
- 灯火親しむべしとは? 意味・原文・書き下し文・注釈 - Web漢文大系
- スポーツ、読書、食欲・・・「~~の秋」といわれる由来 - Manegy
- 新しいウィンドウで開くukai-dc.net「灯火親しむべし」 - うかい歯科
- 秋の夜長に…|WEBコラム|商品案内|杉田エース株式会社
- 読書週間(10月27日から11月9日):本との新しい出会いを楽しむチャンス! - ユー・エス・エス / 上田写真製版所
- 10月27日から始まる「読書週間」、そもそもなぜ始まったのか? - @DIME アットダイム
- 読書推進・図書普及 - 一般社団法人 日本書籍出版協会
- 「読書週間」とは何?いつ?由来や2024年の読書週間、心に残る標語などさくっと解説!【大人の語彙力強化塾714】 | Precious.jp(プレシャス)
- スポーツの秋 - 布亀株式会社
- 秋といえば何の秋?食欲の秋?睡眠の秋?由来を調べてみよう! - なるほど!BUNRI
- 1964年の東京五輪は涼しかった! - nippon.com
- なぜ「芸術の秋」と呼ばれるのか?|ギャラリーダブルエイト|愛知県安城市 - DOUBLE EIGHT
- 芸術の秋|暦とならわし|暦生活 | 日本の季節を楽しむ暮らし
- 音楽会や美術展が秋に多い理由とは? - ウェザーニュース
- スポーツ、読書など「〇〇の秋」と言われる由来は? みんなの秋の楽しみも調査! - Oggi
- 高齢者の集中力維持に最適な室温はどれくらい? - ケアネット
- なぜ「食欲の秋」というのでしょうか? - 京都のお弁当屋さん 2nd Kitchen
- 食欲の秋の由来や起源とは?なぜ食べ物が食べたくなるのか理由を解説 - ドラッグセイムス
- なぜ秋は食欲が増すの?「食欲の秋」の由来|『タツミ訪問看護』採用サイト - メディプラス
- 食欲の秋に食欲が増す理由!その由来や秋に食べたい食べ物、食べすぎの対策もご紹介 - 鰹節
- 冬になると気分が落ち込む「冬季うつ」治し方や予防策について説明!
- 【完全ガイド】12月病の原因・症状・対策・予防法|年末の心身の不調を乗り切る | メンクリ
- 生産性をあげるには温度と湿度が重要! 学校での授業をより効果的にするには - DAIKEN






