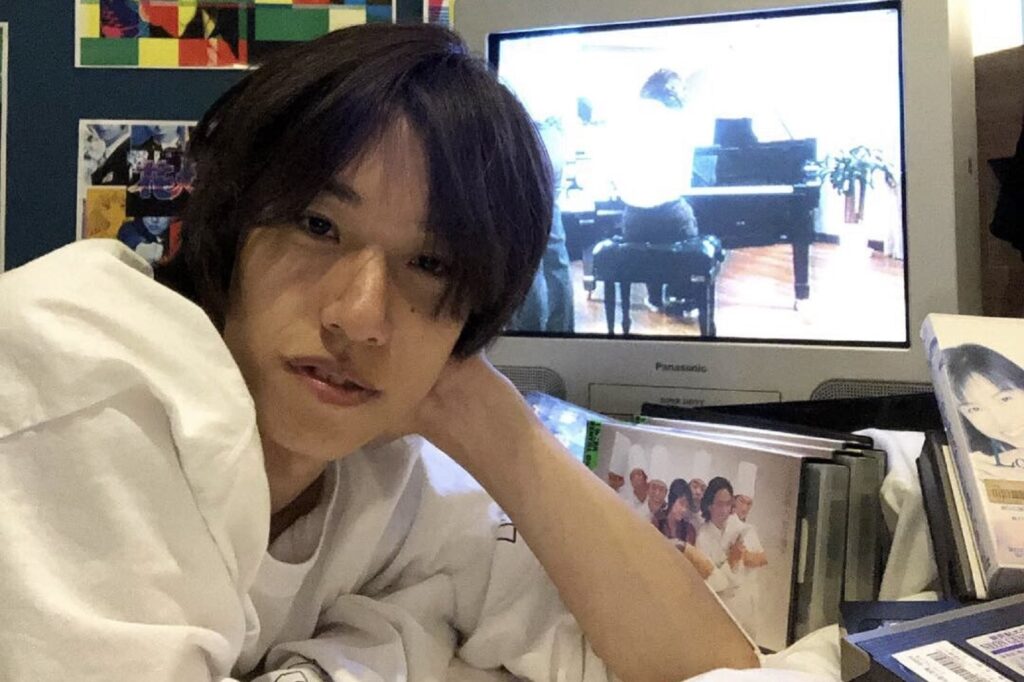「オワコン」とは誰が決めるのか? 流行の仕掛け人と、愛されるコンテンツの境界線

ふと、見慣れたはずの街角に、ぽっかりと空いた空間があることに気づきます。ほんの数年前まで、そこには信じられないほどの行列ができていました。色とりどりのドリンクを片手に、誰もが笑顔で写真を撮っていた、あのタピオカドリンク店の跡地です。
あの熱狂は、一体どこへ消えてしまったのでしょうか?
私たちの周りでは、彗星のように現れては消えていく流行が絶え間なく繰り返されています。そして、ブームが去ったものに対して、私たちは時として少し冷ややかな響きを持つ、ある言葉を口にします。
「あれはもう『オワコン』だよね」
「オワコン」とは、「終わったコンテンツ」を略したインターネットスラングです 1。かつては絶大な人気を誇ったにもかかわらず、今ではすっかり時代遅れになってしまったモノやコト、あるいは人に対して使われる言葉。それはまるで、流行という法廷で下される「有罪判決」のようです。
しかし、ここで一つの素朴な疑問が浮かび上がります。その「オワコン」という烙印は、一体、誰が押しているのでしょうか? 特定の評論家でしょうか。メディアによる宣言でしょうか。それとも、もっと目に見えない、大きな力の働きによるものなのでしょうか。
この記事では、日常に溢れる流行の誕生から終焉までを解剖し、その裏側で作用している社会のメカニズムや人々の心理を解き明かすことで、目まぐるしく移り変わる世界が、ほんの少しだけ面白く、そして愛おしく見えてくる。そんな探求の旅へと、皆様をご案内します。
- 1. 二つのスイーツが語る物語――マリトッツォとタピオカ、それぞれの終着駅
- 1.1. マリトッツォ:時代が生んだ、儚いシンデレラ
- 1.2. タピオカ:ブームの終焉と「定番化」への分かれ道
- 2. 流行の解剖学――「烙印」を押す見えざる手
- 2.1. 最初の審判者たち「アーリーアダプター」という名の仕掛け人
- 2.2. メディアとインフルエンサーが作る「バンドワゴン効果」
- 2.3. 「キャズム」と「幻滅期」という境界線
- 2.4. 最後の審判〜大衆心理と「スノッブ効果」〜
- 3. 不死身のコンテンツたち――なぜ彼らは「オワコン」にならないのか
- 3.1. 「商品」ではなく「世界」を売る戦略
- 3.2. 絶え間ない進化と「変わらない安心感」の両立
- 4. ラザロ効果――「オワコン」が「エモい」に変わる時
- 4.1. テクノロジーが可能にした、世代を超える対話
- 4.2. 奇跡の復活劇〜ファイナルファンタジーXIVの教訓〜
- 5. 「オワコン」とは心の軌跡である
- 5.1. 参考
二つのスイーツが語る物語――マリトッツォとタピオカ、それぞれの終着駅

「オワコン」と一括りにされがちな過ぎ去ったブームですが、その終わり方には驚くほど多様な姿があります。その違いを鮮やかに浮かび上がらせるために、私たちの記憶に新しい二つのスイーツ、「マリトッツォ」と「タピオカ」の物語を比較してみましょう。
マリトッツォ:時代が生んだ、儚いシンデレラ
2021年頃、スイーツ界に突如として現れたシンデレラ、それがマリトッツォでした。丸いブリオッシュ生地に、これでもかと生クリームを挟んだその姿は、見るからに魅力的。コロナ禍という特殊な時代背景が、その人気を後押ししました。崩れにくくテイクアウトに向いている形状は外出自粛の時流に乗り、その「映える」見た目はSNS上で瞬く間に拡散されたのです。
しかし、その輝きは長くは続きませんでした。2023年には、多くの店が販売を取りやめています。マリトッツォの成功要因であった「シンプルさ」は、同時にその寿命を縮める要因にもなりました。それはあくまで「一度は食べてみたい」という好奇心を刺激する単一の体験であり、その先に広がる奥深い「世界観」や多様な楽しみ方を提供するまでには至らなかったのです。一度魔法が解ければ、シンデレラは元の姿に戻らざるを得ませんでした。
タピオカ:ブームの終焉と「定番化」への分かれ道
一方、2018年から2019年にかけて日本中を席巻した第3次タピオカブームは、より複雑な様相を呈していました。ブームの終焉は、専門店が乱立したことによる希少性の低下、模倣店の増加、そしてコロナ禍による客足の減少などが複合的に絡み合った結果でした。街からは多くのタピオカ店が姿を消し、まさに「オワコン」の典型例に見えました。
しかし、ここで興味深い現象が起こります。ブームの牽引役であった「ゴンチャ(貢茶)」のような一部のブランドは、ブームが去った後も成長を続けているのです。彼らはなぜ生き残れたのでしょうか。その答えは、巧みな戦略転換にあります。彼らは自らを単なる「タピオカドリンク店」から、高品質な台湾ティーを軸にした「スペシャルティ ティーストア」へと再定義しました。タピオカ以外のドリンクメニューを充実させ、若者だけでなくファミリー層など、より幅広い顧客層にアプローチすることで、一過性のブームに依存しない安定したビジネスモデルを築き上げたのです。
マリトッツォがほぼ完全に市場から姿を消したのに対し、タピオカはブームに乗っただけの小規模店が淘汰され、戦略を持ったプレイヤーが「定番」として生き残るという市場の再編が起きました。この二つの事例は、「オワコン」という言葉が、完全な消滅だけでなく、市場の成熟と変態という異なる結末をも内包していることを示唆しています。それは単一の終着駅ではなく、様々な行き先を持つ分岐点なのです。
流行の解剖学――「烙印」を押す見えざる手
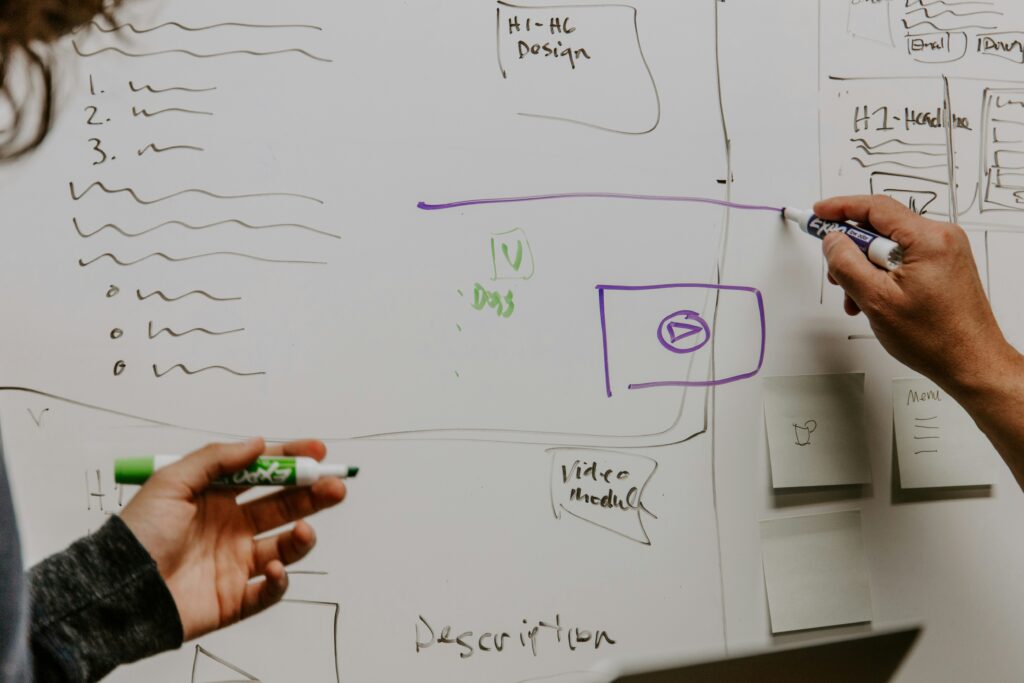
では、コンテンツが「流行」から「オワコン」へと至るプロセスには、どのような力が働いているのでしょうか。そのメカニズムを解き明かすため、社会学やマーケティング理論の観点から、流行の解剖を試みてみましょう。
最初の審判者たち「アーリーアダプター」という名の仕掛け人
新しい商品やサービスが世に出たとき、誰もがすぐに飛びつくわけではありません。社会学者のエベレット・M・ロジャースが提唱した「イノベーター理論」によれば、人々は新しいものを採用する速度によって5つのタイプに分類されます。
- イノベーター(革新者): 市場全体の約2.5%。リスクを恐れず、最も早く新しいものを試す冒険者。
- アーリーアダプター(初期採用者): 市場全体の約13.5%。流行に敏感で、自らの判断で新しいものを取り入れ、周囲に大きな影響を与えるオピニオンリーダー。
- アーリーマジョリティ(前期追随者): 市場全体の約34%。新しいものには比較的慎重だが、アーリーアダプターの動向を見てから採用を決める。
- レイトマジョリティ(後期追随者): 市場全体の約34%。周囲の大多数が採用しているのを確認してから採用する懐疑的な層。
- ラガード(遅滞者): 市場全体の約16%。最も保守的で、変化を嫌う層。
この中で、流行の火付け役として極めて重要な役割を果たすのが、アーリーアダプターです 16。彼らは単なる新しもの好き(イノベーター)とは異なり、その商品やサービスが持つ「価値」を見極める鋭い嗅覚を持っています。彼らが「これは面白い」「これは価値がある」と判断し、採用することこそが、流行が生まれるための最初の、そして最も重要な関門なのです。
メディアとインフルエンサーが作る「バンドワゴン効果」
アーリーアダプターによってその価値が見出されたコンテンツは、次に増幅のフェーズへと移行します。ここで強力なエンジンとなるのが、メディアとインフルエンサーの存在です。
彼らの発信は、「バンドワゴン効果」と呼ばれる社会心理学的な現象を引き起こします。これは、「多くの人が支持しているものには、さらに多くの支持が集まる」という効果です。行列のできているラーメン店に、つい並びたくなってしまう心理と同じです。
インフルエンサーによる「このコスメ、最高!」という投稿や、テレビ番組での「今、若者の間で大流行!」といった特集は、「みんなが注目しているなら、自分も乗り遅れたくない」という大衆心理を刺激します。こうして、一部の層で始まった小さな火種は、メディアとSNSという増幅装置を通じて、社会全体を巻き込む大きな炎へと燃え広がっていくのです。
「キャズム」と「幻滅期」という境界線
しかし、多くの流行は、このまま順調に社会全体へ広がるわけではありません。そこには、二つの大きな「淘汰のフィルター」が存在します。
一つ目は、「キャズム」と呼ばれる深い溝です。これは、アーリーアダプターと、その次に続くアーリーマジョリティとの間に横たわる断絶を指します。両者の価値観は根本的に異なります。アーリーアダプターが「革新性」や「新しさ」を求めるのに対し、アーリーマジョリティは「安心感」や「実用性」「信頼できる実績」を重視するのです。この価値観の溝を埋める橋を架けられなかった製品やサービスは、初期の熱狂だけで終わり、メインストリーム市場に浸透することなく消えていきます。
二つ目は、IT調査会社ガートナーが提唱する「ハイプ・サイクル」モデルにおける「幻滅期」です。新しい技術やサービスは、登場直後にメディアによって過剰な期待(ハイプ)が煽られ、「過度な期待のピーク期」を迎えます。しかし、実際に使ってみると「期待したほどではなかった」「実用性に欠ける」といった現実が見え始めると、期待は急速に萎み、「幻滅のくぼ地(幻滅期)」へと突き落とされるのです。
2021年初頭に爆発的なブームとなった音声SNS「Clubhouse」は、この典型例です。当初は招待制という希少性も相まって大きな話題となりましたが、「リアルタイムでしか聞けない」「アーカイブが残らない」といった時間的コストの高さや、他SNSが同様の機能を実装したことで、急速にユーザーの関心を失いました。多くの人が「Clubhouseはオワコン」という言葉を口にしたのは、まさにこの幻滅期においてでした。
最後の審判〜大衆心理と「スノッブ効果」〜
これらのフィルターを乗り越え、社会に広く普及した流行にも、やがて終わりの時が訪れます。その引き金を引くのは、他ならぬ私たち大衆の心理です。
流行がピークに達すると、今度は「スノッบ効果」が働き始めます。これはバンドワゴン効果とは逆に、「他人とは違うものを持ちたい」という差別化への欲求です。流行の最先端を走っていたアーリーアダプターたちは、誰もが持つようになったモノから興味を失い、次の新しいものを探し始めます。
そして、大多数の人々は、特に明確な理由なく、ただ「なんとなく飽きた」という感覚を共有し始めます。これは、集団の調和を重んじる「同調圧力」の一つの現れとも言えるでしょう。誰かが「もう古いよね」と言い始めると、その空気が伝播し、集団全体が静かに次の流行へと関心を移していくのです。
「オワコン」という烙印は、特定の誰かが独断で押すものではありません。それは、アーリーアダプターによる「価値の発見」から始まり、メディアによる「期待の増幅」、キャズムや幻滅期という「市場の淘汰」を経て、最終的に大衆心理の静かな「関心の移行」によって完了する、一連の社会的・心理的なプロセスの最終結果なのです。それは個人の意志を超えた、巨大なリレー競走のゴールテープのようなものと言えるかもしれません。
不死身のコンテンツたち――なぜ彼らは「オワコン」にならないのか

流行が生まれては消える宿命にある一方で、まるでその法則に抗うかのように、何十年にもわたって輝き続ける「不死身のコンテンツ」が存在します。ポケットモンスター、スーパーマリオ、そしてディズニー。彼らはなぜ「オワコン」にならないのでしょうか。その秘密を探ることは、流行の寿命を分ける境界線を理解する上で、最大のヒントを与えてくれます。
「商品」ではなく「世界」を売る戦略
これらの長寿コンテンツに共通するのは、単一の「商品」を売っているのではなく、ファンが没入できる広大な「世界(IPエコシステム)」を構築している点です。
ポケットモンスターは、その代表格です。ゲームの発売を核としながら、アニメ、カードゲーム、映画、グッズなど、様々なメディアを連携させる「メディアミックス戦略」を展開しています。アニメを見てポケモンを好きになった子どもがゲームを始め、ゲームで遊んだ子が友達とカードで対戦する。このように、異なるメディアが相互に顧客を送り合うことで、巨大で強固なファンの循環システムが生まれています。その結果、ポケモンのIP(知的財産)が生み出した累計収益は、ミッキーマウスやスター・ウォーズをも上回り、世界一となっています。
ディズニーは、映画というメディアコンテンツと、テーマパークという物理的な体験空間を完璧にシナジーさせることで、「非日常の魔法の世界」を創り出しています。映画で見たプリンセスにパークで出会う体験は、ブランドへの愛着を強烈に深めます。彼らはアトラクションやグッズを売っているだけでなく、その世界観そのものを体験として提供しているのです。
そして任天堂は、自社の基本戦略を「任天堂IPに触れる人口の拡大」と明確に定義しています。映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』やテーマパーク『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、それ自体が収益源であると同時に、任天堂のIPに触れる新たな「接点」として機能します。これらの体験を通じてマリオを好きになった人々が、最終的に中核ビジネスであるゲーム専用機へと誘導される。この戦略的なエコシステムこそが、マリオを単なるゲームキャラクター以上の存在に押し上げているのです。
絶え間ない進化と「変わらない安心感」の両立
これらのコンテンツが長く愛されるもう一つの理由は、「変化」と「不変」の絶妙なバランスにあります。
スーパーマリオシリーズは、作品ごとに新しいアクションやギミックを導入し、プレイヤーを飽きさせません。しかし、ジャンプの感覚やコインを取った時の効果音といった、シリーズの根幹をなす「触り心地」は決して変わりません。ポケットモンスターもまた、世代ごとに新しいポケモンや舞台が登場し、常に新鮮な冒険を提供しますが、「ポケモンを捕まえ、育て、戦わせる」というシンプルなゲームプレイの核は一貫しています 53。
この「常に進化し続けるが、根幹は変わらない」という姿勢が、古くからのファンには「変わらない安心感」を、新しいファンには「現代的な面白さ」を提供します。ロングセラー商品に共通するこの戦略は、マンネリ化による陳腐化を防ぎながら、ブランドの核となる価値を守り続けるための、極めて高度な舵取りなのです 55。
コラム:「オワコン」という言葉の誕生
私たちが何気なく使っている「オワコン」という言葉。その起源を辿ると、日本の巨大匿名掲示板「2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)」に行き着きます。2010年頃、一世を風靡したアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズのファンたちの間で、「ハルヒは終わったコンテンツ」という書き込みがなされたのが始まりとされています。元々は特定のアニメファンが使っていた内輪の言葉が、インターネットの海を渡り、今やあらゆるジャンルで使われる一般的なスラングへと成長したのです。一つの言葉の誕生譚にも、文化のダイナミズムが凝縮されています。
一過性の流行と、時代を超えるクラシック。その違いは、単一の体験で完結するか、広大な世界への入り口となるか、という点に集約されるのかもしれません。
| 特徴 | 一過性の流行(例:Clubhouse, マリトッツォ) | 時代を超えるクラシック(例:ポケモン, ディズニー) |
| 中核価値 | 新奇性・時代性 | 世界観・情緒的繋がり |
| ビジネスモデル | 単一の商品・体験 | IPエコシステム・メディアミックス |
| 進化戦略 | 静的・限定的な変化 | 安定した核の周りでの継続的な進化 |
| ユーザーとの関係 | 一過性の消費 | 長期的な関係構築 |
ラザロ効果――「オワコン」が「エモい」に変わる時

「オワコン」の烙印は、必ずしも最終判決ではありません。一度は忘れ去られたはずのコンテンツが、時を経て奇跡の復活を遂げることがあります。まるで死から蘇ったラザロのように。この「リバイバル・ヒット」という現象は、流行のライフサイクルが単純な一方通行ではないことを教えてくれます。
テクノロジーが可能にした、世代を超える対話
近年、私たちは様々なリバイバルブームを目の当たりにしています。1980年代の日本の「シティポップ」、2000年代初頭の「Y2Kファッション」、そして「フィルムカメラ」や「カセットテープ」といったアナログメディア。
これらの復活劇の裏側には、二つの世代の異なる視線が交差しています。一つは、当時をリアルタイムで経験した世代の「ノスタルジー(懐かしさ)」。そしてもう一つは、それを全く知らない若いZ世代の「ノベルティ(新しさ)」です。彼らにとって、フィルム写真のざらついた質感や、シティポップの洗練されたメロディは、デジタルに囲まれた現代にはない「エモい」魅力として映るのです。
この世代間の対話を可能にしたのが、皮肉にも最新のテクノロジーです。YouTubeのレコメンドアルゴリズムが、竹内まりやの『プラスティック・ラヴ』を世界中のユーザーに届けたように、TikTokやInstagramといったSNSが、埋もれていた過去のコンテンツを掘り起こし、新たな文脈を与えて現代に蘇らせているのです。
フィルムカメラが、高画質化を追求するデジタルカメラへのアンチテーゼとして、「不便さ」や「一発勝負の緊張感」そのものに価値を見出されているように、リバイバルとは単なる過去の繰り返しではありません。それは、現代の価値観というフィルターを通して過去を再解釈し、新しい価値を創造するダイナミックなプロセスなのです。
奇跡の復活劇〜ファイナルファンタジーXIVの教訓〜
リバイバルの中でも、ひときわ劇的な物語を持つのが、オンラインゲーム『ファイナルファンタジーXIV』(FF14)です。2010年に発売された旧『FF14』は、ゲームとして致命的な欠陥を数多く抱え、プレイヤーやメディアから厳しい批判を浴びました。グラフィックへの過度なこだわりがゲーム体験を損ない、MMORPGというジャンルへの不勉強さが露呈した結果、発売と同時に「シリーズ史上最大の失敗作」として、これ以上ないほどの「オワコン」の烙印を押されたのです。
通常であれば、ここでサービスを終了してもおかしくありません。しかし、開発チームは前代未聞の決断を下します。失敗作である旧版の運営を続けながら、その裏で全く新しいゲームとして『FF14』をゼロから作り直すという、無謀とも思えるプロジェクトを始動させたのです。
新プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏率いるチームが最も重視したのは、失われた信頼の回復でした。彼らは、生放送などを通じて開発状況を徹底的にプレイヤーに公開し、寄せられるフィードバックに真摯に耳を傾け、それをゲームデザインに反映させていきました。それは、作り手が「面白いだろう」と信じるものを押し付けるのではなく、プレイヤーが「本当に面白い」と感じるものを共に作り上げるという、根本的な哲学の転換でした。
そして2013年、世界を一度滅ぼすというゲーム内イベントを経て、『新生エオルゼア』として生まれ変わったFF14は、世界中のプレイヤーから絶賛され、V字回復を遂げます。この物語は、たとえ最も絶望的な「オワコン」の状況からでも、ユーザーへの誠実な姿勢と、本質的な価値を追求する強い意志があれば、奇跡は起こせるという力強い教訓を私たちに示しています。
「オワコン」とは心の軌跡である
「オワコン」の烙印は誰が押すのか――。この問いから始まった私たちの探求の旅は、一つの結論にたどり着きました。その烙印を押す特定の「誰か」は存在しません。それは、流行の最先端を嗅ぎ分けるアーリーアダプターから、熱狂を増幅させるメディア、市場の現実を突きつけるキャズムの谷、そして最終的に私たち自身の集合的な心理に至るまで、様々なアクターがバトンをつなぐ、壮大なリレーの最終結果なのです。
しかし、見えてきたのは、それだけではありませんでした。
流行のライフサイクルは、単なる消費と忘却の物語ではないということです。それは、私たち人間の根源的な欲求を映し出す鏡のようなものです。
「他人とは違う存在でありたい」という願い(スノッブ効果)と、「社会に属していたい」という安心への渇望(バンドワゴン効果)。過ぎ去った日々への愛惜(ノスタルジー)と、まだ見ぬ未来への期待(イノベーション)。一つの流行が生まれ、頂点を極め、そして静かに忘れ去られていく様は、これら相反する欲求の間で揺れ動く、私たち自身の心の軌跡そのものなのです。
このメカニズムを理解すると、街角から消えたタピオカ店の跡地も、YouTubeで偶然出会った80年代の音楽も、単なる過去の遺物ではなく、私たちの社会が、そして私たち自身が生きてきた証として、新たな意味を帯びて見えてきます。
目まぐるしく移り変わる世界。その儚さの中にこそ、人間の営みの面白さと愛おしさが詰まっているのかもしれません。
テレビを悪く言うのは時代に合っているよ
編集者・ライターとして活動しながら、生粋のテレビっ子としてさまざまなメディアでその魅力を発信し続ける綿貫大介。なかでも彼が特に愛してやまないテレビドラマ『ロングバケーション』のセリフから、自身も実践している人生をより生きやすくするためのヒントを紹介する。
参考
- オワコンとは?何の略?言葉の意味や使い方を例文付きで解説! - ゼクシィ
- オワコン(終わったコンテンツ)とは?意味を分かりやすく解説 - IT用語辞典
- 「覚えていますか、マリトッツォを」本場で食べる、夢を叶えた結果 - withnews(ウィズニュース)
- マリトッツォ、そのブームと未来を考える|肉村ハム蔵 - note
- タピオカブームは終わったのか~美味しいインスタントの売れ残りを飲んで|門田和雄 - note
- タピオカ「元カレ」現象?タピオカが若者に大流行した理由と今の印象についての実態調査
- ゴンチャ、タピオカブーム終焉でも、店数を増やし続けられる納得の理由タピオカ屋はどこへ消えた!?明暗を分けるビジネスチャンスとマーケティング戦略に迫る!
- タピオカブームが去った後も国内年間利用者約3000万人突破の快進撃「ゴンチャ」苦境を乗り越えた秘策と改革 - CHANTO WEB
- タピオカブーム終了後に急成長…ゴンチャが熱狂的ファンを集める理由 なぜそれがやれたのか?
- タピオカブーム終焉後も好調なゴンチャ。個人店はメニュー増やしサバイバル【中華ビジネス戦記】 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
- イノベーター理論とは?5つの採用カテゴリーと普及プロセスを徹底解説 - LIBERARY LAB
- アーリーアダプターとは?イノベーター理論、成功事例も含めて解説 - マクロミル
- イノベーター理論をわかりやすく解説!【事例あり】 - 東大IPC−東京大学協創プラットフォーム開発株式会社
- マーケティング戦略に重要なアーリーアダプターの特徴、攻略法は?イノベーター理論と合わせて解説
- アーリーアダプターとは?新商品成功の鍵を理解活用する戦略を解説 - 株式会社NOBU
- 【バンドワゴン効果とは】有利な方についてしまう......多様な活用事例を紹介 - CANVAS
- バンドワゴン効果とは?事例で解説 - ウェブ戦略なら株式会社グラタス
- バンドワゴン効果とは?日常での事例やマーケティングでの活用方法、注意点を解説 - Chatwork
- 製品普及の壁「キャズム」:理解のためのイノベーター理論と市場調査 - 楽天インサイト
- キャズム理論とは?発生する原因や超えるためのポイント・事例を解説 - 武蔵野コンサルティング
- キャズムとは?イノベーション普及を左右する“溝”とその乗り越え方 - マクロミル
- ハイプ・サイクルとは?基本的な定義と各フェーズの理解ガイド - ザセールス
- ハイプ・サイクル(hype cycle) - 組織・人材開発のHRインスティテュート
- ガートナー社が発行するハイプ・サイクルとは何か?何の役に立つか?どう見るべきか?(2024年版) - コンサルのあんなこと、こんなこと
- 生成AIは必ず衰退する!?ハイプ・サイクルからわかること | 株式会社キヨスル
- クラブハウスの現在は?オワコン化や終了したとの声も【23年現状】 - SaaS型営業DX支援ツール「Sales Crowd」
- クラブハウスの現在 | 流行から衰退までの軌跡と今 - セルバ
- なぜClubhouseは人気急落したのか? 早々に辞めた人たちの本音 - マネーポストWEB
- 同一消費者内で発生する バンドワゴン効果とスノッブ効果* - Kobe University
- 創造性の喪失やストレスの増加につながる「同調圧力」 生じる原因と具体例を解説 - ELEMINIST
- 同調圧力とは? 集団行動に隠されたメリットと見過ごされるデメリット SNSとの因果関係とは?
- ポケモンが長期的に世界で愛され続けるビジネス的成功要因 - note
- ポケモンが海外でも人気の秘密とは?IP収益1位にしたメディアミックス展開を分析してみた
- ポケモンのマーケティング戦略とは?ターゲット拡大のビジネスモデルを解説 - Skettt
- 世界を席巻した日本発IP事例:ポケモンと鬼滅の刃に学ぶ - GIPI – Global IP Institute
- ディズニーの経営戦略とは|事業を成功に導く4つのポイントを解説 | MA-STARS
- なぜ東京ディズニーランドは人気があるのか。 サービス・マーケティングからの分析
- 夢と魔法の国を実現する技術、時代と共に変わるビジネスモデル【ディズニーの成功理由③】
- 『スーパーマリオ』の海外人気が高い理由を解説!人気のキャラクターや作品も紹介 - IP mag
- “集大成”のソフトに - 社長が訊く「スーパーマリオ25周年」
- 長年愛されるポケモン人気キャラクターの秘密 | 株式会社Delighted
- ポケモンの世界的長期人気の普遍的成功要因 - ハヤシ シュンスケ
- 【中小食品メーカーのマーケティング戦略】 第17回:いかにロングセラー商品を生み出すか
- モノが溢れ売れにくい時代にロングセラーになるための4つの条件 | ブログのスイッチ
- 【徹底解説】あなたの商品もロングセラーにできる!成功するブランドの共通点とは?
- ロングセラー商品の活性化のカギは消費者行動の理解にある | ゴウリカマーケティング株式会社
- 〝コン〟って何のこと?「オワコン」の意味と正しい使い方 - @DIME アットダイム
- なぜシティポップは海外で人気なのか?4つの理由を徹底解説 | GYOKKODO
- ひと昔前のカルチャーが流行るのはなぜ? 社会学でひも解くリバイバルブーム | 月と窓
- なぜリバイバルヒット?音楽流行の回帰の背景とは|chuan - note
- シティポップが世界で再評価される理由 YouTubeの影響力とは? - コロブロ
- 2Kとは?平成ギャル文化が世界的トレンド!再ブームのきっかけやファッションアイテムを紹介 #タウンワークマガジン
- フィルムカメラ(表現)にハマる理由 〜魅力について〜|TAKAHIRO | Vlogger - note
- 『新生FFXIV』はいかに“新生”を果たしたか――吉田直樹氏講演リポート【GDC 2014】 - ファミ通
- 【GDC 2014】旧『FFXIV』の失敗は『FFXI』の成功体験から来た慢心や映像偏重主義。吉田プロデューサーが語る『FFXIV』のこれまでとこれから - 電撃オンライン
- スクエニ「スクウェア・エニックス オープンカンファレンス 2012」吉田直樹氏が「FFXIV」を作り直した理由を語る - GAME Watch
- 【FF14】どん底から奇跡の復活を果たしたFF14の歴史解説【初心者】 - YouTube
- 【旧FF14】クソゲーが神ゲーに生まれ変わった!? 吉田Pの大改革